TOP > 藤村克裕雑記帳
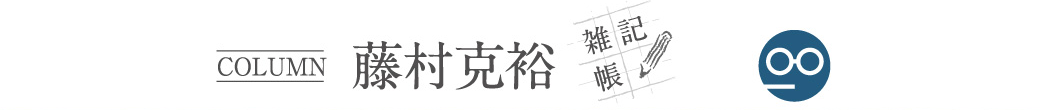

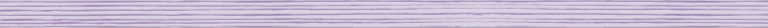
2021-09-07
- 色の不思議あれこれ207

- 「シンビズム」展を豊科でみた その3
- 豊科で見た「シンビズム」展の北澤一伯など
松澤宥氏に“沈潜”したあと、さらに廊下を先に進んで、ギョギョッとしてしまった。床に大量の角材が“二段重ね”でびっしりと敷き詰められている。部屋の中だけでなく廊下にも壁を挟み込むようになっている。二つある部屋の入り口の一つを取り外して廊下と部屋とを一体化させて敷き詰めているのだ。ところどころに、黒いもの白いもの透明なもの、いずれも小ぶりなものたち(正体不明である)が設置されている。
これは、北澤一伯氏の作品。タイトルは『場所の仕事 光の筏』。
確かに、これはこの場所のための作品だと言える。壁の凸凹にピッタリと合わせてあるだけでなく、取り外した扉の外枠の凸凹にもピッタリと合わせて細工してある。そういうディテールにも目は行くのだが、何と言っても、材木の物量感が迫ってくる。一般の柱材より一回り細いように見えるが本当にそうかどうか、判然としない。長さは、北澤氏によって何通りかに切り揃えられている。各所に「小ぶりなもの」たちを配するために凹部がある。二段ではなく一段のままにしてある箇所だ。そこにオブジェが設置してある。また、鉋がけしてあるのか、あるいは白いパテを塗り込んであるのか、材木の表面は滑らかで白い。その白さが照明の光を跳ね返している。木口もきちんと処理されている。“二段重ね”の柱材の全体が床からわずかに浮き上がっている。なるほど「筏」は浮かなければならない。浮かせるためにどうしているか、と床に手を膝とついて覗き込んでみると、厚い合板の板が敷かれている。床の養生もかねて、浮き上がる効果を呼び込んでいるのである。
北澤さんの作品を初めて見たのがいつだったか思い出せないが、床面にほとんど高さのない作品が直接設営されていた。今回の図録に収録されている赤羽義洋氏の「再生の彫刻」という文章を読むと、北澤さんにとって「台座」の問題は極めて重要だったことが分かる。ということは、今回の作品は、台座が浮いて部屋いっぱいに広がって、ついには部屋から廊下へとはみ出して、自らが彫刻として成立できるか、というチャレンジを含んでいる、と考えることもできる。 
- また、各所に配されて、リズムを成しているオブジェというか彫刻というかそのディテールが問題だが、よく見えない。手が届くところに置かれているものも正体不明である。白い大理石とかライムストーンによる彫刻? 珊瑚? 手作りガラス? 既製品の試験管? 錆びた鉄筋? ドライフラワー? などなど?
水平面からわずかにその一部をのぞかせるものたち、水平面上にあるものたち、何種類かの単位の長さの材木による構成的な効果、それらに何がしかの意味性、物語性を読み取る事ができるかもしれないが、私には判然としない。判然としないままでよい、と思った。
眩しささえ感じさせる 材木広がりの圧倒的な物量感やその多様な白さと散在するオブジェ群とのコンビネーションは北澤さん独自のものである。他に見たことがない。
他にも、丸田恭子氏の絵画、根岸芳郎氏の絵画、小林紀晴氏の写真、藤森照信氏の建築の写真、スケッチ、家具、マケット、というように見どころ満載であるが、すでに私の力が尽きた。
この「シンビウム」展は、前半がすでに上田市美術館で2月〜3月に開催されており、出品者は、小山利枝子、辰野登恵子、戸谷成雄、母袋俊也の4作家であった。これまでに3回開催されてきたが、今回の開催で一区切り、という事である。長野県というところの底力を感じさせられた。
(2021年9月6日 東京にて)
- [ 藤村克裕プロフィール ]

- 1951年生まれ 帯広出身
- 立体作家、元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員の藤村克裕先生のアートについてのコラムです。
- 1977年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。
- 1979年 東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修了。
- 元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員。
- [ 新着記事一覧 ]
-
- 2025-09-01
-
藤村克裕雑記帳アーカイブ300
ARCHIVE 2013 - 2025年
-
- 2025-09-01
-
藤村克裕雑記帳アーカイブ299
ARCHIVE 2025年
-
- 2025-09-01
-
藤村克裕雑記帳アーカイブ298
ARCHIVE 2024年
- [ INDEX ]
- ・261 ヴィム・ヴェンダースの映画『アンゼルム “傷ついた世界”の芸術家』と福田尚代氏の個展のこと
- ・262 小林嵯峨舞踏公演『幻の字の子供』
- ・263 『戦後の女性画家たちー有馬さとえ・朝倉摂・毛利眞美・小林喜巳子・招瑞娟ー』展を見た
- ・264 「神護寺 空海と真言密教のはじまり」展をみた
- ・265 東京都現代美術館「高橋龍太郎コレクション」展に行ってきた
- ・266 岡山県立美術館「藤原和通 そこにある音」展を見た その1
- ・267 岡山県立美術館「藤原和通 そこにある音」展を見た その2
- ・268 「北川民次展 メキシコから日本へ」を見た
- ・269 晴天の日(11月17日、11月19日)のこと
- ・270 雨模様の寒い日、「谷川さんの家」の方へ行ってみた
- ・281 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(1)
- ・282 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(2)
- ・283 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(3)
- ・284 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(4)
- ・285 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(5)
- ・286 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(6)
- ・287 ARCHIVE 2013年
- ・288 ARCHIVE 2014年
- ・289 ARCHIVE 2015年
- ・290 ARCHIVE 2016年
- [ ARCHIVE ]
当サイトに掲載されている個々の情報(文字、写真、イラスト等)は編集著作権物として著作権の対象となっています。無断で複製・転載することは、法律で禁止されております。
