TOP > 藤村克裕雑記帳
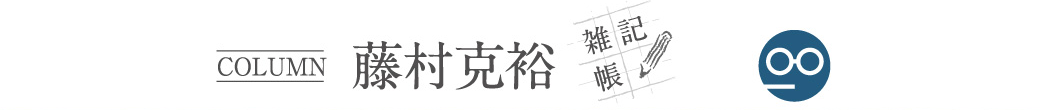

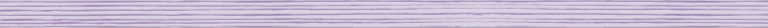
2025-09-01
- 藤村克裕雑記帳アーカイブ299

- ARCHIVE 2025年
- 2025-01-10
【271】埼玉県立近代美術館で「没後30年 木下佳通代」展をみた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=323
2025-01-21
【272】「ルイーズ・ブルジョワ展」に滑り込んだ
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=324
2025-02-06
【273】佐川晃司個展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=325
2025-02-12
【274】野村和弘個展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=326
2025-03-03
【275】『芸術新潮』の谷川俊太郎特集
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=327
2025-04-18
【276】「スペース23℃」での榎倉康二展(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=328
2025-04-18
【277】「スペース23℃」での榎倉康二展(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=329
2025-04-18
【278】「スペース23℃」での榎倉康二展(3)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=330
2025-05-22
【279】加藤啓、ゾフィー・トイバー&ジャン・アルプ、ヒルマ・アフ・クリント、岡﨑乾二郎など
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=331
2025-06-13
【280】「自由を扶くひと 望月桂」展を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=332
2025-07-17
【281】「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=333
2025-07-17
【282】「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=334
2025-07-17
【283】「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(3)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=335
2025-07-17
【284】「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(4)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=336
2025-07-17
【285】「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(5)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=337
2025-07-17
【286】「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(6)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=338 - → 藤村克裕雑記帳 アーカイブ目次へ
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/
- [ 藤村克裕プロフィール ]

- 1951年生まれ 帯広出身
- 立体作家、元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員の藤村克裕先生のアートについてのコラムです。
- 1977年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。
- 1979年 東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修了。
- 元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員。
- [ 新着記事一覧 ]
-
- 2025-09-01
-
藤村克裕雑記帳アーカイブ300
ARCHIVE 2013 - 2025年
-
- 2025-09-01
-
藤村克裕雑記帳アーカイブ299
ARCHIVE 2025年
-
- 2025-09-01
-
藤村克裕雑記帳アーカイブ298
ARCHIVE 2024年
- [ INDEX ]
- ・261 ヴィム・ヴェンダースの映画『アンゼルム “傷ついた世界”の芸術家』と福田尚代氏の個展のこと
- ・262 小林嵯峨舞踏公演『幻の字の子供』
- ・263 『戦後の女性画家たちー有馬さとえ・朝倉摂・毛利眞美・小林喜巳子・招瑞娟ー』展を見た
- ・264 「神護寺 空海と真言密教のはじまり」展をみた
- ・265 東京都現代美術館「高橋龍太郎コレクション」展に行ってきた
- ・266 岡山県立美術館「藤原和通 そこにある音」展を見た その1
- ・267 岡山県立美術館「藤原和通 そこにある音」展を見た その2
- ・268 「北川民次展 メキシコから日本へ」を見た
- ・269 晴天の日(11月17日、11月19日)のこと
- ・270 雨模様の寒い日、「谷川さんの家」の方へ行ってみた
- ・281 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(1)
- ・282 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(2)
- ・283 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(3)
- ・284 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(4)
- ・285 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(5)
- ・286 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(6)
- ・287 ARCHIVE 2013年
- ・288 ARCHIVE 2014年
- ・289 ARCHIVE 2015年
- ・290 ARCHIVE 2016年
- [ ARCHIVE ]
当サイトに掲載されている個々の情報(文字、写真、イラスト等)は編集著作権物として著作権の対象となっています。無断で複製・転載することは、法律で禁止されております。
