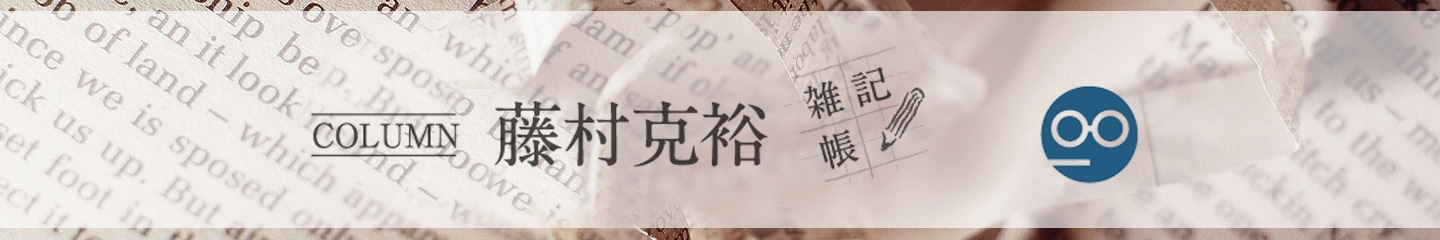

立体作家、元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員の藤村克裕先生のアートについてのコラムです。
藤村克裕 プロフィール
1977年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。
1979年 東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修了。
元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員。
最新コラム
2025-09-01
藤村克裕雑記帳アーカイブ300
ARCHIVE 2013 - 2025年
立体作家、元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員の藤村克裕先生のアートについてのコラムです。2013年4月から2025年7月まで当サイトで連載していた記事をアーカイブとして掲載しています。
コラムINDEX
ARCHIVE 2025年
2025-09-01
2025-01-10
【271】埼玉県立近代美術館で「没後30年 木下佳通代」展をみた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=323
2025-01-21
【272】「ルイーズ・ブルジョワ展」に滑り込んだ
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=324
2025-02-06
【273】佐川晃司個展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=325
2025-02-12
【274】野村和弘個展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=326
2025-03-03
【275】『芸術新潮』の谷川俊太郎特集
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=327
2025-04-18
【276】「スペース23℃」での榎倉康二展(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=328
2025-04-18
【277】「スペース23℃」での榎倉康二展(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=329
2025-04-18
【278】「スペース23℃」での榎倉康二展(3)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=330
2025-05-22
【279】加藤啓、ゾフィー・トイバー&ジャン・アルプ、ヒルマ・アフ・クリント、岡﨑乾二郎など
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=331
2025-06-13
【280】「自由を扶くひと 望月桂」展を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=332
2025-07-17
【281】「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=333
2025-07-17
【282】「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=334
2025-07-17
【283】「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(3)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=335
2025-07-17
【284】「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(4)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=336
2025-07-17
【285】「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(5)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=337
2025-07-17
【286】「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(6)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=338
【271】埼玉県立近代美術館で「没後30年 木下佳通代」展をみた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=323
2025-01-21
【272】「ルイーズ・ブルジョワ展」に滑り込んだ
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=324
2025-02-06
【273】佐川晃司個展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=325
2025-02-12
【274】野村和弘個展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=326
2025-03-03
【275】『芸術新潮』の谷川俊太郎特集
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=327
2025-04-18
【276】「スペース23℃」での榎倉康二展(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=328
2025-04-18
【277】「スペース23℃」での榎倉康二展(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=329
2025-04-18
【278】「スペース23℃」での榎倉康二展(3)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=330
2025-05-22
【279】加藤啓、ゾフィー・トイバー&ジャン・アルプ、ヒルマ・アフ・クリント、岡﨑乾二郎など
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=331
2025-06-13
【280】「自由を扶くひと 望月桂」展を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=332
2025-07-17
【281】「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=333
2025-07-17
【282】「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=334
2025-07-17
【283】「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(3)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=335
2025-07-17
【284】「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(4)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=336
2025-07-17
【285】「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(5)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=337
2025-07-17
【286】「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(6)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=338
ARCHIVE 2024年
2025-09-01
2024/1/9
【251】「アトリエ・トリゴヤ」と「ナミイタ」のことなど、
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=301
2024/1/22
【252】「みちのく いとしい仏たち」展を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=302
2024/1/29
【253】「《没後38年》 土方巽を語ること XⅢ」のこと
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=303
2024/4/8
【254】国立西洋美術館に傘を忘れてとりに行ってきた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=306
2024/4/9
【255】国立西洋美術館に傘を忘れて取りに行ってきた 2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=307
2024/4/10
【256】国立西洋美術館に忘れた傘をとりに行ってきた 3
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=308
2024/4/10
【257】国立西洋美術館に忘れた傘をとりに行ってきた 4
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=309
2024/5/7
【258】「中平卓馬 火|氾濫」展をめぐって
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=310
2024/6/4
【259】カール・アンドレ展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=311
2024/6/25
【260】「シルバーデー」に東京都現代美術館に行った
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=312
2024/6/28
【261】ヴィム・ヴェンダースの映画『アンゼルム “傷ついた世界”の芸術家』と福田尚代氏の個展のこと
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=313
2024/7/10
【262】小林嵯峨舞踏公演『幻の字の子供』
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=314
2024/8/2
【263】『戦後の女性画家たちー有馬さとえ・朝倉摂・毛利眞美・小林喜巳子・招瑞娟ー』展を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=315
2024/8/6
【264】「神護寺 空海と真言密教のはじまり」展をみた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=316
2024/8/14
【265】東京都現代美術館「高橋龍太郎コレクション」展に行ってきた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=317
2024/10/24
【266】岡山県立美術館「藤原和通 そこにある音」展を見た その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=318
2024-10-28
【267】岡山県立美術館「藤原和通 そこにある音」展を見た その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=319
2024-11-07
【268】「北川民次展 メキシコから日本へ」を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=320
2024-11-20
【269】晴天の日(11月17日、11月19日)のこと
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=321
2024-11-26
【270】雨模様の寒い日、「谷川さんの家」の方へ行ってみた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=322
【251】「アトリエ・トリゴヤ」と「ナミイタ」のことなど、
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=301
2024/1/22
【252】「みちのく いとしい仏たち」展を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=302
2024/1/29
【253】「《没後38年》 土方巽を語ること XⅢ」のこと
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=303
2024/4/8
【254】国立西洋美術館に傘を忘れてとりに行ってきた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=306
2024/4/9
【255】国立西洋美術館に傘を忘れて取りに行ってきた 2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=307
2024/4/10
【256】国立西洋美術館に忘れた傘をとりに行ってきた 3
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=308
2024/4/10
【257】国立西洋美術館に忘れた傘をとりに行ってきた 4
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=309
2024/5/7
【258】「中平卓馬 火|氾濫」展をめぐって
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=310
2024/6/4
【259】カール・アンドレ展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=311
2024/6/25
【260】「シルバーデー」に東京都現代美術館に行った
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=312
2024/6/28
【261】ヴィム・ヴェンダースの映画『アンゼルム “傷ついた世界”の芸術家』と福田尚代氏の個展のこと
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=313
2024/7/10
【262】小林嵯峨舞踏公演『幻の字の子供』
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=314
2024/8/2
【263】『戦後の女性画家たちー有馬さとえ・朝倉摂・毛利眞美・小林喜巳子・招瑞娟ー』展を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=315
2024/8/6
【264】「神護寺 空海と真言密教のはじまり」展をみた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=316
2024/8/14
【265】東京都現代美術館「高橋龍太郎コレクション」展に行ってきた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=317
2024/10/24
【266】岡山県立美術館「藤原和通 そこにある音」展を見た その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=318
2024-10-28
【267】岡山県立美術館「藤原和通 そこにある音」展を見た その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=319
2024-11-07
【268】「北川民次展 メキシコから日本へ」を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=320
2024-11-20
【269】晴天の日(11月17日、11月19日)のこと
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=321
2024-11-26
【270】雨模様の寒い日、「谷川さんの家」の方へ行ってみた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=322
ARCHIVE 2023年
2025-09-01
2023/3/13
【233】「小池照男のコスモロジー」AプログラムとBプログラムを見た日
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=282
2023/4/28
【234】サボっててごめんなさい!
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=283
2023/5/12
【235】「マティス展」をみた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=284
2023/5/25
【236】諏訪市美術館に立ち寄ってきた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=285
2023/6/12
【237】世田谷美術館への行き方を忘れてしまっていた日
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=286
2023/7/21
【238】何もはかどらない日々
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=287
2023/8/16
【239】若林奮を見にもう一度ムサビに行った
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=288
2023/8/18
【240】百人町のWHITE HOUSE 東京ステーションギャラリー
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=289
2023/9/14
【241】「ウポポイ」に行ってきた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=290
2023/9/21
【242】セザンヌを見に永青文庫に行った
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=291
2023/9/25
【243】お相撲、千秋楽
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=292
2023/10/23
【244】10月のこと 1、長谷宗悦氏の個展を見た(10月3日)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=293
2023/10/27
【245】10月のこと 2、林武史氏の個展を見た(10月7日)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=295
2023/11/6
【246】10月のこと 3、「風景論以後」展を見た(10月13日)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=296
2023/11/8
【247】10月のこと 4、アンジェイ・ワイダによるタディウシュ・カントル『死の教室』の映像を早稲田のshyで見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=297
2023/11/13
【248】「やまと絵」展をみた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=298
2023/12/4
【249】おお、もう12月ではないか!
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=299
2023/12/15
【250】岡﨑乾二郎『頭のうえを何かが』(ナナロク社、2023年)を読んだ
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=300
【233】「小池照男のコスモロジー」AプログラムとBプログラムを見た日
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=282
2023/4/28
【234】サボっててごめんなさい!
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=283
2023/5/12
【235】「マティス展」をみた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=284
2023/5/25
【236】諏訪市美術館に立ち寄ってきた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=285
2023/6/12
【237】世田谷美術館への行き方を忘れてしまっていた日
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=286
2023/7/21
【238】何もはかどらない日々
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=287
2023/8/16
【239】若林奮を見にもう一度ムサビに行った
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=288
2023/8/18
【240】百人町のWHITE HOUSE 東京ステーションギャラリー
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=289
2023/9/14
【241】「ウポポイ」に行ってきた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=290
2023/9/21
【242】セザンヌを見に永青文庫に行った
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=291
2023/9/25
【243】お相撲、千秋楽
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=292
2023/10/23
【244】10月のこと 1、長谷宗悦氏の個展を見た(10月3日)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=293
2023/10/27
【245】10月のこと 2、林武史氏の個展を見た(10月7日)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=295
2023/11/6
【246】10月のこと 3、「風景論以後」展を見た(10月13日)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=296
2023/11/8
【247】10月のこと 4、アンジェイ・ワイダによるタディウシュ・カントル『死の教室』の映像を早稲田のshyで見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=297
2023/11/13
【248】「やまと絵」展をみた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=298
2023/12/4
【249】おお、もう12月ではないか!
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=299
2023/12/15
【250】岡﨑乾二郎『頭のうえを何かが』(ナナロク社、2023年)を読んだ
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=300
ARCHIVE 2022年
2025-09-01
2022/1/20
【208】ゴッホ展を見てきた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=244
2022/1/20
【209】犬一匹に500万円!
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=245
2022/2/10
【210】府中美術館で「池内晶子:地のちからをあつめて」展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=246
2022/2/22
【211】高崎での空き時間に
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=247
2022/3/8
【212】松澤宥展を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=248
2022/3/8
【213】松澤宥展を見た その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=249
2022/3/9
【214】松澤宥展を見た その3
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=250
2022/3/28
【215】「香月泰男展」に滑り込んだ
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=251
2022/4/1
【216】「ロニ・ホーン展」にも滑り込んだ
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=252
2022/6/7
【217】近所の工事が巻き起こしていること
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=254
2022/6/27
【218】北海道づくしの日々
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=255
2022/7/5
【219】「彫刻刀が刻む戦後日本—2つの民衆版画運動」展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=257
2022/7/19
【220】パトリック・ボカノウスキーの映画『太陽の夢』を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=260
2022/8/22
【221】上野・国立西洋美術館に行ってきた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=261
2022/8/29
【222】笠間、茨城県陶芸美術館「井上雅之展」
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=262
2022/9/2
【223】「井上雅之展」補足
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=263
2022/9/5
【224】絶対音感の持ち主が音痴って
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=265
2022/9/9
【225】ルートヴィッヒ美術館展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=266
2022/9/30
【226】「フジオプロ旧社屋をこわすのだ !! 」展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=267
2022/10/3
【227】日曜日の東京都現代美術館
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=275
2022/10/17
【228】小杉武久の2022
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=276
2022/10/18
【229】「実験映画を見る会」
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=277
2022/10/31
【230】「試展ー白州模写『アートキャンプ白州』とは何だったのか」展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=278
2022/11/28
【231】正木さんが送ってくれた榎倉さんの資料群
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=279
2022/12/26
【232】正木さんが送ってくれた榎倉さんの資料群(つづき)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=280
【208】ゴッホ展を見てきた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=244
2022/1/20
【209】犬一匹に500万円!
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=245
2022/2/10
【210】府中美術館で「池内晶子:地のちからをあつめて」展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=246
2022/2/22
【211】高崎での空き時間に
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=247
2022/3/8
【212】松澤宥展を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=248
2022/3/8
【213】松澤宥展を見た その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=249
2022/3/9
【214】松澤宥展を見た その3
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=250
2022/3/28
【215】「香月泰男展」に滑り込んだ
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=251
2022/4/1
【216】「ロニ・ホーン展」にも滑り込んだ
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=252
2022/6/7
【217】近所の工事が巻き起こしていること
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=254
2022/6/27
【218】北海道づくしの日々
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=255
2022/7/5
【219】「彫刻刀が刻む戦後日本—2つの民衆版画運動」展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=257
2022/7/19
【220】パトリック・ボカノウスキーの映画『太陽の夢』を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=260
2022/8/22
【221】上野・国立西洋美術館に行ってきた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=261
2022/8/29
【222】笠間、茨城県陶芸美術館「井上雅之展」
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=262
2022/9/2
【223】「井上雅之展」補足
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=263
2022/9/5
【224】絶対音感の持ち主が音痴って
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=265
2022/9/9
【225】ルートヴィッヒ美術館展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=266
2022/9/30
【226】「フジオプロ旧社屋をこわすのだ !! 」展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=267
2022/10/3
【227】日曜日の東京都現代美術館
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=275
2022/10/17
【228】小杉武久の2022
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=276
2022/10/18
【229】「実験映画を見る会」
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=277
2022/10/31
【230】「試展ー白州模写『アートキャンプ白州』とは何だったのか」展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=278
2022/11/28
【231】正木さんが送ってくれた榎倉さんの資料群
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=279
2022/12/26
【232】正木さんが送ってくれた榎倉さんの資料群(つづき)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=280
ARCHIVE 2021年
2025-09-01
2021-01-20
【194】「絵画の見方」展など(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=229
2021/1/20
【195】「絵画の見方」展など(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=230
2021/2/12
【196】近美の常設展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=231
2021/3/15
【197】日下正彦「溢したミルク」展 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=233
2021/3/15
【198】日下正彦「溢したミルク」展 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=234
2021/4/13
【199】モンドリアン展に行ってきた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=235
2021/4/16
【200】写大ギャラリーの森山大道
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=236
2021/6/7
【201】「緊急事態宣言」下の美術館
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=237
2021/7/16
【202】小渕沢で16000歩
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=238
2021/8/2
【203】『かんらん舎大谷芳久の手探り』展を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=239
2021/8/30
【204】加藤翼「縄張りと島」展を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=240
2021/9/7
【205】「シンビズム展」を豊科で見た その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=241
2021/9/7
【206】「シンビズム」展を豊科で見た その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=242
2021/10/18
【207】「シンビズム」展を豊科でみた その3
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=243
【194】「絵画の見方」展など(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=229
2021/1/20
【195】「絵画の見方」展など(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=230
2021/2/12
【196】近美の常設展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=231
2021/3/15
【197】日下正彦「溢したミルク」展 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=233
2021/3/15
【198】日下正彦「溢したミルク」展 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=234
2021/4/13
【199】モンドリアン展に行ってきた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=235
2021/4/16
【200】写大ギャラリーの森山大道
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=236
2021/6/7
【201】「緊急事態宣言」下の美術館
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=237
2021/7/16
【202】小渕沢で16000歩
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=238
2021/8/2
【203】『かんらん舎大谷芳久の手探り』展を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=239
2021/8/30
【204】加藤翼「縄張りと島」展を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=240
2021/9/7
【205】「シンビズム展」を豊科で見た その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=241
2021/9/7
【206】「シンビズム」展を豊科で見た その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=242
2021/10/18
【207】「シンビズム」展を豊科でみた その3
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=243
ARCHIVE 2020年
2025-09-01
2020-01-14
【159】坂田一男展、田中睦治展、保科豊巳展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=191
2020-01-31
【160】「ハマスホイとデンマーク絵画」展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=192
2020-02-07
【161】府中市美術館「青木野枝 霧と鉄と山と」展をみた その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=193
2020-02-07
【162】府中市美術館「青木野枝 霧と鉄と山と」展をみた その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=194
2020-02-10
【163】ヒヤシンス・ハウス
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=195
2020-02-10
【164】森田恒友展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=196
2020-02-19
【165】風間サチ子展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=197
2020-02-19
【166】武蔵美の市ヶ谷キャンパス
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=198
2020-03-09
【167】「津田青楓展」を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=199
2020-04-21
【168】ルドン展の図録が出てきた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=200
2020-04-23
【169】『あべのますく』が届いた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=201
2020-05-01
【170】ミロ『農園』の写真図版を原寸大にカラーコピーしてみた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=204
2020-05-22
【171】東京ステーションギャラリー「神田日勝展」は開くだろうか
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=205
2020-05-25
【172】「神田日勝展」、開くのが ああ待ち遠しい その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=206
2020-05-25
【173】「神田日勝展」、開くのが ああ待ち遠しい その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=207
2020-06-11
【174】「神田日勝 大地への筆触」展 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=209
2020-06-11
【175】「神田日勝 大地への筆触」展 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=210
2020-06-11
【176】「神田日勝 大地への筆触」展 その3
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=211
2020-06-11
【177】「神田日勝 大地への筆触」展 その4
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=212
2020-06-15
【178】神田日勝とペインティング・ナイフ その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=213
2020-06-15
【179】神田日勝とペインティング・ナイフ その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=214
2020-07-22
【180】ロンドン・ナショナル・ギャラリー展を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=215
2020-07-30
【181】久しぶりの東京都現代美術館
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=216
2020-08-17
【182】梅雨が明けて
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=217
2020-08-17
【183】梅雨が明けて その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=218
2020-09-16
【184】アーティゾン美術館に行ってきた その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=219
2020-09-16
【185】アーティゾン美術館に行ってきた その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=220
2020-09-24
【186】横浜の川俣正
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=221
2020-10-02
【187】大津絵を見てきた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=222
2020-10-15
【188】ゲルハルト・リヒターがモデルの映画
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=223
2020-10-26
【189】「式場隆三郎『脳室反射鏡』」展をみた その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=224
2020-10-26
【190】「式場隆三郎『脳室反射鏡』」展をみた その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=225
2020-11-18
【191】東京国立博物館で『桃山・天下人の100年』展を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=226
2020-12-01
【192】相模原で「受験絵画」
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=227
2020-12-01
【193】高崎で「佐賀町」
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=228
【159】坂田一男展、田中睦治展、保科豊巳展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=191
2020-01-31
【160】「ハマスホイとデンマーク絵画」展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=192
2020-02-07
【161】府中市美術館「青木野枝 霧と鉄と山と」展をみた その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=193
2020-02-07
【162】府中市美術館「青木野枝 霧と鉄と山と」展をみた その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=194
2020-02-10
【163】ヒヤシンス・ハウス
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=195
2020-02-10
【164】森田恒友展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=196
2020-02-19
【165】風間サチ子展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=197
2020-02-19
【166】武蔵美の市ヶ谷キャンパス
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=198
2020-03-09
【167】「津田青楓展」を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=199
2020-04-21
【168】ルドン展の図録が出てきた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=200
2020-04-23
【169】『あべのますく』が届いた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=201
2020-05-01
【170】ミロ『農園』の写真図版を原寸大にカラーコピーしてみた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=204
2020-05-22
【171】東京ステーションギャラリー「神田日勝展」は開くだろうか
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=205
2020-05-25
【172】「神田日勝展」、開くのが ああ待ち遠しい その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=206
2020-05-25
【173】「神田日勝展」、開くのが ああ待ち遠しい その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=207
2020-06-11
【174】「神田日勝 大地への筆触」展 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=209
2020-06-11
【175】「神田日勝 大地への筆触」展 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=210
2020-06-11
【176】「神田日勝 大地への筆触」展 その3
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=211
2020-06-11
【177】「神田日勝 大地への筆触」展 その4
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=212
2020-06-15
【178】神田日勝とペインティング・ナイフ その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=213
2020-06-15
【179】神田日勝とペインティング・ナイフ その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=214
2020-07-22
【180】ロンドン・ナショナル・ギャラリー展を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=215
2020-07-30
【181】久しぶりの東京都現代美術館
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=216
2020-08-17
【182】梅雨が明けて
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=217
2020-08-17
【183】梅雨が明けて その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=218
2020-09-16
【184】アーティゾン美術館に行ってきた その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=219
2020-09-16
【185】アーティゾン美術館に行ってきた その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=220
2020-09-24
【186】横浜の川俣正
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=221
2020-10-02
【187】大津絵を見てきた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=222
2020-10-15
【188】ゲルハルト・リヒターがモデルの映画
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=223
2020-10-26
【189】「式場隆三郎『脳室反射鏡』」展をみた その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=224
2020-10-26
【190】「式場隆三郎『脳室反射鏡』」展をみた その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=225
2020-11-18
【191】東京国立博物館で『桃山・天下人の100年』展を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=226
2020-12-01
【192】相模原で「受験絵画」
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=227
2020-12-01
【193】高崎で「佐賀町」
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=228
ARCHIVE 2019年
2025-09-01
2019-01-08
【118】「吉村芳生」展と「フィリップス・コレクション展」をハシゴした。 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=146
2019-01-08
【119】「吉村芳生」展と「フィリップス・コレクション展」をハシゴした。 その2 https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=147
2019-01-21
【120】「辰野登恵子 オン・ペーパーズ」展に滑り込んだ
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=149
2019-02-08
【121】小伝馬町と相模原の松澤宥 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=150
2019-02-08
【122】小伝馬町と相模原の松澤宥 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=151
2019-02-28
【123】横浜で昼ご飯を食べた話
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=153
2019-03-22
【124】横浜を歩いた日 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=154
2019-03-22
【125】横浜を歩いた日 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=155
2019-03-28
【126】横浜でのこと・補遺 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=156
2019-03-28
【127】横浜でのこと・補遺 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=157
2019-04-02
【128】「VOCA」展、「表層の冒険」展、「百年の編み手たち」展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=158
2019-04-03
【129】「麻生三郎資料室」展を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=159
2019-04-25
【130】「櫛野展正のアウトサイド・ジャパン」展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=160
2019-05-17
【131】「このどうしようもない世界を笑いとばせ 福沢一郎展」 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=161
2019-05-17
【132】「このどうしようもない世界を笑いとばせ 福沢一郎展」 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=162
2019-05-24
【133】友人のムシの居所
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=163
2019-07-19
【134】土砂降りの国分寺駅に降り立った日のこと
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=165
2019-07-19
【135】土砂降りの国分寺駅に降り立った日のこと その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=166
2019-07-29
【136】「クリスチャン・ボルタンスキー」展を見た。 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=167
2019-07-29
【137】「クリスチャン・ボルタンスキー」展を見た。 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=168
2019-08-23
【138】あいちトリエンナーレ
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=169
2019-08-23
【139】小田原ビエンナーレ(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=170
2019-08-23
【140】小田原ビエンナーレ(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=171
2019-08-26
【141】室生寺釈迦如来坐像と坂本繁二郎 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=172
2019-08-26
【142】室生寺釈迦如来坐像と坂本繁二郎 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=173
2019-08-26
【143】室生寺釈迦如来坐像と坂本繁二郎 その3
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=174
2019-09-27
【144】応挙の絶筆にびっくりした日以降のこと その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=175
2019-09-27
【145】応挙の絶筆にびっくりした日以降のこと その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=176
2019-10-09
【146】岸田劉生展を見た日 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=177
2019-10-09
【147】岸田劉生展を見た日 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=178
2019-10-29
【148】バスキア展と独立展とをみた日 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=180
2019-10-29
【149】バスキア展と独立展とをみた日 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=181
2019-11-01
【150】「DECODE:出来事と記録」展 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=182
2019-11-01
【151】「DECODE:出来事と記録」展 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=183
2019-11-20
【152】キンビで見た「児童画」 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=184
2019-11-20
【153】キンビで見た「児童画」 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=185
2019-12-04
【154】目「非常にはっきりとわからない」展 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=186
2019-12-04
【155】目「非常にはっきりとわからない」展 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=187
2019-12-18
【156】「ダムタイプ」展 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=188
2019-12-18
【157】「ダムタイプ」展 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=189
【118】「吉村芳生」展と「フィリップス・コレクション展」をハシゴした。 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=146
2019-01-08
【119】「吉村芳生」展と「フィリップス・コレクション展」をハシゴした。 その2 https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=147
2019-01-21
【120】「辰野登恵子 オン・ペーパーズ」展に滑り込んだ
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=149
2019-02-08
【121】小伝馬町と相模原の松澤宥 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=150
2019-02-08
【122】小伝馬町と相模原の松澤宥 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=151
2019-02-28
【123】横浜で昼ご飯を食べた話
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=153
2019-03-22
【124】横浜を歩いた日 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=154
2019-03-22
【125】横浜を歩いた日 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=155
2019-03-28
【126】横浜でのこと・補遺 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=156
2019-03-28
【127】横浜でのこと・補遺 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=157
2019-04-02
【128】「VOCA」展、「表層の冒険」展、「百年の編み手たち」展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=158
2019-04-03
【129】「麻生三郎資料室」展を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=159
2019-04-25
【130】「櫛野展正のアウトサイド・ジャパン」展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=160
2019-05-17
【131】「このどうしようもない世界を笑いとばせ 福沢一郎展」 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=161
2019-05-17
【132】「このどうしようもない世界を笑いとばせ 福沢一郎展」 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=162
2019-05-24
【133】友人のムシの居所
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=163
2019-07-19
【134】土砂降りの国分寺駅に降り立った日のこと
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=165
2019-07-19
【135】土砂降りの国分寺駅に降り立った日のこと その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=166
2019-07-29
【136】「クリスチャン・ボルタンスキー」展を見た。 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=167
2019-07-29
【137】「クリスチャン・ボルタンスキー」展を見た。 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=168
2019-08-23
【138】あいちトリエンナーレ
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=169
2019-08-23
【139】小田原ビエンナーレ(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=170
2019-08-23
【140】小田原ビエンナーレ(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=171
2019-08-26
【141】室生寺釈迦如来坐像と坂本繁二郎 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=172
2019-08-26
【142】室生寺釈迦如来坐像と坂本繁二郎 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=173
2019-08-26
【143】室生寺釈迦如来坐像と坂本繁二郎 その3
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=174
2019-09-27
【144】応挙の絶筆にびっくりした日以降のこと その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=175
2019-09-27
【145】応挙の絶筆にびっくりした日以降のこと その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=176
2019-10-09
【146】岸田劉生展を見た日 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=177
2019-10-09
【147】岸田劉生展を見た日 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=178
2019-10-29
【148】バスキア展と独立展とをみた日 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=180
2019-10-29
【149】バスキア展と独立展とをみた日 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=181
2019-11-01
【150】「DECODE:出来事と記録」展 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=182
2019-11-01
【151】「DECODE:出来事と記録」展 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=183
2019-11-20
【152】キンビで見た「児童画」 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=184
2019-11-20
【153】キンビで見た「児童画」 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=185
2019-12-04
【154】目「非常にはっきりとわからない」展 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=186
2019-12-04
【155】目「非常にはっきりとわからない」展 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=187
2019-12-18
【156】「ダムタイプ」展 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=188
2019-12-18
【157】「ダムタイプ」展 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=189
ARCHIVE 2018年
2025-09-01
2018-01-23
【085】「熊谷守一 生きるよろこび」展をみた その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=108
2018-01-23
【086】「熊谷守一 生きるよろこび」展をみた その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=109
2018-01-23
【087】「熊谷守一 生きるよろこび」展をみた その3
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=110
2018-01-23
【088】「熊谷守一 生きるよろこび」展をみた その4
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=111
2018-01-23
【089】「熊谷守一 生きるよろこび」展をみた その5
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=112
2018-03-26
【090】『Spectator』誌の「つげ義春特集」 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=114
2018-03-26
【091】『Spectator』誌の「つげ義春特集」 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=115
2018-03-26
【092】『Spectator』誌の「つげ義春特集」 その3
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=116
2018-04-03
【093】VOCA展の上野公園
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=117
2018-05-01
【094】2018年4月19日、PlanB、原口典之+田中泯 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=118
2018-05-01
【095】2018年4月19日、PlanB、原口典之+田中泯 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=119
2018-07-12
【096】ゴードン・マッタ=クラーク展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=120
2018-07-12
【097】『ゴードン・マッタ=クラーク展』 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=121
2018-07-17
【098】ゴードン・マッタ=クラーク展 続き その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=122
2018-07-17
【099】ゴードン・マッタ=クラーク展 続き その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=124
2018-07-17
【100】ゴードン・マッタ=クラーク展 続き その3
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=125
2018-07-26
【101】三田まで出かけて迷って辿り着いた「蟻鱒鳶ル」
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=126
2018-08-21
【102】迎賓館に行ってみた その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=127
2018-08-21
【103】迎賓館に行ってみた その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=128
2018-09-13
【104】ゴードン・マッタ=クラーク展にまた行ってきた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=130
2018-09-13
【105】ゴードン・マッタ=クラーク展にまた行ってきた その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=131
2018-09-20
【106】無人の古本屋の噂を聞いて三鷹まで見物に行ってきた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=132
2018-09-25
【107】東武線の不思議な家
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=133
2018-10-04
【108】「おべんとう展」を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=135
2018-10-04
【109】岩手県一関市で
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=136
2018-10-18
【110】岩手県・一関の「アーティストラン・スペース空」 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=137
2018-10-18
【111】岩手県・一関の「アーティストラン・スペース空」 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=138
2018-10-31
【112】足利市立美術館「長重之展」 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=140
2018-10-31
【113】足利市立美術館「長重之展」 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=141
2018-11-09
【114】赤瀬川原平・未発表コラージュ展を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=142
2018-11-09
【115】赤瀬川原平・未発表コラージュ展を見た その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=143
2018-12-17
【116】ボナール展 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=144
2018-12-17
【117】ボナール展 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=145
【085】「熊谷守一 生きるよろこび」展をみた その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=108
2018-01-23
【086】「熊谷守一 生きるよろこび」展をみた その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=109
2018-01-23
【087】「熊谷守一 生きるよろこび」展をみた その3
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=110
2018-01-23
【088】「熊谷守一 生きるよろこび」展をみた その4
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=111
2018-01-23
【089】「熊谷守一 生きるよろこび」展をみた その5
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=112
2018-03-26
【090】『Spectator』誌の「つげ義春特集」 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=114
2018-03-26
【091】『Spectator』誌の「つげ義春特集」 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=115
2018-03-26
【092】『Spectator』誌の「つげ義春特集」 その3
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=116
2018-04-03
【093】VOCA展の上野公園
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=117
2018-05-01
【094】2018年4月19日、PlanB、原口典之+田中泯 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=118
2018-05-01
【095】2018年4月19日、PlanB、原口典之+田中泯 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=119
2018-07-12
【096】ゴードン・マッタ=クラーク展
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=120
2018-07-12
【097】『ゴードン・マッタ=クラーク展』 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=121
2018-07-17
【098】ゴードン・マッタ=クラーク展 続き その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=122
2018-07-17
【099】ゴードン・マッタ=クラーク展 続き その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=124
2018-07-17
【100】ゴードン・マッタ=クラーク展 続き その3
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=125
2018-07-26
【101】三田まで出かけて迷って辿り着いた「蟻鱒鳶ル」
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=126
2018-08-21
【102】迎賓館に行ってみた その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=127
2018-08-21
【103】迎賓館に行ってみた その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=128
2018-09-13
【104】ゴードン・マッタ=クラーク展にまた行ってきた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=130
2018-09-13
【105】ゴードン・マッタ=クラーク展にまた行ってきた その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=131
2018-09-20
【106】無人の古本屋の噂を聞いて三鷹まで見物に行ってきた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=132
2018-09-25
【107】東武線の不思議な家
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=133
2018-10-04
【108】「おべんとう展」を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=135
2018-10-04
【109】岩手県一関市で
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=136
2018-10-18
【110】岩手県・一関の「アーティストラン・スペース空」 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=137
2018-10-18
【111】岩手県・一関の「アーティストラン・スペース空」 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=138
2018-10-31
【112】足利市立美術館「長重之展」 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=140
2018-10-31
【113】足利市立美術館「長重之展」 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=141
2018-11-09
【114】赤瀬川原平・未発表コラージュ展を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=142
2018-11-09
【115】赤瀬川原平・未発表コラージュ展を見た その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=143
2018-12-17
【116】ボナール展 その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=144
2018-12-17
【117】ボナール展 その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=145
ARCHIVE 2017年
2025-09-01
2017-01-26
【059】岩槻に行ってきた(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=73
2017-02-02
【060】岩槻に行ってきた(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=78
2017-03-17
【061】井上洋介の絵画群にまみれて
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=79
2017-04-05
【062】井上洋介の絵画群にまみれて2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=80
2017-06-30
【063】草間彌生展にいってきた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=81
2017-06-30
【064】草間彌生展にいってきた2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=82
2017-07-07
【065】「丹下健三ってすごい、と思った日」その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=83
2017-07-07
【066】「丹下健三ってすごい、と思った日」その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=84
2017-07-12
【067】アンジェイ・ワイダ『残像』(2016年)をみた その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=85
2017-07-12
【068】アンジェイ・ワイダ『残像』(2016年)をみた その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=86
2017-08-01
【069】石川九楊展「書だ!」に行ってきた その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=87
2017-08-09
【070】石川九楊展「書だ!」に行ってきた その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=88
2017-08-09
【071】石川九楊展「書だ!」に行ってきた その3
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=89
2017-08-25
【072】「ジャコメッティ」展を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=91
2017-08-25
【073】再び「ジャコメッティ展」に行ってきた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=92
2017-09-06
【074】「極限芸術〜死刑囚は描く〜」展を見た その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=93
2017-09-06
【075】「極限芸術〜死刑囚は描く〜」展を見た その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=94
2017-10-10
【076】東京国立博物館で「運慶」展をみた その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=96
2017-10-10
【077】東京国立博物館で「運慶」展をみた その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=97
2017-10-10
【078】東京国立博物館で「運慶」展をみた その3
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=98
2017-10-12
【079】「古本屋ツアー・イン・ジャパン さすらいの十年」展をみた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=99
2017-10-17
【080】根本敬「樹海」を見に行ってきた その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=100
2017-10-17
【081】根本敬「樹海」を見に行ってきた その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=101
2017-11-06
【082】「運慶展」再び
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=103
2017-12-04
【083】「古代アンデス文明展」をみた その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=105
2017-12-04
【084】「古代アンデス文明展」をみた その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=106
【059】岩槻に行ってきた(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=73
2017-02-02
【060】岩槻に行ってきた(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=78
2017-03-17
【061】井上洋介の絵画群にまみれて
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=79
2017-04-05
【062】井上洋介の絵画群にまみれて2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=80
2017-06-30
【063】草間彌生展にいってきた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=81
2017-06-30
【064】草間彌生展にいってきた2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=82
2017-07-07
【065】「丹下健三ってすごい、と思った日」その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=83
2017-07-07
【066】「丹下健三ってすごい、と思った日」その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=84
2017-07-12
【067】アンジェイ・ワイダ『残像』(2016年)をみた その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=85
2017-07-12
【068】アンジェイ・ワイダ『残像』(2016年)をみた その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=86
2017-08-01
【069】石川九楊展「書だ!」に行ってきた その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=87
2017-08-09
【070】石川九楊展「書だ!」に行ってきた その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=88
2017-08-09
【071】石川九楊展「書だ!」に行ってきた その3
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=89
2017-08-25
【072】「ジャコメッティ」展を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=91
2017-08-25
【073】再び「ジャコメッティ展」に行ってきた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=92
2017-09-06
【074】「極限芸術〜死刑囚は描く〜」展を見た その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=93
2017-09-06
【075】「極限芸術〜死刑囚は描く〜」展を見た その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=94
2017-10-10
【076】東京国立博物館で「運慶」展をみた その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=96
2017-10-10
【077】東京国立博物館で「運慶」展をみた その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=97
2017-10-10
【078】東京国立博物館で「運慶」展をみた その3
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=98
2017-10-12
【079】「古本屋ツアー・イン・ジャパン さすらいの十年」展をみた
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=99
2017-10-17
【080】根本敬「樹海」を見に行ってきた その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=100
2017-10-17
【081】根本敬「樹海」を見に行ってきた その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=101
2017-11-06
【082】「運慶展」再び
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=103
2017-12-04
【083】「古代アンデス文明展」をみた その1
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=105
2017-12-04
【084】「古代アンデス文明展」をみた その2
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=106
ARCHIVE 2016年
2025-09-01
2016-01-13
【043】橋本での「スーパー・オープン・スタジオ」巡りをした(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=51
2016-01-15
【044】橋本での「スーパー・オープン・スタジオ」巡りをした(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=52
2016-01-18
【045】橋本での「スーパー・オープン・スタジオ」巡りをした(3)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=53
2016-02-12
【046】『一遍聖絵』を見た(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=54
2016-02-19
【047】『一遍聖絵』を見た(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=55
2016-03-14
【048】魔除けの展覧会・文化学園服飾博物館(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=56
2016-03-18
【049】魔除けの展覧会・文化学園服飾博物館(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=57
2016-06-06
【050】「女わざと自然とのかかわり・農を支えた東北の布たち」展(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=58
2016-06-06
【051】「女わざと自然とのかかわり・農を支えた東北の布たち」展(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=59
2016-06-20
【052】耳鳴りのこと
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=60
2016-07-22
【053】モランディ展のこと
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=61
2016-07-27
【054】モランディ展のこと・ふたたび
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=62
2016-08-19
【055】モランディ・さらに
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=63
2016-09-16
【056】若冲展のこと
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=64
2016-12-12
【057】「ラスコー展」に行って来た(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=69
2016-12-20
【058】「ラスコー展」に行ってきた(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=72
【043】橋本での「スーパー・オープン・スタジオ」巡りをした(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=51
2016-01-15
【044】橋本での「スーパー・オープン・スタジオ」巡りをした(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=52
2016-01-18
【045】橋本での「スーパー・オープン・スタジオ」巡りをした(3)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=53
2016-02-12
【046】『一遍聖絵』を見た(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=54
2016-02-19
【047】『一遍聖絵』を見た(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=55
2016-03-14
【048】魔除けの展覧会・文化学園服飾博物館(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=56
2016-03-18
【049】魔除けの展覧会・文化学園服飾博物館(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=57
2016-06-06
【050】「女わざと自然とのかかわり・農を支えた東北の布たち」展(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=58
2016-06-06
【051】「女わざと自然とのかかわり・農を支えた東北の布たち」展(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=59
2016-06-20
【052】耳鳴りのこと
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=60
2016-07-22
【053】モランディ展のこと
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=61
2016-07-27
【054】モランディ展のこと・ふたたび
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=62
2016-08-19
【055】モランディ・さらに
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=63
2016-09-16
【056】若冲展のこと
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=64
2016-12-12
【057】「ラスコー展」に行って来た(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=69
2016-12-20
【058】「ラスコー展」に行ってきた(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=72
ARCHIVE 2015年
2025-09-01
2015-01-20
【023】2014年12月京都で小谷元彦展を見た(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=23
2015-01-21
【024】2014年12月京都で小谷元彦展を見た(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=31
2015-01-26
【025】2014年12月京都で小谷元彦展を見た(3)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=32
2015-03-19
【026】ゴダールの3D映画をみた(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=33
2015-03-23
【027】ゴダールの3D映画をみた(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=34
2015-03-24
【028】ゴダールの3D映画をみた(3)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=35
2015-06-08
【029】昔、まだ小さかった義兄が枇杷を食べた(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=36
2015-06-10
【030】昔、まだ小さかった義兄が枇杷を食べた(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=37
2015-09-09
【031】『マスク展』を見た(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=38
2015-09-10
【032】『マスク展』を見た(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=39
2015-10-21
【033】井上有一展をみた(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=40
2015-10-22
【034】井上有一展をみた(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=41
2015-10-26
【035】井上有一展をみた(3)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=42
2015-11-04
【036】長新太の仕事(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=43
2015-11-10
【037】長新太の仕事(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=45
2015-11-13
【038】長新太の仕事(3)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=46
2015-11-19
【039】長新太の仕事(4)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=47
2015-12-26
【040】燕三条市に行ってきた(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=48
2015-12-26
【041】燕三条市に行ってきた(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=49
2015-12-26
【042】燕三条市に行ってきた(3)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=50
【023】2014年12月京都で小谷元彦展を見た(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=23
2015-01-21
【024】2014年12月京都で小谷元彦展を見た(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=31
2015-01-26
【025】2014年12月京都で小谷元彦展を見た(3)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=32
2015-03-19
【026】ゴダールの3D映画をみた(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=33
2015-03-23
【027】ゴダールの3D映画をみた(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=34
2015-03-24
【028】ゴダールの3D映画をみた(3)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=35
2015-06-08
【029】昔、まだ小さかった義兄が枇杷を食べた(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=36
2015-06-10
【030】昔、まだ小さかった義兄が枇杷を食べた(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=37
2015-09-09
【031】『マスク展』を見た(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=38
2015-09-10
【032】『マスク展』を見た(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=39
2015-10-21
【033】井上有一展をみた(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=40
2015-10-22
【034】井上有一展をみた(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=41
2015-10-26
【035】井上有一展をみた(3)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=42
2015-11-04
【036】長新太の仕事(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=43
2015-11-10
【037】長新太の仕事(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=45
2015-11-13
【038】長新太の仕事(3)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=46
2015-11-19
【039】長新太の仕事(4)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=47
2015-12-26
【040】燕三条市に行ってきた(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=48
2015-12-26
【041】燕三条市に行ってきた(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=49
2015-12-26
【042】燕三条市に行ってきた(3)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=50
ARCHIVE 2014年
2025-09-01
2014-06-23
【010】松本に行ってきた(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=10
2014-06-23
【011】松本に行ってきた(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=11
2014-06-23
【012】松本に行ってきた(3)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=12
2014-07-15
【013】福井で「藤本由紀夫展」を見た(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=13
2014-07-15
【014】福井で「藤本由紀夫展」を見た(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=14
2014-08-05
【015】画家・数野繁夫さんについて(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=15
2014-08-05
【016】画家・数野繁夫さんについて(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=16
2014-08-05
【017】画家・数野繁夫さんについて(3)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=17
2014-09-04
【018】関島寿子さんの作品を見た(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=18
2014-09-10
【019】関島寿子さんのトークを思い起こす(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=19
2014-09-16
【020】関島寿子さんのトークを思い起こす(3)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=20
2014-12-09
【021】宝塚歌劇団月組公演を見た日(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=21
2014-12-09
【022】宝塚歌劇団月組公演を見た日(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=22
【010】松本に行ってきた(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=10
2014-06-23
【011】松本に行ってきた(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=11
2014-06-23
【012】松本に行ってきた(3)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=12
2014-07-15
【013】福井で「藤本由紀夫展」を見た(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=13
2014-07-15
【014】福井で「藤本由紀夫展」を見た(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=14
2014-08-05
【015】画家・数野繁夫さんについて(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=15
2014-08-05
【016】画家・数野繁夫さんについて(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=16
2014-08-05
【017】画家・数野繁夫さんについて(3)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=17
2014-09-04
【018】関島寿子さんの作品を見た(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=18
2014-09-10
【019】関島寿子さんのトークを思い起こす(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=19
2014-09-16
【020】関島寿子さんのトークを思い起こす(3)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=20
2014-12-09
【021】宝塚歌劇団月組公演を見た日(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=21
2014-12-09
【022】宝塚歌劇団月組公演を見た日(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=22
ARCHIVE 2013年
2025-09-01
2013-04-15
【001】兵庫県立美術館で緑の照明に出くわした
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=1
2013-04-15
【002】ミッドタウンでイルミネーション見物
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=2
2013-06-06
【003】冬の光(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=3
2013-06-06
【004】冬の光(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=4
2013-07-02
【005】新井淳一さんってすごい
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=5
2013-07-08
【006】小山穂太郎展を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=6
2013-07-13
【007】円空展をみて考えたこと
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=7
2013-08-09
【008】山楽、山雪、応挙を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=8
2013-09-30
【009】櫻井英嘉さんのこと
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=9
【001】兵庫県立美術館で緑の照明に出くわした
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=1
2013-04-15
【002】ミッドタウンでイルミネーション見物
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=2
2013-06-06
【003】冬の光(1)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=3
2013-06-06
【004】冬の光(2)
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=4
2013-07-02
【005】新井淳一さんってすごい
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=5
2013-07-08
【006】小山穂太郎展を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=6
2013-07-13
【007】円空展をみて考えたこと
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=7
2013-08-09
【008】山楽、山雪、応挙を見た
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=8
2013-09-30
【009】櫻井英嘉さんのこと
https://www.gazaizukan.jp/fujicolumn/index.php?indid=9
「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(6)
2025-07-17
「O GREAT IN OUR DULL WORLD OF CLAY /秋風悠悠動軽波
THE MAID OF BUDA AND THE CARVEN WOOD /伐木之樵切水之魚」
2025年、樹脂、UV耐性コーティング、180.0×233.0×396.0cm。
この彫刻作品が今回最も大きな彫刻作品で、床に直に置かれていた。
乱暴な言い方をすれば、大きかろうが、小さかろうが、岡﨑氏の彫刻作品にあまり違いはないように私には思われる。
すでに、陶土を使った岡﨑氏の彫刻を知っている観客には、粘土のかたまりどうしを大胆に接合していくその作り方は、接合面というか、塊と塊との界面をこそ問題にしていることは明らかだからである。
界面という手がかりで考えてみれば、それはすでに「こづくえ」に始まっていたことは明らかであり、この場合、界面は、ナイフを入れて切り分け、その一方を折り曲げることであらわになった切断面がそれだった。界面があらわになった姿こそが「こづくえ」や「あかさかみつけ」シリーズ以来、岡﨑氏のレリーフ=彫刻の面白さだったのである。
また、かつて展開した二枚組の「絵画作品」。これらは、トレースとマスキングとによって成立していた。トレースした形状でマスキングして塗られた絵具の外郭=キワに出来上がる“厚み”もまた界面なのであった。
これらは、1990年代初頭、代官山のヒルサイドギャラリーで発表された平面を組み合わせた大きな立体や、新木場にあった南天子ギャラリーSOKOで発表された3種類9個による立体が問題にした界面のことが変容したものである(この時、立体作品と共に「絵画」作品も同時に発表されていたことを思い起こすとよい)。それは、やがて、石膏やブロンズや金網による彫刻作品に至り、種明かしのようなセラミックでの彫刻に至って、今回の展覧会での3Dプリンタを動員した巨大な出品作の数々に繋がってくる。こうした岡﨑氏の作品の流れを思い起こすと、そこには「界面」という問題意識が貫かれていることが見えてくる。
とはいえ、手の痕跡をほとんどとどめていない原型=その粘土の塊は、どう操作されて得られたのか、私にはまったく見当がつかない。ヘラなどで掻き取った痕跡が、ある種の“決め”の意思を示しているのだろうとは想像できるが、果たしてそれで“決まった”のかどうかさえ、よく分からない。土練機から取り出したばかりのような柔らかめの粘土を、板状に拡げて、それを巻き取りながら、さらに曲げたり、捻ったりしていったものだろうか。あるいは、ゴムのような伸び縮みする素材の布状のものに柔らかめの粘土を包み込んで操作しているのだろうか。
岡崎氏が最も原初的な材料といえる粘土を彫刻制作のために選んだことには、大きな意味がある。心棒のない塑像。
THE MAID OF BUDA AND THE CARVEN WOOD /伐木之樵切水之魚」
2025年、樹脂、UV耐性コーティング、180.0×233.0×396.0cm。
この彫刻作品が今回最も大きな彫刻作品で、床に直に置かれていた。
乱暴な言い方をすれば、大きかろうが、小さかろうが、岡﨑氏の彫刻作品にあまり違いはないように私には思われる。
すでに、陶土を使った岡﨑氏の彫刻を知っている観客には、粘土のかたまりどうしを大胆に接合していくその作り方は、接合面というか、塊と塊との界面をこそ問題にしていることは明らかだからである。
界面という手がかりで考えてみれば、それはすでに「こづくえ」に始まっていたことは明らかであり、この場合、界面は、ナイフを入れて切り分け、その一方を折り曲げることであらわになった切断面がそれだった。界面があらわになった姿こそが「こづくえ」や「あかさかみつけ」シリーズ以来、岡﨑氏のレリーフ=彫刻の面白さだったのである。
また、かつて展開した二枚組の「絵画作品」。これらは、トレースとマスキングとによって成立していた。トレースした形状でマスキングして塗られた絵具の外郭=キワに出来上がる“厚み”もまた界面なのであった。
これらは、1990年代初頭、代官山のヒルサイドギャラリーで発表された平面を組み合わせた大きな立体や、新木場にあった南天子ギャラリーSOKOで発表された3種類9個による立体が問題にした界面のことが変容したものである(この時、立体作品と共に「絵画」作品も同時に発表されていたことを思い起こすとよい)。それは、やがて、石膏やブロンズや金網による彫刻作品に至り、種明かしのようなセラミックでの彫刻に至って、今回の展覧会での3Dプリンタを動員した巨大な出品作の数々に繋がってくる。こうした岡﨑氏の作品の流れを思い起こすと、そこには「界面」という問題意識が貫かれていることが見えてくる。
とはいえ、手の痕跡をほとんどとどめていない原型=その粘土の塊は、どう操作されて得られたのか、私にはまったく見当がつかない。ヘラなどで掻き取った痕跡が、ある種の“決め”の意思を示しているのだろうとは想像できるが、果たしてそれで“決まった”のかどうかさえ、よく分からない。土練機から取り出したばかりのような柔らかめの粘土を、板状に拡げて、それを巻き取りながら、さらに曲げたり、捻ったりしていったものだろうか。あるいは、ゴムのような伸び縮みする素材の布状のものに柔らかめの粘土を包み込んで操作しているのだろうか。
岡崎氏が最も原初的な材料といえる粘土を彫刻制作のために選んだことには、大きな意味がある。心棒のない塑像。
「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(5)
2025-07-17
そしてまた、2019年作2点組の作品。先に見た「パネル絵画」とどう変化しているか。
右側の作品のタイトル。
「小さな鳥は北のほうから海上をかなり低く飛んできた。舟のへさきに止まった彼女はずいぶん疲れている。「旅は始めてかい?」言葉が伝わるよりも速く鳥は飛ぶ。言葉が消えぬ間に波は静まり太陽も戻ってきた。私はもう夢を見ることはない。けれど瞼の上に鳥が飛んでくる。青空にみるみる白い雲が棚引き、朗々たる声がはらはら雪のようにふってきた。「あの歌は誰が歌っているの」。砂浜にライオンがいる。「きみは幾つ?」ライオンは微笑む。ごらんなさい、ごらんなさい、わたしは幸せです。いつも挨拶を交わしていたけど、話をしたのははじめてなのです。」カンヴァス、アクリル、210.0×260.0×6.7cm(パネルは二種類、左側に210.0×78.0×6.7cm、その右側に210.0×52.0×6.7cm、その右側に78.0cm幅のパネル、その右側に52.0cm幅のパネル)
左側の作品のタイトル。
「静かな場所だった。聴こえているのは存在しない音楽。賑やかなのは私の耳のせい。波止場のざわめきは遠く、しとやかに聴こえる。まごまごしてここに迷い込んだ。眩しい光。こまごました磯の香り、イナサの風。あの島に行くつもり?舟の名は?アイオロス、一緒についていくさ。」カンヴァス、アクリル、210.0×130.0×6.7cm(パネルは二種類、左側に210.0×52.0×6.7cm、右側に210.0×78.0×6.7cm)
いずれの作品にも画面の上方と下方に布地の白さが横方向に拡がっていると同時に、パネルの連結部の縦線を越えて色の形が繋がる領域がなくなったわけではないが、この作品ではパネルの縦線で画面が断ち切られている印象が強く生じさせらている(パネルの縦の継ぎ目が目立っている)。が、そうしたパネルの縦線を横切って画面左上から右下へとわずかな傾斜を呈する動勢を感じさせている。色彩も、彩度の高い原色ではなくいわゆる中間色を用いている。塗りも比較的薄い印象だ。筆触(ヘラ触)はごく短い。これらが全体からの印象である。
右側の大きい作品から見ていこう。
右側の作品のタイトル。
「小さな鳥は北のほうから海上をかなり低く飛んできた。舟のへさきに止まった彼女はずいぶん疲れている。「旅は始めてかい?」言葉が伝わるよりも速く鳥は飛ぶ。言葉が消えぬ間に波は静まり太陽も戻ってきた。私はもう夢を見ることはない。けれど瞼の上に鳥が飛んでくる。青空にみるみる白い雲が棚引き、朗々たる声がはらはら雪のようにふってきた。「あの歌は誰が歌っているの」。砂浜にライオンがいる。「きみは幾つ?」ライオンは微笑む。ごらんなさい、ごらんなさい、わたしは幸せです。いつも挨拶を交わしていたけど、話をしたのははじめてなのです。」カンヴァス、アクリル、210.0×260.0×6.7cm(パネルは二種類、左側に210.0×78.0×6.7cm、その右側に210.0×52.0×6.7cm、その右側に78.0cm幅のパネル、その右側に52.0cm幅のパネル)
左側の作品のタイトル。
「静かな場所だった。聴こえているのは存在しない音楽。賑やかなのは私の耳のせい。波止場のざわめきは遠く、しとやかに聴こえる。まごまごしてここに迷い込んだ。眩しい光。こまごました磯の香り、イナサの風。あの島に行くつもり?舟の名は?アイオロス、一緒についていくさ。」カンヴァス、アクリル、210.0×130.0×6.7cm(パネルは二種類、左側に210.0×52.0×6.7cm、右側に210.0×78.0×6.7cm)
いずれの作品にも画面の上方と下方に布地の白さが横方向に拡がっていると同時に、パネルの連結部の縦線を越えて色の形が繋がる領域がなくなったわけではないが、この作品ではパネルの縦線で画面が断ち切られている印象が強く生じさせらている(パネルの縦の継ぎ目が目立っている)。が、そうしたパネルの縦線を横切って画面左上から右下へとわずかな傾斜を呈する動勢を感じさせている。色彩も、彩度の高い原色ではなくいわゆる中間色を用いている。塗りも比較的薄い印象だ。筆触(ヘラ触)はごく短い。これらが全体からの印象である。
右側の大きい作品から見ていこう。
「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(4)
2025-07-17
岡﨑氏が複数のパネルを連結させた絵画=「パネル絵画」を制作するようになったのは「2015年頃から」(『視覚のカイソウ』展の図録の記述による)というのだが、そのいささか暴力的な印象さえ感じさせる岡﨑氏の一連の作品群を、私はどう見ていいか分からず、判断を保留したままここまできた。その「パネル絵画」について、岡﨑氏は会場に掲げられたコメント文で次のように言っている。
・「パネル絵画」を本格的に展開し始めたのは2022年以降。
・それまでは、「縦長のパネルを水平に並べる程度の扱いに」留まっていた。
・この形式を使うのは、「大きな画面を作るために画面を分割する必要性」があったからでもある。
・それだけではなく、「画面にあらかじめ物理的比例関係を組み込んでおく」という理由がある。
・制作過程では、「パネル同士の隣接関係は可変的で何度となく入れ替えられる」。
分かりにくいので、私なりの解釈を加えて少し補足したい。
「大きな画面を作るために画面を分割する」というのは、「大きな画面」を分割して得ることができた小さなパネル同士を組み合わせて最終的にもう一度「大きな画面」を作り上げる、という意味だろう。
「画面にあらかじめ物理的比例関係を組み込んでおく」というのは、パネル同士の組み合わせ方の可能性をあらかじめ想定している、ということだろう。とはいえ、一度に全ての可能性を探るわけにはいかないから、「縦長のパネルを水平に並べる程度の扱い」から始めたのだろう。
制作過程において「パネル同士の隣接関係は可変的」、ということは、制作している時にはパネルを入れ替えたり、上下逆さまにもしたりしているが、岡﨑氏が完成したと判断した時以降には、パネル同士の結合は固定してもう入れ替えをしないし、させない、ということだろう。
そんなことを念頭に置いて、たとえば「パネル絵画」と取り組み始めて間もない2016年の作品を見てみる。3階フロアの「パネル絵画」群と比べる意味においてもこれは大事なことだ。「パネル絵画」をはじめて見た時、どう見ていいかまったく分からなかった、ということもある。そのリベンジを試みたい。長いタイトルを書き(打ち)写す。
2点組の作品である。
右側の作品
「あなたはこの水を乾かし、あるいは飲み干すだろう。けれど決して水は滅びない。水は姿を変え移動しただけである。水は乾くことなく、水がのどの渇きを癒すのだ。と似て、私の指一本いや手足を切り落とそうと、わたしは切り落とせない。姿を変える勝手気ままが水ではなく、わたし(の赤い水、血)ではない。水の中に水の姿に関わらぬ何か、として水の霊が宿っている(水が弾きだすと波と早合点しないように。波は音楽のようにあちこち拡がり増えたり減ったりするが、水の霊は増減せず分割もされない)。わたしは水の中にあり、泳ぎ、まどろみ、そして目覚める」
カンヴァスにアクリル絵の具、210.0×260.0×7.0cm。(この大きな作品=通常のカンヴァスのサイズでいうと400号弱の大きさになるが、ここで使われている縦長のパネルは4枚。寸法は二種類、210.0×108.0×7.0cm、210.0×72.0×7.0cm。それぞれ各2枚である。横幅の寸法が3対2の比率になっており、完成時には、両側に幅広のパネル、中央に幅の狭い方の2枚のパネルが結合されている。また、幅広のパネルの縦横の比率はほぼ2対1、幅が狭い方のパネルの比率はほぼ3対1である。)
左側の作品。
「宙空の箒/アウフヘーベン」
カンヴァスにアクリル絵具、25.0×18.0cm(会場で配布されていた「作品リスト」には厚みの寸法の記述がない)。「ゼロ・サムネイル」シリーズとほぼ同一の寸法と形式の作品だろう。「ゼロ・サムネイル」のシリーズには奇妙な“額縁”がついているが、この作品も例外ではない。
右側の作品と左側の作品との2枚組の作品は、今回の会場では仮設壁同士が成したコーナーを挟んで展示されているので、2点組というより、ひとつずつ独立した作品としても見える。2016年の制作というから、先の岡﨑氏のコメント文に従えば、「縦長のパネルを水平に並べる程度」の段階で、「パネル絵画」の可能性をまだ本格的には展開していない時期の初期作品である(2022年以降の作品は3階フロアにまとめて展示されている)。
・「パネル絵画」を本格的に展開し始めたのは2022年以降。
・それまでは、「縦長のパネルを水平に並べる程度の扱いに」留まっていた。
・この形式を使うのは、「大きな画面を作るために画面を分割する必要性」があったからでもある。
・それだけではなく、「画面にあらかじめ物理的比例関係を組み込んでおく」という理由がある。
・制作過程では、「パネル同士の隣接関係は可変的で何度となく入れ替えられる」。
分かりにくいので、私なりの解釈を加えて少し補足したい。
「大きな画面を作るために画面を分割する」というのは、「大きな画面」を分割して得ることができた小さなパネル同士を組み合わせて最終的にもう一度「大きな画面」を作り上げる、という意味だろう。
「画面にあらかじめ物理的比例関係を組み込んでおく」というのは、パネル同士の組み合わせ方の可能性をあらかじめ想定している、ということだろう。とはいえ、一度に全ての可能性を探るわけにはいかないから、「縦長のパネルを水平に並べる程度の扱い」から始めたのだろう。
制作過程において「パネル同士の隣接関係は可変的」、ということは、制作している時にはパネルを入れ替えたり、上下逆さまにもしたりしているが、岡﨑氏が完成したと判断した時以降には、パネル同士の結合は固定してもう入れ替えをしないし、させない、ということだろう。
そんなことを念頭に置いて、たとえば「パネル絵画」と取り組み始めて間もない2016年の作品を見てみる。3階フロアの「パネル絵画」群と比べる意味においてもこれは大事なことだ。「パネル絵画」をはじめて見た時、どう見ていいかまったく分からなかった、ということもある。そのリベンジを試みたい。長いタイトルを書き(打ち)写す。
2点組の作品である。
右側の作品
「あなたはこの水を乾かし、あるいは飲み干すだろう。けれど決して水は滅びない。水は姿を変え移動しただけである。水は乾くことなく、水がのどの渇きを癒すのだ。と似て、私の指一本いや手足を切り落とそうと、わたしは切り落とせない。姿を変える勝手気ままが水ではなく、わたし(の赤い水、血)ではない。水の中に水の姿に関わらぬ何か、として水の霊が宿っている(水が弾きだすと波と早合点しないように。波は音楽のようにあちこち拡がり増えたり減ったりするが、水の霊は増減せず分割もされない)。わたしは水の中にあり、泳ぎ、まどろみ、そして目覚める」
カンヴァスにアクリル絵の具、210.0×260.0×7.0cm。(この大きな作品=通常のカンヴァスのサイズでいうと400号弱の大きさになるが、ここで使われている縦長のパネルは4枚。寸法は二種類、210.0×108.0×7.0cm、210.0×72.0×7.0cm。それぞれ各2枚である。横幅の寸法が3対2の比率になっており、完成時には、両側に幅広のパネル、中央に幅の狭い方の2枚のパネルが結合されている。また、幅広のパネルの縦横の比率はほぼ2対1、幅が狭い方のパネルの比率はほぼ3対1である。)
左側の作品。
「宙空の箒/アウフヘーベン」
カンヴァスにアクリル絵具、25.0×18.0cm(会場で配布されていた「作品リスト」には厚みの寸法の記述がない)。「ゼロ・サムネイル」シリーズとほぼ同一の寸法と形式の作品だろう。「ゼロ・サムネイル」のシリーズには奇妙な“額縁”がついているが、この作品も例外ではない。
右側の作品と左側の作品との2枚組の作品は、今回の会場では仮設壁同士が成したコーナーを挟んで展示されているので、2点組というより、ひとつずつ独立した作品としても見える。2016年の制作というから、先の岡﨑氏のコメント文に従えば、「縦長のパネルを水平に並べる程度」の段階で、「パネル絵画」の可能性をまだ本格的には展開していない時期の初期作品である(2022年以降の作品は3階フロアにまとめて展示されている)。




















