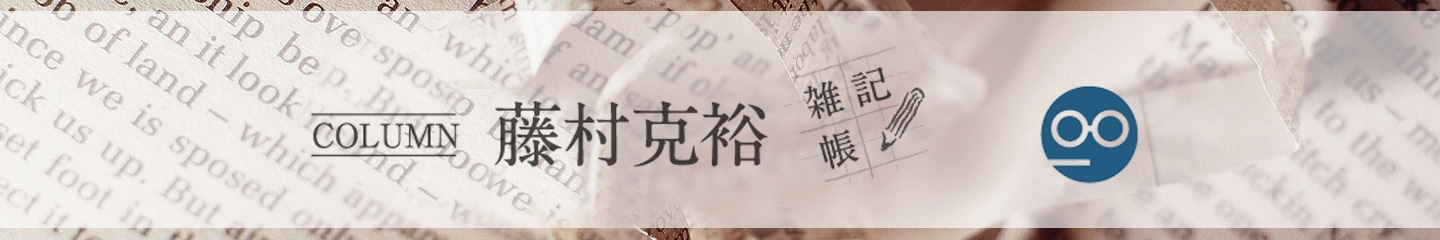

立体作家、元京都芸術大学教授の藤村克裕先生のアートについてのコラムです。
藤村克裕 プロフィール
1977年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。
1979年 東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修了。
内外の賞を数々受賞。
元京都芸術大学教授。
「自由を扶くひと 望月桂」展を見た
6月5日。ひさびさの晴天。東武東上線・東松山駅に降り立って、市内循環バスに乗り、「丸木美術館東」で下車、さらにテクテク西に向けて歩き、なんとか「原爆の図 丸木美術館」にたどり着いて、表記の展覧会を見た。晴れ渡った外は明るすぎるくらいだったのに、ほぼ半日、自然光がほとんどない環境にいたことになった。帰路、外がとてもまぶしかった。
展覧会タイトルの「扶く」を恥ずかしながら読めなかった。大昔、高校入学時に買わされた今やボロボロの『角川漢和中辞典』で調べて、やっと読めるようになった。「たすく」と読む。「望月桂」は、そのまま素直に「もちづきかつら」。
「原爆の図 丸木美術館」にははじめて行った。
この名高い美術館の名はもちろん知っていたが、「原爆の図」というハードさに対する気おくれ、あるいは複雑な思いがあって、訪れるには至らなかった。が、今回は、「望月桂」 という人の作品をぜひ見たかったので、意を決して行って来たのである。
最近、卯城竜太氏と松田修氏との対談を収めた『公(こう)の時代』(朝日出版社)という本をたまたま読んで、すごく感心したことは先にこの「雑記帳」に書いた。その本で、望月桂というひとや横井弘三というひとのことを初めて知ったことも書いたが、その後、偶然、この展覧会のことを知った。その時、これは見に行く、と決めて、その偶然に感謝した。
たどり着いた「丸木美術館」の入り口、その分厚そうな板の扉は閉じられていた。めげずに扉右手のガラス窓から声をかけ、奥に現れた女性からチケットを買った。入口扉を、えいっ、と押して、中に入ると、ホールがいきなりショップになっていて、いささか面食らった。右手はガラス窓越しに事務所、左手に二階への階段やトイレがある。右手前方に通路を見つけて、ぐんぐん進む。左手に二つ展示室があったが、これらを素通りしてさらにぐんぐん進んで、風間サチコ氏デザインという(あとで知った)ヘチマをあしらったロゴのある仮設壁の両側の、人が出入りできるほどの“すきま”、その右側から展示室に入った。すぐのところに出品目録があったので、メモ帳がわりにさせてもらった。
コラムINDEX
加藤啓、ゾフィー・トイバー&ジャン・アルプ、ヒルマ・アフ・クリント、岡崎乾二郎など
なんだか、文を書くのが困難になって、書けば、やたら長くなって時間がかかってしまう。読んでくださる方には迷惑な話、それはわかっている。わかっているが、どうすればいいのか自分ではわからない。そこで、文を書くことから意識的に離れてみたが、なにかが起きたわけではなかった。もとのもくあみ、である。
先日、地下鉄・丸ノ内線・四谷三丁目駅の近くの、「四谷ひろば」というところにある「四谷三丁目ランプ坂ギャラリーRAMP」で、加藤啓氏の展示と、それから別の日にパフォーマンスを見た。まったく知らなかった人だが、SNSへのある方の投稿に興味を覚えて、出かけて行った。
「四谷ひろば」は、かつて小学校だったところ。子供が減って、ここの小学校は閉じてしまった。そのあと、有志がここでさまざまな活動をしてきているようである。訪れた日には、体育館で居合の稽古が行われているのが見えた。稽古着に刀(模擬刀であろうが)姿の男女が十人ほど。居合は、人間を日本刀で斬ったり突き刺したりする技術の体系なので、ハタから見ているだけでこわい。なので、居合の見物はほどほどにして、ギャラリーに向かった。
ランプ坂ギャラリーには三つのスペースがある(廊下も含めれば四つ)。そのうちの最初の会場と廊下には、なにやら不思議な物品=人形やオブジェが、壁沿いや展示台の上にたくさん吊られたり置かれたりしていた。どうやら、海岸や川辺で拾い上げて持ち帰った流木や貝殻、プラスチックのゴミ、空き缶、‥‥などを相互に針金でつないでつくったもののようであった。会場を埋め尽くすほどの数の人形やオブジェ、片隅にはペンチや針金などが置かれた作業机もあって、どうやら会期中にも、そこで修繕や新作のための作業を行なっているようだ。会場に踏み込んだ時には、一見、雑然とした印象だったが、随所に工夫があるのがわかってくると、作者の細やかな視線や手ざわりがジワジワと伝わってくる。
ひとつひとつに見入ろうとしていると、奥の方からガラガラと音を立てて、大きな人形を持った背の高いやせた年かさの男性が現れて、横に渡して張ってあった針金にその人形からの針金を引っかけてふたたび奥に消えた。どうやらこれらをつくった加藤啓氏のようだ。修繕がすんだのだろうか。
ふたたび人形たちに見入ろうとしていると、ガッシャン! と大きな音がした。横に渡した針金が外れてさっきの人形が床に落ちてしまったのである。
慌てるでもなく、さっきの男性がもう一度現れて、外れた針金をあらため、床にうずくまって落ちた人形の具合を確かめ始めた。つい、お手伝いしましょうか? と声をかけると、いいえ、大丈夫です、と言った。背中が、放っておいて頂戴! と言っていたので、その場を離れ、人形のひとつひとつに見入っているうちに、男性のことを忘れてしまった。
言ってみれば「見立て」による仕事である。多く使われている流木にはできるだけ手を加えないように配慮されている。拾得物相互を針金で繋いで人間や動物や魚や鳥や虫などをつくる、と決めている。関節や節のところでつないであるから、動く。というか、動くように作っていく。操り人形としての仕掛けがこれも針金で加えられていく。とても面白い。強引すぎるような「見立て」さえたびたびなされ、そうなってくると俄然面白くなる。
二つ目の部屋にあったオブジェの方は、舟や船、楽器というか音具のようなもの、富士山、‥‥など。窓を巧みに使っている。展示に用いられているテーブルに、白い布がさりげなく掛けられているのが人形やオブジェへの愛情を感じさせている。ここにも多くの人形が吊り下げられている。
三つ目の部屋には、絵や紙で作ったレリーフが並んでいた。船や海をテーマとした作品群だった。
会場を二巡し、男性=加藤氏とお話しできた。人形やオブジェは鎌倉の海や三浦海岸で拾ったものでつくっている、と言った。昔、故大野一雄氏のところにいたことがある、とも言った。つまりダンスの心得がある人なのである。その後、新宿区の小学校の教員となって定年まで勤め上げたが、若い頃から緑内障で、いまは片方の目がほとんど見えない、とも言った。「ランプ坂ギャラリー」ではすでに何度も展示をしてきたという。展示のためのさりげない工夫がじつに合理的で感心させられたが、そのよってきたるところが理解できた。思わず、なにか買って帰りたくなって申し出ると、私がとりわけ気に入った作品は、パフォーマンスに使うので売れない、と言った。やむをえず、値段をつけて展示してある中から、ひとつ選んで買わせてもらった。いま、リビングの壁にぶら下げてある。とても気に入っている。
「スペース23℃」での榎倉康二展(3)
壁にピンッ!と直接張った大きな綿布上には、油=廃油を染み込ませた細長い板を綿布に押し当ててできたようなその板の痕跡めいた形状と、その形状からさらに滲み出たしみの形状とがあった。その形状と、その形状をなした細長い板それ自身とを組み合わせていく。あるものはその痕跡上に、あるものはそこからずらして固定し、つまり、今度は、作品の一部として色材=油=廃油と一体化した「版」が登場しただけでなく、「版」が布に作り上げた図像に対して、その「版」によってさらに“出来事”が生じている、ということが強調されたのである。
「版」自体が作品の一部として登場する版画作品の作例を、私はこの他に思い浮かべることができない。これは、榎倉氏独自の発想が展開したもの、と言えるだろう。その結果、「版」からの図像=“痕跡”だけでなく、そこからさらにしみがにじみ出ているという“出来事”、さらに「版」そのものが、その“痕跡”からずれたり、回転している、という出来事も生じていたのである。
それは、同じ年の10月10日~15日のときわ画廊個展で更なる展開を見せた。この時、作品は2点あって、互いに緊密に関係を及ぼし合って、画廊空間全体が作品化していた。「版」である細長い板は、壁に張られた大きな綿布上の図像=“痕跡”から離れて床上に置かれ、まるで実体と影とが反転したような不思議な印象をもたらし、それが2点の作品相互で緊密な関係性を生成させていたのである。私はこの時の榎倉作品に立ち会った時のことを今でもありありと思い出す。ときわ画廊の空間全体が緊張感に満ちていて、あまりにきれいで言葉を失った。こんなにきれいでいいのだろうか、とさえ思いながら立ち尽くしていた。
そのときわ画廊個展の一ヶ月後に「今日の作家’77 絵画の豊かさ」展(11月18日~29日)への出品、翌年(1978年)2月の東京画廊個展、さらに1978年6月からの「べニス・ビエンナーレ」出品、とこの「無題」のシリーズは繋がっていってひと区切りとなった。
その1978年の「ベニス・ビエンナーレ」への出品以降、最初に発表されたのが、今回、「スペース23℃」に展示されている3点を含む西村画廊個展(10月)と「今日の作家〈表現を仕組む〉」展(11月)への出品作「干渉率(空間に)」のシリーズだったのである。
やっと元のところへたどりつけた。回り道が過ぎたかもしれない。
この西村画廊個展と「今日の作家77 絵画の豊かさ」展では、制作時には「版」の役割を果たしていたはずの正方形の物体や他の物体(木っ端のようなもの)は、作品にまったく姿を見せていない。その痕跡だけを残して綿布上から消えたのである。観客は版であり色材でもあったはずの物体、つまり正方形をその一部に備えたなにかしらの物体や木っ端を、画面に残されたその痕跡=図像から想像するしかなくなった。版画では、「版」は、刷りが終われば用済みとなるのが普通なのだから、このシリーズで再び普通の版画の形式に立ち返った、とも言えるだろう。
「スペース23℃」での榎倉康二展(2)
その正方形の周囲に広がるにじみ=しみは、黒い色が油性であるゆえに綿布に生じているように見えるが、榎倉氏の手によってにじみ=しみのような表情を得るために“作られて”いるのかもしれず、本当のところが分からない。ここでも私(たち)は、このシリーズの作品以前の榎倉氏の代名詞のような油=廃油=しみの作品の展開をあらかじめ知っているがゆえに判断が危うくなってしまっている。
いずれにしても、今回展示されている「干渉率B(空間へ)」のシリーズでは、画面の中に、黒い正方形の形状をしたものが、唐突に放り出されたような印象を生じている。その理由として、一つには縫い目の水平との関係、二つには綿布の薄さと白さ、その面積の広がり、三つには正方形の傾き。また、会場に一緒に展示されている3点の写真作品がその印象を誘導している感があるのも否めない。
制作されてから長い年月が経ってしまったことが、綿布に散らばる無数の小さなシミからあらわである。この自然のしみが、榎倉氏のしみの作品にあらたな表情を刻々と加えているのだ。
余計なことだが、今回展示されている30号の「干渉率B(空間に‥‥)ーNo.2」は1978年10月23日~11月4日の西村画廊個展「干渉率」においての出品作の一つである。当時の図録に掲載されているからまちがいないだろう。ところが、この文の最初に述べた作品集『榎倉康二 KojiEnokura』の中の「資料編」の年譜の1978年の項には、西村画廊個展「干渉率」開催についての記載がない。理由は分からない。
「スペース23℃」での榎倉康二展(1)
過日、東京画廊+BTAPが、A4・ハードカバー・250ページ近くの大変美しい書物=『榎倉康二 Koji Enokura』を発行した。その発行を記念したシンポジウムがこの展覧会前に「スペース23℃」で非公開で開催されていた。シンポジウムには、当該書物に論考を寄せた熊谷伊佐子氏(美術評論家)、佐原しおり氏(東京国立近代美術館)、光田由里氏(多摩美術大学)、それから、
榎倉氏と1960年代初頭の“浪人時代”から濃密な付き合いがあった美術家・藤井博氏とが登場し、東京画廊の佐々木博之氏の司会でそれぞれ貴重な発言をした。その記録映像が展覧会場で流されていたが、会場でこのシンポジウムの映像をすべて視聴するのはきびしい。なぜって、とても長いから。幸い「スペース23℃」のホームページから視聴できる。
榎倉康二氏は、1995年10月、それまでの奥沢の自宅から現在地へと引越すために、その準備作業中に心筋梗塞で亡くなった。52歳だった。あれから30年経ったわけだ。
「スペース23℃」は、榎倉氏夫人の榎倉充代氏が、その引越し先の榎倉氏の仕事場になるはずだった部屋を展示スペースとして2000年に開設した。その後、庭に新たな小ぶりの建物=スペースをつくって、そこに移動し現在に至っている。自然光を取り込んだたいへん美しい空間である。
開設時には、榎倉康二氏の遺作展を四期にわたって開催し、その後も、榎倉氏の作品展や、榎倉氏の父君=画家・榎倉省吾氏の作品展、それから生前の榎倉康二氏と密接な関係があった作家達の個展など、着実な展示活動を継続してきている。じつは私も、榎倉氏と親しかった二人=故八田淳氏の遺作ドローイングや写真作品と資料類による展示、故藤原和通氏の初期作品の写真と資料による展示をさせていただいて、大変お世話になった。「スペース23℃」での榎倉展では、毎回、榎倉氏の作品やドローイング、それから他ではあまり見る機会のない資料も展示されるので、その都度発見や驚きがある。
今回の展示は、1977~78年の「干渉率B(空間に)」のシリーズからの3点と、これらの作品の“原型”と考えてもよさそうな1972年の写真作品「予兆ー鉛の塊・空間へA」のシリーズからの3点による構成である。これに、冒頭で述べたシンポジウムのビデオ映像が加わっている。
シリーズ『干渉率B(空間に)』からの3点は、100号が2点、30号が1点。いずれも、既製の木枠に張られた薄手の綿布(うっすらと木枠のシルエットが透けて見える)に、にじみ=しみをともなった黒い正方形の形状をひとつずつ配した作品である。正方形は、木枠の四辺から離れた任意の位置に、ある傾きを持って配されている(今回は展示されていないが、横長画面中央に正方形が水平・垂直にきっちり配された作品もあるようである)。
木枠に張られた綿布は、どれも、二枚の綿布を縫い合わせて作られており、その縫い目が水平に伸びている。そのことから、縫い目と黒い正方形の位置との関係を強く意識した設定であることが見て取れる。100号や30号の大きさなら一枚の綿布で事足りるのだから、わざわざ二枚の綿布を縫い合わせる必要はない。なのに、わざわざ縫い合わせている。このことからも、榎倉氏はこの作品で、縫い目の水平に特別な役割を担わせていたことは明らかである。
『芸術新潮』の谷川俊太郎特集
読み耽ったその日からすこし経って、用事で、古くからの知人と南阿佐ヶ谷駅で待ち合わせた。無事に落ち合って、その人の家へと並んで歩き始めながら、じつは、去年、吉増剛造の本で「阿佐ヶ谷の谷川さんの家へ」という文章を見つけて、谷川俊太郎の『道順』という詩を頼りにしてこの通りの南側一帯を随分歩き回ったけど、彼の家を見つけることはできなかった、と話した。知人は、じゃあ案内しよう、と遠回りしてくれた。そのうち、別の話に夢中になっていると、あ、ここだよ、とその人は立ち止まった。
なんともあっけなかった。
「不思議にひくい木造のお家」と吉増氏が書いていたその家のたたずまいは、想像していたのとは全く違っていたし、「犬」の字を丸で囲んだ四つの「登録標」はもちろん、表札もなかった。これじゃあ見つからない。
その日はさっさと用事を済ませて、あかるいうちに帰宅した。そして、ずっとこたつの上に置いたままの『芸術新潮』誌を手に取って、つい、もう一度読み耽った。
野村和弘個展
このギャラリーでは、かつて(今でも)私が驚嘆した(している)野村氏の作品=「色点の作品(ドット・ペインティング)」にかかわる展示がなされていた。
「色点の作品(ドット・ペインティング)」のシリーズから2点。1988年から1993年まで彼が滞在したドイツ・デュッセルドルフで、1989年から制作され始めたシリーズだ。
ドローイング3点。「色点の作品(ドット・ペインティング)」の発端から、「色点の作品(ドット・ペインティング)」の形式が確定するに至るまでの間に試みられたドローイング(群)からの3点である。
そして、今回の展示のメインをなす「封印されたタブロー形式の作品 2025/2009」。ドイツで制作されたこのシリーズの作品群のうちの101点を一点一点箱に入れてそれぞれ封印してしまった。その101箱を床に並べている。
会場の見かけは、極めてシンプルだが、大変に高密度の展示になっている。
思わず「封印した」ではなくて「封印してしまった」と書いた(打ち込んだ)。なぜそんなことをする? という私の複雑な思いがここに込められている。
封印を示す小さな赤丸印のシールが一つ一つの箱に8つずつ、箱の厚みをなす4辺以外の8つの辺の中央に、赤丸の直径部が箱の辺のエッジに重なるように(二つの面を跨ぐように)それぞれ貼り込んである。さらに、その上を幅広の透明接着テープで貼り込んである。じつに厳密な封印である。それらが縦に床に直接立てられ相互にピッタリと接する状態で並べてあるから、つまりは細長い直方体=角柱になって横たわっているのである。封印を示す赤丸の半円が二つ接することで正円となり、それらが几帳面に並んでいる。僅かに生じている正円からの誤差が、これら全てが手作業で成り立っていることを示す“しるし”になってもいる。
それぞれの箱の側面には、作品タイトル(=「WIE OFT ISST EVA DEN APFEL?」エヴァは、何回リンゴを食べる?)とこのシリーズの作品のための通し番号とをタイプ打ち(?)した“シール”を、同一寸法で箱の同一の場所に貼り込んでいる。
通し番号は「1ー39」からはじまり、最後が「1ー195」となっている。つまり、「1ー1」から「1ー38」まではこの作品に含まれておらず、封印されていないようである。「1ー195」が最後なので、ドイツで作られたのは195点、ということかもしれないが、確かなことは分からない。途中、いくつも番号が欠けていて、都合101箱。「1ー195」の通し番号が、封印された作品の中では最も“近作”だ、ということになる。
箱は、ボール紙製で作品のサイズよりひと回り大きいはずだがともかくは同一サイズで作ってあり、「タブロー形式」の作品がひとつ完成するたびに、箱も作って作品をその箱に収めてきたものである。もともと透明な接着テープを使って箱を作ってあったが、封印に際してさらにあらたな透明接着テープを十字に(赤丸の上になるように)貼り込んでいる。
一つ一つの箱の色に差異が生じているが、そのこともまた、それぞれの箱の中に一点一点異なった同じシリーズの作品を収めていることを示している。そのような封印された101点の「色点の作品(ドット・ペインティング)」なのである。
野村氏がこれら「タブロー形式」の作品を封印してしまったものを作品として発表したのは、2010年いわき市立美術館での東嶋毅氏との二人展の時だったはずだ。あの時、美術館2階の階段を取り巻くロビーの様なスペースの床と壁とが出会う領域のひとつに細長く直方体状に置かれたこれらを見た時、私にはにわかにその意味が理解できず、また野村氏が何故そんなことをするのか、ということにも思い至らなかった。そして、時を経るうちにこの「封印」のことを忘れてしまっていたのである。それがこうして久しぶりに人々の前に展示された。
会場にいた野村氏に尋ねれば、ドイツでは木枠に綿布を張ってそれにこのシリーズの作品を作っていたが、日本に持ち帰ったこれらの作品にカビが生えてしまった。それが封印を決断する大きな理由になった、とのことだった。修復することも考えたが封印することを選んだ、という。封印された101箱から成る直方体=角柱のこの作品の購入を申し出る個人や機関があったとしても、決して封印を解かないことを条件にする、ということも野村氏は言った。
決してまぜっ返そうとしたわけではないが、私はつい、どこかの銀行の貸金庫係みたいにこっそり封印を解いて中を見て、必要なら修復もして、知らん顔して、中身を入れ替えて、箱だけ元のように戻しておく人がいるんじゃないの? と尋ねてみたが、野村氏は取り合わなかった。つまり、決して封印は解かない。封印を解くことは許されないのである。
帰国後も続くこのシリーズの制作には、木枠に綿布ではなく、木製パネルに化繊布を使っている、ということも野村氏は言った。絵具はいずれもアクリル樹脂絵具とのことである。
「このシリーズ」、と書いた(打ち込んだ)。そもそも「タブロー形式」の作品=「色点の作品(ドット・ペインティング)」とはどんな作品なのか、それを共有するために、ギャラリー入口からの動線を無視することにはなるが、奥の壁に2点横に並んで展示されていた「色点の作品(ドット・ペインティング)」を少し詳しく見ていかなければならない。なお、「このシリーズ」には「タブロー形式」の他に壁に直接描く「壁画形式」と「ドローイング形式」とがある。今回は「タブロー形式」と「ドローイング形式」とのシリーズからの展示である。
佐川晃司個展
とはいえ、蓄えを使い果たした私どもが行けるところは限られて、一番手っ取り早いのが入場無料の画廊、それから美術館図書室や国立都立区立図書館、近所の公園などということになってしまった。外食などはもってのほかである。必要な時はおにぎりを持参する。高齢者のための東京都の無料パス(じつは有料で入手するんだけど)を極限まで有効利用して、どんどん繰り出していくのだ、という心意気である。
そんなわけで、過日、久しぶりにいくつかの画廊を訪れてみると、おお、なんということだろう、見応えある展示が目白押しだったのである。
まず、地下鉄・新富町駅に降り立って、7番出口から徒歩数分のヒノ・ギャラリー。
「佐川晃司展『半面性の樹塊』ー1990年を中心に」。
1985年から1999年の間に制作された油絵7点、ドローイング4点、合計11点を並べた自選展であった。
1985年というと、その3月に、佐川氏や彼の同期の川俣正氏、田中睦治氏、保科豊巳氏が東京藝大油画の大学院の博士課程を満期退学した年である(私は“ぷー”だった)。佐川氏は、その年の4月から京都精華大学の専任教員となって京都に移り住み、今日に至っている。大学教員としての彼の仕事の方は2024年3月の定年退職まできっちり勤め上げた。この間、国公私立美術館などでの個展やグループ展、東京、京都、大阪の画廊での個展というように、作品制作と発表とを着実に進めてきた。
ヒノ・ギャラリーでの作品展示は2022年3月に続き2回目。前回の発表は、東京ではかなり久しぶりの個展であったが、今回は1985年からの京都での生活・制作が始まって少ししてからの五年間ほどの取り組みを中心にした展示で、この時期に佐川氏が今日まで取り組み続けているテーマや方向を見出し、自らの取り組みの確信を得た、ということを示している。
今回の展示作品を時系列に沿って整理すれば、1985年の作品として「何処のドローイング」、1988年の作品として油彩「空き地F4号」、「空地No.3によるドローイング」「半面性の樹塊の原形ドローイング」、「しげみのスケッチ」、1989年の作品として油彩「空地120号」、同「空地F6号」、1990年の作品として油彩「半面性の樹塊No.2」、同「半面性の樹塊No.4」、同「半面性の樹塊No.5」、そして1999年の作品として「半面性の樹塊No.33」、ということになる。
「半面性の樹塊」のシリーズの「原形」は1988年にはドローイングとして現れ出ていたことが今回の展示で明らかにされているが、それまでに「何処」のシリーズ、「空地」のシリーズがあったことも示されている。「半面性の樹塊」のシリーズは1989年〜1990年あたりから本格的に大型の油彩画で繰り返し制作されてきて、とうに100作を超えていると伝え聞く。
となれば、1985年以前の作品は? ということにもなろうが、じつは、昨年(2024年)11月〜12月に京都精華大ギャラリーで、「Seika Artist File #2『Imagined Sceneries ー7つの心象風景をめぐる』」という展覧会が開催されて、ここに佐川氏は1981年〜2年頃に制作した作品を出品した(らしい)。つまり、この展覧会で、今回展示されている作品群以前の作品群が、ある程度まとめて公開されていたのである。
残念ながら、私はこの文の冒頭に記した拙宅の工事があって、その展示を見に行くことができなかった。見ることができていれば、このヒノ・ギャラリーでの展示はまた違って見えただろうし、2024、25年という時期に、学生時代や京都における最初期の作品を並べた佐川氏の意図をさらに身近に感じ取ることができただろう。それを思うと、見に行けなかったことがいかにも悔やまれる。
ヒノ・ギャラリーに踏み込んでまず目に飛び込んでくるのは、入り口右側壁に展示されている大型の絵画のヘリが壁面から僅かに浮いて展示されていることと、入口から対角線状の二つの壁に展示されていた「空地120号」(1989年)と「半面性の樹塊No.33」(1999年)であった。いずれも油彩の大作であるが、どちらかの作品から見始めなければならないので、私は横長の「空地120号」の方から見ることにした。
「ルイーズ・ブルジョワ展」に滑り込んだ
“ルイーズ・ブルジョワ展から帰ってきたところ、言っとくけど素晴らしかったわ”。
もちろん、“素晴らしかったぞなもし”、でも、“素晴らしかったべさ”、でも、他の言い方でもまったく構わないのだが、私は、まんまと美術館のこの仕掛けに乗せられてしまった。この展覧会は素晴らしかった。ぐうの音も出なかった。
何が素晴らしかったか?
ひとつひとつの作品への作家の圧倒的な集中度。そこに込められた作家の繊細さ、それを支え抜く作家の強さ。そして透徹した知性。
ルイーズ・ブルジョワといえば、私の場合、ただちに思い浮かぶのは「眠りⅡ」1967年や「花咲けるヤヌス」1968年や「少女(可憐版)」1968−1999年のような、どうしたって人間の性器を想起させる彫刻作品や、布を縫い合わせて作った頭像などのちょっとこわい人体彫刻や、どろどろした赤いドローイング群だった。ある時、「C.O.Y.O.T.E」1947-49年(1979年に改題、ピンクに塗装)を何かの本で知ったときは、意外に感じてすごく驚いたことを覚えている。1997年の横浜美術館での「『ルイーズ・ブルジョワ』展」は見ていない。森美術館へのアプローチにある巨大な蜘蛛の彫刻はさすがに知っていたが、しげしげと見ることもなく、ルイーズ・ブルジョアについても不勉強で、ほとんど何も知らずにここまできた。ふと気付いた時、いつのまにか年配の女性作家がぐいぐい頭角をあらわしてきていた、といった程度の認識だったのである。これは、とても恥ずかしい。じつは大変なキャリアの持ち主だった。
埼玉県立近代美術館で「没後30年 木下佳通代」展をみた
次の日(1月8日)は快晴。JR北浦和駅に降り立って、埼玉県立近代美術館「没後30年 木下佳通代」展に滑り込んだ。
関西(=神戸)を拠点に活動した木下佳通代氏がすでに亡くなっていたことや、亡くなって30年経っていたことさえまったく知らずにきたが、私の学生時代、この人の作品は美術雑誌などで頻繁に紹介されていた印象があって、この際、私自身のことを振り返る意味でも、その活動の流れを知っておきたい、と思ったのである。
展覧会は、木下氏の学生時代の作品から絶筆まで網羅的に展示されていて、資料展示もあって、丁寧に作られていたが、木下氏が絵画に回帰したという1982年以降1994年に亡くなるまでのあいだに限っても、通し番号で800の作品やドローイングを残したというし、それ以前の作品やドローイングを含めれば、総作品数は1200点以上になるというから、とてもそれら全て(=文字通りの全貌)を展示することは不可能で、大まかな歩みを示すにとどまったようにみえた。
だからかどうか、なんだか物足りない、という印象を抱えて帰路に着いた。
木下佳通代氏は1939年神戸市生まれ。中学生の時に油絵セットを買ってもらって美術部に入部し、高校で美術部の部長になったほどに絵に親しんだ。現役で京都市立芸術大学西洋画科に合格し、1962年の卒業後は神戸の中学校の教員をしながら制作・発表活動を続けた(発表活動はすでに学生時代から始めている)。この間、高校時代、文化祭で他の高校の美術部部長だった河口龍夫氏と知り合って、交際を続け、1963年に結婚した。結婚生活は短期間で終わったようだが、その間、河口氏らが1965年に結成した「前衛美術集団・グループ〈位〉」と行動を共にした(ただしメンバーではなかった)。離婚の時期が展示でも図録でも特定できないが、図録に掲載されている中村史子氏編の「年譜」には、1968年の項に「この頃までグループ〈位〉は活動を続けるが、木下は河口龍夫と袂を分かつ」とあるので、このあたりと考えていいだろう(私=フジムラは、以前勤務していた学校で河口龍夫氏ともご一緒したので、ご当人の風貌や身のこなし、語り口に直接触れている。しかし、不勉強で河口氏の作品やその展開については詳しくなく、今、資料も手元にない。お二人がご夫婦だったことも全く知らなかったので、ちょっと驚いた。同時に、なるほど、という気持ちが生じたことも白状しておく。なぜ、なるほど、なんだろう、という疑問が生じるがここでそこには触れない)。1970年にグループ〈位〉のメンバーだった奥田善巳氏と結婚。ふたりで喫茶店を営んだらしい。1971年、移転した場所で「美術教室アートルーム・トーア」を開設。これを主宰しながら制作と発表活動を続けた。1990年に乳がんの告知を受け、手術以外の治療法を求めて国内各地、ロスアンジェルスに複数の病院を訪ね、ロスアンジェルスの病院で治療を受けながら制作に励んだ。が、1994年神戸の病院で死去。55歳は若すぎる。
展覧会は三つの章で構成されていた。
雨模様の寒い日、「谷川さんの家」の方へ行ってみた
さむい、さむい、と言っているうちに、詩人・荒川洋治氏の「◯◯◯◯◯はさむい」というあの有名なフレーズを思い出したのだが、「◯◯◯◯◯」のところをどうしても思い出せない。こんなはずはない、と思うのだが思い出せない。
いつか古本屋で激安で買った『荒川洋治全詩集』を探し出して、さらにその中の『水駅』のところを探すと、あった。
「◯◯◯◯◯」には「口語の時代」と入る。
「口語の時代はさむい」。
「見附のみどりに」という詩のおしまいのほうに出てくる。
こうだ。
見附のみどりに
まなざし青くひくく
江戸は改代町への
みどりをすぎる
はるの見附
個々のみどりよ
朝だから
深くは追わぬ
ただ
草は高くでゆれている
妹は
濠ばたの
きよらかなしげみにはしりこみ
白いうちももをかくす
葉先のかぜのひとゆれがすむと
こらえていたちいさなしぶきの
すっかりかわいさのました音が
さわぐ葉陰をしばし
打つ
かけもどってくると
わたしのすがたがみえないのだ
なぜかもう
暗くなって
濠の波よせもきえ
女に向かう肌の押しが
さやかに効いた草のみちだけは
うすくついている
夢を見ればまた隠れあうこともできるが妹よ
江戸はさきごろおわったのだ
あれからのわたしは
遠く
ずいぶんと来た
いまわたしは、埼玉銀行新宿支店の白金のひかりをついてあるいている。ビルの破音。消えやすいその飛沫。口語の時代はさむい。葉陰のあのぬくもりを尾けてひとたび、打ちいでてみようか見附に。
晴天の日(11月17日、11月19日)のこと
ずいぶん多くの人たちが谷川氏のことを投稿していてそのことに驚いたが、PCを閉じ、ふと書棚に手を伸ばして、いつか古本市で激安で入手した吉増剛造『太陽の川』(小沢書店、1978年)という本を取り出して開いたら、まさにその開いたところに「阿佐ヶ谷の谷川さんの家へ」という文章があった。「谷川さんの家」って、谷川俊太郎氏の家のこと? 雑誌の写真図版で見たことがあるけど、きれいに片付いているんだよなあ、とか思って、しかし、あまりの符合にうろたえながら、つい読み出してしまった。
「阿佐ヶ谷の谷川さんの家へ、そう、昔はここに草原があって白い気球がぽっかり浮かんでいた。零歳から四歳くらいまでぼくはここに住んでいて戦争前夜の空気を呼吸していた。(略)」
と始まる吉増氏の10ページほどのその文章は、まさに谷川俊太郎氏の家に勝手に行ってみたこと=吉増氏に言わせると「谷川あるき」のことを書いていた。吉増氏が線路(中央線)を挟んで反対側に住んでいた幼い頃の記憶をたどりながらそこを前日に歩いてみたことも含めているので、時空が入り組んだ複雑な印象の文になっている。で、ここでは線路の反対側のこと=吉増氏の前日の散歩のことは省略。
「(略)「三彩」の編集者だった頃、隣にある谷川徹三氏のところに原稿を受け取るために行ったのが最初で、そのときもわたしは道に迷った。谷川さんの家附近は奇妙ないりくみかたをしていて、道に迷うと谷川宅を巻くようにしてさまようことになる。地下鉄南阿佐ケ谷駅から青梅街道をやや新宿よりにもどって右に折れ、ゆるい坂を下ってゆく少し低地のようなところに谷川さんのひらたい感じの木造の家がある。地形のせいだろうか、道が奇妙に枝分かれしていて迷うらしい。あたりには樹木も多くわたしは谷川さんのところにゆこうとして木立にそった細道を何度かゆききして迷った時の印象が強い。(略)新宿から「ゴワオワオワオと地下鉄がやってきて」(谷川俊太郎)それにのって南阿佐ヶ谷へやってきた。
(略)
「(略)地図はなし。谷川さんの御招待もなし。自分で「谷川あるき」と名付けているだけ。カメラと夏用の白いボストンバッグをもって。いや「地図」はこの詩。
煙草屋の角を右へ折れてください
足の悪い男の子が走ってゆきます
枯れかかった樫の木の下を通ると
ふと前世の記憶が戻ってくるかもしれません
道なりにゆるく小学校のほうに曲がって
(老人同士云い争う声が聞えるでしょうか)
訳もなく立ち止まってもいいんですよ
その時すれちがった一人の若い女の不幸に
あなたは一生立ちいる事ができないのです
でも口笛を吹いて下さって結構です
風がパン工場の匂いを運んできたら
十字路は気が向いたら左折して
ちょっとつまずいたりして石塀にそって
仕方なく歩いてくると表札が出ています
私はぼんやり煙草をふかしているでしょう
何のお話をしましょうか番茶をすすって
それともあなたは私の家を通り過ぎて
港のほうまでいらっしゃるのですか (谷川俊太郎「道順」)
やっぱり十分ほど迷って谷川家を巻くようにして杉並横丁の一隅谷川邸に出た。(略)」
そこで吉増氏は戸口に「犬の登録標が四つも」あるのを発見する。◯の中に「犬」という字=記号が縦書きの文中に四つ縦に並べてあるのが面白い。「ぼんやり煙草をふかしている」はずの谷川氏は不在のようす。
「(略)「道順」という詩にそって歩いてみるとおもしろいことに気づく。あの『道順』は谷川さんの家へ、ゆるやかなカーブをえがいて裏から入ってきて、戸口に出るようになっている。裏のほうは昔は沼地だったのか、幼い頃の谷川俊太郎氏の遊び場だったのか。「港のほう」という感じがよく判る。そのせいだろう小学校の金網越しに幻の塔もみえてきた。」
吉増氏のこの文章は、別の日、白樺湖畔での講演のために中央線に乗って信濃境駅を過ぎたあたりで感じたり考えたりしたことで終わっている。
今日(11月19日)の東京は、ちょっと寒いけどとっても天気がいい。こんな日は、この吉増氏の文章に従って「『ゴワオワオワオ』の地下鉄」に乗って南阿佐ヶ谷駅に降り立ち、吉増氏が「地図」として利用した詩を片手に、当てずっぽうに「谷川さんの家」の方へ散歩するのもいいなあ、と思った。
が、拙宅は今日も工事中。職人さんの仕事が終わらなければどこにも出かけることができないのだ。
その工事もやがて終わる。う、嬉しい。
「北川民次展 メキシコから日本へ」を見た
快晴の日曜日(文化の日)、田園都市線・用賀駅に降り立ってテクテク歩き出す。
象設計集団によるあの遊歩道は今も健在で、ほどなく国道に出て砧公園が見える。
せっかくだから樹々を愛でながら行こう、と信号待ちして国道を渡る。
公園に入って歩を進めれば、大きなクスやケヤキの堂々とした姿や木漏れ日が嬉しいはずが、奥に複数のテントがしつらえられていて人々が群がっており、拡声器からお姉さんの早口の大きな声がしている。拡声器だから大きな声は当たり前だが、イベントの真っ最中らしい。樹々どころではない。ホーホーのテイで世田谷美術館に逃げ込んだ。
チケットを買って、会場に入り、一点一点佇んで眺め入り、巡っていけば、ほう、こういう人だったのか、と興味深い。作品と資料、合わせて180点ほどが並んでいる、という。が、途中からなんだか時系列がよく分からなくなる。この人の経歴は複雑なのだ。とりわけ若い頃の移動はめまぐるしい。会場出口に掲げられていた年譜を参考に一度整理しておくことが必要だろう。
1894年静岡県生まれ。早稲田大学予科を経て、オレゴン州在住の兄を頼って1914年に渡米、しばらく西海岸で過ごすが、1916年シカゴを経てニューヨークに移り住む。働きながらアート・スチューデント・リーグで学び、1920年アメリカ南部へ向かう。1921年キューバに移るが、正体不明の日本人にお金やドローイングなどを入れたトランクを盗まれ、やがてメキシコ市に移る。1922年日本人医師を頼ってコスコマテペックに移る。1923年その医師と共に熱帯地方(ベラクルス州)に赴き、その後ひとりで放浪しながら絵を描き、メキシコ市で個展。1924年国立美術学校で学び三ヶ月で卒業。そこの校長からの推薦でチュルブスコ野外学校の画学生になる。1925年トラルパン野外美術学校の助手になる。1926年トラルパン野外美術学校に用務員として正式に勤務する。1928年国立芸術宮殿ギャラリーで個展。1929年二宮鉄野と結婚。1930年長女誕生。1931年ニューヨークでの「現代メキシコ作家とメキシコ派の作家展」に出品。シケイロスに会う。1932年トラルパン野外美術学校閉校、開校したタスコ野外美術学校に校長として勤務。メキシコを訪れた藤田嗣治との交友(翌年6月まで)。1935年シカゴ美術館内こども美術館で北川指導の子どもたちの「作品展」。国吉康雄、イサム・ノグチがタスコに来訪。1936年タスコ野外美術学校閉校、日本に帰国。
ここまでが主にメキシコで活動したおおまかな足跡である。会場には1921年作の油絵から展示されている。日本を離れてからメキシコを中心に22年経て帰国だ。続ける、、、。
1936年帰国後、瀬戸市(妻:鉄野の実家があった)に滞在する。1937年上京、豊島区長崎仲町(現千早町)に住む。二科展に出品、二科会会員。日動画廊で個展。1938年久保貞次郎来訪。1939年「海王丸」で沖縄、トラック諸島を巡る。長男誕生。1940年ニューヨーク近代美術館「メキシコ美術の2000年」展に「タスコの山B」が展示。1941年「コドモ文化会」を久保貞次郎らと設立。1942年絵本『マハウノツボ セトモノ/オハナシ』刊行。1943年二科会の活動停止。瀬戸市安戸に疎開。
ここまでが帰国後東京での活動の足跡だ。戦争、疎開、、、。藤田嗣治とは東京で再会したらしい。藤田1937年作の「北川民次の肖像」が展示されている。ご当人(北川民次)はこれを気に入らなかったようだ。
1944年瀬戸高等女学校の教員として赴任。1945年終戦。1946年再建二科展。1949年「名古屋動物園児童美術学校」開設。1951年瑞穂区に「北川児童美術学園」開設。
1955年1月メキシコ再訪。12月にニューヨークへ移動。1956年1月パリに滞在。スペイン、イタリアを経て5月に帰国。1965年以降壁画制作。1968年東春日井郡に移る。1974年妻の鉄野死去。1978年二科会会長。数ヶ月後に辞任、退会。筆を置く。1988年瀬戸市の病院に入院。1989年瀬戸市の病院で死去。
瀬戸市移住後のことは端折りすぎたかもしれない。
ともかく、早大予科時代に絵画に関心を持ち、やがて描き始め、日本を飛び出して20年以上を海外で生活と制作と続けて帰国し、戦争を経て、1978年に筆を置くまで、ほぼ休みなく活動したわけで、こんな人はそんなに多くないはずだ。パリではなく、日本→アメリカ→メキシコ→日本、というのも彼の独自性がうかがえる。
展示は、六つに“章立て”されて、その“章”ごとに時系列で並べられていて、時系列の把握が混乱してくる所以になってしまっている。回顧展であるなら、やはり時系列を大事にしてほしい、と思うのは私だけだろうか。
ともかく、以下のような構成であった。
Ⅰ 民衆へのまなざし、
Ⅱ 壁画と社会、
Ⅲ 幻想と象徴、
Ⅳ 都市と機械文明、
Ⅴ 美術教育と絵本の仕事、
エピローグ 再びメキシコへ。
会場を巡って、これは大変に器用な人だなあ、との印象が繰り返し押し寄せてきた。
一見、素朴で親しみやすい土俗的・民衆的な表情をたたえた作品群だが、注意深く見れば、多くの先人(例えばセザンヌ)や同時代人(例えばピカソ、リベラ、藤田嗣治、レジェなど)からかなりの影響を受けている様子が見て取れる。が、それをナマのまま晒すことがない。そこが、“器用さ”を感じさせるところである。影響を受けることを恐れないが、どんな影響もいったん良く“咀嚼”して自分のものにしていく、これがこの人の信条なのだろう。
そして、色感が独特である。多くは褐色系のグレイを基調にして、そこに白と黒とをアクセントのように配している。青や赤や緑などの原色もまた、褐色系のグレイに準じて彩度を抑え込みながら抑揚を加えて配している。
結果、破綻がない。かといって、鈍い、というわけではない。色どうしに独特の響き合いがある。後年、黒線で形状を囲い、鮮やかな色彩を用いるようになっても、こうした半調子を確立した時期を経ていることが効いている。
典型例として、1930年の作という40号ほどの油彩=「トラルバム霊園のお祭り」を見ていこう。
“大小の遠近法”と“重なりの遠近法”とを主に用い、おおらかな“線遠近法”を加味して地形や建物を巧みに構成して配し、そこに、さまざまな人物や物品を細部に至るまで丁寧に描き上げてある。
単純化しつつも線的に明快な形状の組み立ては、古典的な風格さえたたえていて、見飽きることがない。
岡山県立美術館「藤原和通 そこにある音」展を見た その2
この章ではイタリア時代の藤原氏の活動を「リキアーミ」を中心に紹介している。
さまざまな事情があったにしろ、結果的に藤原氏は「パリ青年ビエンナーレ」と「ベニスビエンナーレ」という“晴れ舞台”で構想していた巨大な「音具」を実現できなかった。立て続けのことで、しかも多くの人々を巻き込んでのことだから責任も生じただろう。当時の藤原氏の心中は想像するに余りある。
結局、そのままイタリア各地を転々としながら、やがて北イタリア山中(アルプス)の寒村パーレに落ち着き、バイオリンの弓を作りながら1988年までそこで暮らした。
岡山県立美術館「藤原和通 そこにある音」展を見た その1
藤原和通(ふじわらかずみち)氏は、「音楽」と「音」を、言うならば“命懸け”で追求した人だ。また、生涯、キノコに深い関心を寄せつづけた人でもあった。サービス精神が旺盛な人でもあった。1944年倉敷市に生まれ、2020年横浜市で亡くなった。
藤原氏の晩年、私は、何度か藤原氏の仕事場で話を伺う機会を得て、その仕事ぶりと人柄に魅了された。私は、この藤原和通という人を、「天才」だ、と確信しており、直接何度もお話を伺えた幸運を感謝している。
藤原氏が亡くなったことは長く藤原氏のアシスタントを務めた新江和美氏からの電話で知った。ともかく遺品が散逸しないようにアドバイスするのが精一杯だった。新江氏は厄介な事柄をひとつずつクリアして、新江氏自身が藤原氏の作品や各種資料を所蔵するかたちでそれらの散逸を防ぎ、現在もそれらの保管と整理・研究にあたっている(はずである)。その新江氏が今回の展覧会に全面的に協力した、と聞いた。新江氏と私とはちょっとした行き違いから、行き来がなくなって久しい。やむを得ないことと思っている。
担当学芸員の洪性孝(ホン ソンヒョ)氏とは一度下諏訪の松澤宥邸でお目にかかっていた。
この「藤原和通 そこにある音」展は素晴らしい。岡山県立美術館は、岡山県出身の藤原氏の活動を紹介するはじめての機会であることを充分に“自覚”して、藤原氏の活動の時系列に沿って「Prologue」と四つの章で構成しており、展示も勘所を外していない。実に見応えがある。とはいえ、必要だったと思われるデモンストレーションや観客の“体験”づくり、といった要素には課題も見えた。
「Prologue 音楽家・藤原和通」
水平の台の上に写真や資料を並べ、透明な板で作った箱状のカバーを台に被せている。反射で見づらいが、驚くべき展示である。藤原氏はよくこうしたものを手元に残していたものだ。
まず写真三点。
一点目、松の並木を背に、並んでしゃがむ小学生たちの前にすっくと立つ小学生・藤原少年の写真。
二点目、中学校のグラウンドでトロンボーンを吹く藤原少年の写真。
三点目については長くなる。
中学でトロンボーンを吹いていた少年が、倉敷青陵高校合唱部で音楽の先生から音楽室の鍵を預けられるほど信頼を受け、出入り自由、心ゆくまで音楽に浸り、やがて音楽家になる夢を抱いた。未確認情報ながら、京都大学法学部に合格するも夢断ち難く中退。大阪で学習塾をやっていたお姉さんを手伝ってお金を貯めて、オペラを作りたい、と上京した。その足で、当時、桐朋学園大学音楽学部教授もしていた作曲家・石井歓氏を大学に訪ねた。石井氏は合唱曲を多く作っていた。弟子にしてください、と頼み込んで、簡単な試験のあと弟子入りを許された。ふつうなら入試を経て大学で教わるだろう、と尋ねると、無駄を省きたかった、とこともなげに言った。このあたり、「天才」の片鱗が顔を覗かせている。
ただちに東京駅そばにあった中古楽器屋でピアノを買い、石井氏の諸々のことを手伝いながら懸命に学んだらしい。セリーの技法を身につけ、当時の超売れっ子の作曲家=宮川泰氏のまるでラクガキのような走り書きの楽譜の清書をはじめとするアルバイトなどにも精を出し、“むっちゃ”忙しくしているうちに沸々と疑問が湧いてきた。「音楽」は「音」で成り立っているのに「音」のことを何も知らない、自分の関心はどうやら「音」にあるようだ、「音」を追求したい、、、と石井氏の元を去った。とはいえ、そう単純でもないかもしれない。石井氏は、1966年に開設された愛知県立芸術大学に教授、音楽学部長として赴任したので、東京と名古屋との二拠点での生活になったのである。また、あのハチャトリアンのもとに留学した、という話もある。いずれも未確認情報である。
石井氏のもとを去って、このあたりが「天才」の面目躍如なのだが、なんと、奈良県の奥吉野に移り住む。雇ってください、と訪ねた先はなんでもあの川喜田半泥子の実家というか直系の家柄だった。体つきを見られて即座に、あんたにはムリ! と断られたが粘り、雇ってもらった。懸命に働いて、一年後には班長を任されるまでになった。班長だった時は、川で丸太を運ぶ仕事などをやっていたという。(ちなみに、あの熊谷守一も岐阜で同じような仕事をしていた時期があったはずである。)
と、ここまで来て、やっと三枚目の写真のことである。奥吉野の山を背景に三人、その中の一人として特徴的な樵(きこり)の帽子を被った藤原青年が写っている。
これら三枚の写真の横にはさらに驚くべき資料が置かれていた。
まず、見開きで置かれた「劇団新人会広報誌『新人会』1969」という印刷物。「『人斬り以蔵異聞』三幕」とあって、俳優陣、スタッフ陣の名前の並びの中に「音楽:藤原和通」と確認できる。その下に台本が置かれている。藤原氏はれっきとしたプロ劇団の芝居の音楽を作っていたのだ。
東京都現代美術館「高橋龍太郎コレクション」展に行ってきた
都営新宿線・菊川駅に降り立ち、普段ならそのままテクテク歩くのだが、暑すぎる。バスで行く。午前10時過ぎの菊川駅バス停には列ができていたが、そこは建物の日陰であった。そんな些細なことが嬉しい。程なくバスはやってきて現代美術館前に到着。「日本現代美術私観 高橋龍太郎コレクション」展に入った。
日本現代美術のコレクターとして名高い高橋龍太郎氏(1946〜)である。いまやそのコレクション総数は3500点を超えるという。それらの中から選んだ作品に、東京都現代美術館の収蔵作品を加えることで構成した展覧会(と聞いている)。なぜ、公立美術館が、個人のコレクションに依存した展覧会を開催するのか? 他人のフンドシで相撲を取るようなものではないか? というような疑問は当然のように浮かんでくるが、ともかくは一通り見てから考えてみることにした。この展覧会の担当は学芸員の藪前知子氏と聞いた。
入場後まず出くわしたのは、故久保守氏と故中原實氏の各一点ずつの油画作品だった。と、書いて(打ち込んで)みて、手が止まる。作品のサイズはもちろん、タイトルや制作年も記憶に残っていないことに気付かされるのだ。そんな時は、いつもなら、会場から持ち帰ってくる「出品目録」を頼りにできる。だが、この日には、なんと、「出品目録」が会場のどこにも置かれていなかったのである。
なので、会場から出る時に、入退場をチェックしているお姉さんに「出品目録」のことを尋ねてみた。そしたら、私どもでは分かりませんので少しお待ちください、と“係”の人を呼んでくれた。現れたその男性に(お名前も所属も聞きそびれた)、「出品目録」はいつできますか? と尋ねると、9月上旬には図録が刊行される予定なのでその頃には「出品目録」もできるはずですが、詳しいことは、当館のホームページからこの展覧会を検索して、「出品目録」に関する告知や「出品目録」の公開がなされるのを待ってもらえないでしょうか、とのことであった。
「出品目録」なしに展覧会の図録を作れるのか? なぜ図録の刊行時期と「出品目録」との公開が重なるのか? など数々の疑問が生じたが、食い下がっても、流行りの“カスハラ”になりかねないので、ほどほどにした。が、いかにも釈然としない。男性係員の方はとってもきちんとした方だったのに。
公立美術館の展覧会で、観客のために「出品目録」が準備されていないなんてことは、今まで私は経験したことがなかった。この事態はどう考えてもありえないことである。担当学芸員氏は(もちろん館長氏でも東京都知事氏でもいいけど)こうした事態に至った事情の説明を行い、その説明を含めて「出品目録」を少なくともホームページ上に可能な限り早く公開・配布すべきである。ぷんぷん!
で、この文を続けて書く(打ち込む)ために、しょうがないので、拙宅にあったはずの久保守氏と中原實氏の資料を探すことにした(ぷんぷん)。
結果、中原實氏の資料だけはなんとか見つけ出して取り出すことができた(前述の耐震補強工事を円滑に進めるために、現在、全ての荷物を“塊”にしているので思うように探し出せないのだ)。取り出せたのは、1989年に武蔵野市が発行した「中原實展」の図録だったが、中を繰れば、、、あった。当該油彩作品は1947年作の『杉の子』(167.0×135.0cm)だったのである。
もう一方の久保守氏作品だが、彼の資料が拙宅のどこにあるかは分かっている。が、その場所の前には、今、大きな荷物がいくつも積み重なって鎮座しているので、取り出すのは諦めた。展示されていた久保氏の作品は、空襲で焼け野原と化し何もかも無くなった後の冬の東京の風景を、おそらくは写生を元にして油絵として描いたのだろう、大変きちんとした絵であった。
これら二点、いずれも東京都現代美術館の所蔵。どちらも作者の本格的な技量をよく示すとてもいい絵であった。会場に置かれていて観客が自由に持ち帰ってよい「展覧会ガイド」(会場に掲げられていた文章と同じ文章が日英の二か国語で、加えて会場配置図とがA3両面に刷られている)によれば、この二作品からこの展覧会を開始したのには次のような理由がある、とのことであった。①二点とも高橋龍太郎氏が生まれた1946年頃に描かれた作品であること、②東京都現代美術館が扱う戦後美術(高橋龍太郎氏の「胎内記憶」と重なる50年間の美術)の起点に位置付けうる作品であること。なんだか、コジツケのような気がしないでもない。きっと多々あるであろう東京都現代美術館所蔵の1946年前後制作の作品群から、なぜこれら二点を選んだのか、という理由が曖昧なのではないか。加えて、高橋氏は、「いい絵」には興味がない、ということをYouTubeで閲覧可能なインタビューなどで繰り返し述べている。なのに、なぜ、この二作品で始めるのか、それが分からない。分からないが、思いがけない絵を見ることができたのはラッキーといえばラッキーであった。
これら二作品を掲げたスペースの床には什器を置いて、高橋氏の若き日の姿を捉えた写真や、吉本隆明『擬制の終焉』など学生当時の愛読書、編集に携わっていたというサルトル特集掲載の「三田新聞」のコピーなどをガラスケース越しに展示し、高橋氏の「胎内記憶」を暗示していた。これらを「胎内記憶」というのもなんだかなあ、と思ったが、こだわらずに先に進んだ。
「神護寺 空海と真言密教のはじまり」展をみた
朝刊が配達される音がする。ノロノロ起き上がって取りに行く。真っ先にテレビ欄を見ると、あれま、今日のNHK「日曜美術館」は表記の展覧会を特集するらしい。まずいぞ、これではどんどん混み始めるに違いない。「日曜美術館」の影響力はあなどれないのだ。で、急遽、このまま午前中に見物に行くことを決めた。東京国立博物館・「神護寺 空海と真言密教のはじまり」展。
9時半過ぎにJR上野駅・公園口に降り立ち、歩き出せば、国立西洋美術館チケット売り場から入り口あたりのわずかな日陰に二重三重の行列ができているのが見えて、焦る。国立科学博物館への道筋の左側にちょいとした“森”があるので、日陰を求めて樹々の間の遊歩道を進めば、白衣姿の野口英世氏のブロンズ像は、今日も試験管をかざして熱心に研究を続けている。ありがたいことだ。
さらに進めば、予想していたことではあるが、木立は途絶え木陰も無くなって、強い照り返しの広場に出なければならくなった。この先さらに、横断歩道を渡って係員に前売りチケットを示して博物館敷地内に入り、平成館までのあの長い道のりを進まねばならない。その間、日陰はない。が、私は進んでいく(えらい)。午前10時前とはいえ、すでに十分すぎる灼熱地獄。
やっと会場に辿り着いた。冷房がうれしい。
エスカレータで二階に進めば、入り口に「神護寺」との“墨書”が大きく掲げられている。空海の字のようでもあるが確信はない。左側壁を見れば、「神護寺」の境内の配置図がある。つい、これに見入った。
神護寺には、以前、まだ京都の学校に勤めていた時、東京からやってきた家人と合流して訪れたことがあった(学生時代の古美研(古美術研究旅行)では行っていないはずだ)。京都駅前からバスで行った。やはり暑い時だったような気がするが、曖昧である。バス停から坂や石段を登った。石段の先に門が見えた時の様子は覚えている。が、境内のことを思い出そうとしても、ほとんど何も覚えていない。図に示されているうち、覚えていたのは「かわらけ投げ」だけだった。あと、おそらくは金堂であろうか、楽しみにしていた「源頼朝像」、その実物大かどうか、ともかく大きな複製写真が置かれていて、それにひどくがっかりしたことを覚えている。本尊の「薬師如来立像」は遠くに見たような気もするが、確かでない。「高雄曼荼羅」はまったく記憶にない。その日、栂尾の高山寺まで足を伸ばそうかとも思っていたが、「鳥獣戯画」が見られる保証もないのでやめた。何も調べずに来てしまったバチが当たった。なんだかなさけない1日だった。そういうわけで、リベンジの意味もある。




















