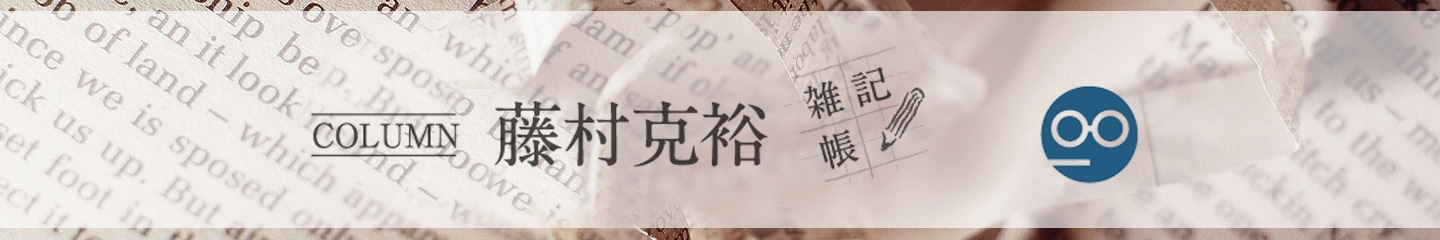

立体作家、元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員の藤村克裕先生のアートについてのコラムです。
藤村克裕 プロフィール
1977年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。
1979年 東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修了。
元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員。
「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(6)
2025-07-17
「O GREAT IN OUR DULL WORLD OF CLAY /秋風悠悠動軽波
THE MAID OF BUDA AND THE CARVEN WOOD /伐木之樵切水之魚」
2025年、樹脂、UV耐性コーティング、180.0×233.0×396.0cm。
この彫刻作品が今回最も大きな彫刻作品で、床に直に置かれていた。
乱暴な言い方をすれば、大きかろうが、小さかろうが、岡﨑氏の彫刻作品にあまり違いはないように私には思われる。
すでに、陶土を使った岡﨑氏の彫刻を知っている観客には、粘土のかたまりどうしを大胆に接合していくその作り方は、接合面というか、塊と塊との界面をこそ問題にしていることは明らかだからである。
界面という手がかりで考えてみれば、それはすでに「こづくえ」に始まっていたことは明らかであり、この場合、界面は、ナイフを入れて切り分け、その一方を折り曲げることであらわになった切断面がそれだった。界面があらわになった姿こそが「こづくえ」や「あかさかみつけ」シリーズ以来、岡﨑氏のレリーフ=彫刻の面白さだったのである。
また、かつて展開した二枚組の「絵画作品」。これらは、トレースとマスキングとによって成立していた。トレースした形状でマスキングして塗られた絵具の外郭=キワに出来上がる“厚み”もまた界面なのであった。
これらは、1990年代初頭、代官山のヒルサイドギャラリーで発表された平面を組み合わせた大きな立体や、新木場にあった南天子ギャラリーSOKOで発表された3種類9個による立体が問題にした界面のことが変容したものである(この時、立体作品と共に「絵画」作品も同時に発表されていたことを思い起こすとよい)。それは、やがて、石膏やブロンズや金網による彫刻作品に至り、種明かしのようなセラミックでの彫刻に至って、今回の展覧会での3Dプリンタを動員した巨大な出品作の数々に繋がってくる。こうした岡﨑氏の作品の流れを思い起こすと、そこには「界面」という問題意識が貫かれていることが見えてくる。
とはいえ、手の痕跡をほとんどとどめていない原型=その粘土の塊は、どう操作されて得られたのか、私にはまったく見当がつかない。ヘラなどで掻き取った痕跡が、ある種の“決め”の意思を示しているのだろうとは想像できるが、果たしてそれで“決まった”のかどうかさえ、よく分からない。土練機から取り出したばかりのような柔らかめの粘土を、板状に拡げて、それを巻き取りながら、さらに曲げたり、捻ったりしていったものだろうか。あるいは、ゴムのような伸び縮みする素材の布状のものに柔らかめの粘土を包み込んで操作しているのだろうか。
岡崎氏が最も原初的な材料といえる粘土を彫刻制作のために選んだことには、大きな意味がある。心棒のない塑像。
THE MAID OF BUDA AND THE CARVEN WOOD /伐木之樵切水之魚」
2025年、樹脂、UV耐性コーティング、180.0×233.0×396.0cm。
この彫刻作品が今回最も大きな彫刻作品で、床に直に置かれていた。
乱暴な言い方をすれば、大きかろうが、小さかろうが、岡﨑氏の彫刻作品にあまり違いはないように私には思われる。
すでに、陶土を使った岡﨑氏の彫刻を知っている観客には、粘土のかたまりどうしを大胆に接合していくその作り方は、接合面というか、塊と塊との界面をこそ問題にしていることは明らかだからである。
界面という手がかりで考えてみれば、それはすでに「こづくえ」に始まっていたことは明らかであり、この場合、界面は、ナイフを入れて切り分け、その一方を折り曲げることであらわになった切断面がそれだった。界面があらわになった姿こそが「こづくえ」や「あかさかみつけ」シリーズ以来、岡﨑氏のレリーフ=彫刻の面白さだったのである。
また、かつて展開した二枚組の「絵画作品」。これらは、トレースとマスキングとによって成立していた。トレースした形状でマスキングして塗られた絵具の外郭=キワに出来上がる“厚み”もまた界面なのであった。
これらは、1990年代初頭、代官山のヒルサイドギャラリーで発表された平面を組み合わせた大きな立体や、新木場にあった南天子ギャラリーSOKOで発表された3種類9個による立体が問題にした界面のことが変容したものである(この時、立体作品と共に「絵画」作品も同時に発表されていたことを思い起こすとよい)。それは、やがて、石膏やブロンズや金網による彫刻作品に至り、種明かしのようなセラミックでの彫刻に至って、今回の展覧会での3Dプリンタを動員した巨大な出品作の数々に繋がってくる。こうした岡﨑氏の作品の流れを思い起こすと、そこには「界面」という問題意識が貫かれていることが見えてくる。
とはいえ、手の痕跡をほとんどとどめていない原型=その粘土の塊は、どう操作されて得られたのか、私にはまったく見当がつかない。ヘラなどで掻き取った痕跡が、ある種の“決め”の意思を示しているのだろうとは想像できるが、果たしてそれで“決まった”のかどうかさえ、よく分からない。土練機から取り出したばかりのような柔らかめの粘土を、板状に拡げて、それを巻き取りながら、さらに曲げたり、捻ったりしていったものだろうか。あるいは、ゴムのような伸び縮みする素材の布状のものに柔らかめの粘土を包み込んで操作しているのだろうか。
岡崎氏が最も原初的な材料といえる粘土を彫刻制作のために選んだことには、大きな意味がある。心棒のない塑像。
「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(5)
2025-07-17
そしてまた、2019年作2点組の作品。先に見た「パネル絵画」とどう変化しているか。
右側の作品のタイトル。
「小さな鳥は北のほうから海上をかなり低く飛んできた。舟のへさきに止まった彼女はずいぶん疲れている。「旅は始めてかい?」言葉が伝わるよりも速く鳥は飛ぶ。言葉が消えぬ間に波は静まり太陽も戻ってきた。私はもう夢を見ることはない。けれど瞼の上に鳥が飛んでくる。青空にみるみる白い雲が棚引き、朗々たる声がはらはら雪のようにふってきた。「あの歌は誰が歌っているの」。砂浜にライオンがいる。「きみは幾つ?」ライオンは微笑む。ごらんなさい、ごらんなさい、わたしは幸せです。いつも挨拶を交わしていたけど、話をしたのははじめてなのです。」カンヴァス、アクリル、210.0×260.0×6.7cm(パネルは二種類、左側に210.0×78.0×6.7cm、その右側に210.0×52.0×6.7cm、その右側に78.0cm幅のパネル、その右側に52.0cm幅のパネル)
左側の作品のタイトル。
「静かな場所だった。聴こえているのは存在しない音楽。賑やかなのは私の耳のせい。波止場のざわめきは遠く、しとやかに聴こえる。まごまごしてここに迷い込んだ。眩しい光。こまごました磯の香り、イナサの風。あの島に行くつもり?舟の名は?アイオロス、一緒についていくさ。」カンヴァス、アクリル、210.0×130.0×6.7cm(パネルは二種類、左側に210.0×52.0×6.7cm、右側に210.0×78.0×6.7cm)
いずれの作品にも画面の上方と下方に布地の白さが横方向に拡がっていると同時に、パネルの連結部の縦線を越えて色の形が繋がる領域がなくなったわけではないが、この作品ではパネルの縦線で画面が断ち切られている印象が強く生じさせらている(パネルの縦の継ぎ目が目立っている)。が、そうしたパネルの縦線を横切って画面左上から右下へとわずかな傾斜を呈する動勢を感じさせている。色彩も、彩度の高い原色ではなくいわゆる中間色を用いている。塗りも比較的薄い印象だ。筆触(ヘラ触)はごく短い。これらが全体からの印象である。
右側の大きい作品から見ていこう。
右側の作品のタイトル。
「小さな鳥は北のほうから海上をかなり低く飛んできた。舟のへさきに止まった彼女はずいぶん疲れている。「旅は始めてかい?」言葉が伝わるよりも速く鳥は飛ぶ。言葉が消えぬ間に波は静まり太陽も戻ってきた。私はもう夢を見ることはない。けれど瞼の上に鳥が飛んでくる。青空にみるみる白い雲が棚引き、朗々たる声がはらはら雪のようにふってきた。「あの歌は誰が歌っているの」。砂浜にライオンがいる。「きみは幾つ?」ライオンは微笑む。ごらんなさい、ごらんなさい、わたしは幸せです。いつも挨拶を交わしていたけど、話をしたのははじめてなのです。」カンヴァス、アクリル、210.0×260.0×6.7cm(パネルは二種類、左側に210.0×78.0×6.7cm、その右側に210.0×52.0×6.7cm、その右側に78.0cm幅のパネル、その右側に52.0cm幅のパネル)
左側の作品のタイトル。
「静かな場所だった。聴こえているのは存在しない音楽。賑やかなのは私の耳のせい。波止場のざわめきは遠く、しとやかに聴こえる。まごまごしてここに迷い込んだ。眩しい光。こまごました磯の香り、イナサの風。あの島に行くつもり?舟の名は?アイオロス、一緒についていくさ。」カンヴァス、アクリル、210.0×130.0×6.7cm(パネルは二種類、左側に210.0×52.0×6.7cm、右側に210.0×78.0×6.7cm)
いずれの作品にも画面の上方と下方に布地の白さが横方向に拡がっていると同時に、パネルの連結部の縦線を越えて色の形が繋がる領域がなくなったわけではないが、この作品ではパネルの縦線で画面が断ち切られている印象が強く生じさせらている(パネルの縦の継ぎ目が目立っている)。が、そうしたパネルの縦線を横切って画面左上から右下へとわずかな傾斜を呈する動勢を感じさせている。色彩も、彩度の高い原色ではなくいわゆる中間色を用いている。塗りも比較的薄い印象だ。筆触(ヘラ触)はごく短い。これらが全体からの印象である。
右側の大きい作品から見ていこう。
「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(4)
2025-07-17
岡﨑氏が複数のパネルを連結させた絵画=「パネル絵画」を制作するようになったのは「2015年頃から」(『視覚のカイソウ』展の図録の記述による)というのだが、そのいささか暴力的な印象さえ感じさせる岡﨑氏の一連の作品群を、私はどう見ていいか分からず、判断を保留したままここまできた。その「パネル絵画」について、岡﨑氏は会場に掲げられたコメント文で次のように言っている。
・「パネル絵画」を本格的に展開し始めたのは2022年以降。
・それまでは、「縦長のパネルを水平に並べる程度の扱いに」留まっていた。
・この形式を使うのは、「大きな画面を作るために画面を分割する必要性」があったからでもある。
・それだけではなく、「画面にあらかじめ物理的比例関係を組み込んでおく」という理由がある。
・制作過程では、「パネル同士の隣接関係は可変的で何度となく入れ替えられる」。
分かりにくいので、私なりの解釈を加えて少し補足したい。
「大きな画面を作るために画面を分割する」というのは、「大きな画面」を分割して得ることができた小さなパネル同士を組み合わせて最終的にもう一度「大きな画面」を作り上げる、という意味だろう。
「画面にあらかじめ物理的比例関係を組み込んでおく」というのは、パネル同士の組み合わせ方の可能性をあらかじめ想定している、ということだろう。とはいえ、一度に全ての可能性を探るわけにはいかないから、「縦長のパネルを水平に並べる程度の扱い」から始めたのだろう。
制作過程において「パネル同士の隣接関係は可変的」、ということは、制作している時にはパネルを入れ替えたり、上下逆さまにもしたりしているが、岡﨑氏が完成したと判断した時以降には、パネル同士の結合は固定してもう入れ替えをしないし、させない、ということだろう。
そんなことを念頭に置いて、たとえば「パネル絵画」と取り組み始めて間もない2016年の作品を見てみる。3階フロアの「パネル絵画」群と比べる意味においてもこれは大事なことだ。「パネル絵画」をはじめて見た時、どう見ていいかまったく分からなかった、ということもある。そのリベンジを試みたい。長いタイトルを書き(打ち)写す。
2点組の作品である。
右側の作品
「あなたはこの水を乾かし、あるいは飲み干すだろう。けれど決して水は滅びない。水は姿を変え移動しただけである。水は乾くことなく、水がのどの渇きを癒すのだ。と似て、私の指一本いや手足を切り落とそうと、わたしは切り落とせない。姿を変える勝手気ままが水ではなく、わたし(の赤い水、血)ではない。水の中に水の姿に関わらぬ何か、として水の霊が宿っている(水が弾きだすと波と早合点しないように。波は音楽のようにあちこち拡がり増えたり減ったりするが、水の霊は増減せず分割もされない)。わたしは水の中にあり、泳ぎ、まどろみ、そして目覚める」
カンヴァスにアクリル絵の具、210.0×260.0×7.0cm。(この大きな作品=通常のカンヴァスのサイズでいうと400号弱の大きさになるが、ここで使われている縦長のパネルは4枚。寸法は二種類、210.0×108.0×7.0cm、210.0×72.0×7.0cm。それぞれ各2枚である。横幅の寸法が3対2の比率になっており、完成時には、両側に幅広のパネル、中央に幅の狭い方の2枚のパネルが結合されている。また、幅広のパネルの縦横の比率はほぼ2対1、幅が狭い方のパネルの比率はほぼ3対1である。)
左側の作品。
「宙空の箒/アウフヘーベン」
カンヴァスにアクリル絵具、25.0×18.0cm(会場で配布されていた「作品リスト」には厚みの寸法の記述がない)。「ゼロ・サムネイル」シリーズとほぼ同一の寸法と形式の作品だろう。「ゼロ・サムネイル」のシリーズには奇妙な“額縁”がついているが、この作品も例外ではない。
右側の作品と左側の作品との2枚組の作品は、今回の会場では仮設壁同士が成したコーナーを挟んで展示されているので、2点組というより、ひとつずつ独立した作品としても見える。2016年の制作というから、先の岡﨑氏のコメント文に従えば、「縦長のパネルを水平に並べる程度」の段階で、「パネル絵画」の可能性をまだ本格的には展開していない時期の初期作品である(2022年以降の作品は3階フロアにまとめて展示されている)。
・「パネル絵画」を本格的に展開し始めたのは2022年以降。
・それまでは、「縦長のパネルを水平に並べる程度の扱いに」留まっていた。
・この形式を使うのは、「大きな画面を作るために画面を分割する必要性」があったからでもある。
・それだけではなく、「画面にあらかじめ物理的比例関係を組み込んでおく」という理由がある。
・制作過程では、「パネル同士の隣接関係は可変的で何度となく入れ替えられる」。
分かりにくいので、私なりの解釈を加えて少し補足したい。
「大きな画面を作るために画面を分割する」というのは、「大きな画面」を分割して得ることができた小さなパネル同士を組み合わせて最終的にもう一度「大きな画面」を作り上げる、という意味だろう。
「画面にあらかじめ物理的比例関係を組み込んでおく」というのは、パネル同士の組み合わせ方の可能性をあらかじめ想定している、ということだろう。とはいえ、一度に全ての可能性を探るわけにはいかないから、「縦長のパネルを水平に並べる程度の扱い」から始めたのだろう。
制作過程において「パネル同士の隣接関係は可変的」、ということは、制作している時にはパネルを入れ替えたり、上下逆さまにもしたりしているが、岡﨑氏が完成したと判断した時以降には、パネル同士の結合は固定してもう入れ替えをしないし、させない、ということだろう。
そんなことを念頭に置いて、たとえば「パネル絵画」と取り組み始めて間もない2016年の作品を見てみる。3階フロアの「パネル絵画」群と比べる意味においてもこれは大事なことだ。「パネル絵画」をはじめて見た時、どう見ていいかまったく分からなかった、ということもある。そのリベンジを試みたい。長いタイトルを書き(打ち)写す。
2点組の作品である。
右側の作品
「あなたはこの水を乾かし、あるいは飲み干すだろう。けれど決して水は滅びない。水は姿を変え移動しただけである。水は乾くことなく、水がのどの渇きを癒すのだ。と似て、私の指一本いや手足を切り落とそうと、わたしは切り落とせない。姿を変える勝手気ままが水ではなく、わたし(の赤い水、血)ではない。水の中に水の姿に関わらぬ何か、として水の霊が宿っている(水が弾きだすと波と早合点しないように。波は音楽のようにあちこち拡がり増えたり減ったりするが、水の霊は増減せず分割もされない)。わたしは水の中にあり、泳ぎ、まどろみ、そして目覚める」
カンヴァスにアクリル絵の具、210.0×260.0×7.0cm。(この大きな作品=通常のカンヴァスのサイズでいうと400号弱の大きさになるが、ここで使われている縦長のパネルは4枚。寸法は二種類、210.0×108.0×7.0cm、210.0×72.0×7.0cm。それぞれ各2枚である。横幅の寸法が3対2の比率になっており、完成時には、両側に幅広のパネル、中央に幅の狭い方の2枚のパネルが結合されている。また、幅広のパネルの縦横の比率はほぼ2対1、幅が狭い方のパネルの比率はほぼ3対1である。)
左側の作品。
「宙空の箒/アウフヘーベン」
カンヴァスにアクリル絵具、25.0×18.0cm(会場で配布されていた「作品リスト」には厚みの寸法の記述がない)。「ゼロ・サムネイル」シリーズとほぼ同一の寸法と形式の作品だろう。「ゼロ・サムネイル」のシリーズには奇妙な“額縁”がついているが、この作品も例外ではない。
右側の作品と左側の作品との2枚組の作品は、今回の会場では仮設壁同士が成したコーナーを挟んで展示されているので、2点組というより、ひとつずつ独立した作品としても見える。2016年の制作というから、先の岡﨑氏のコメント文に従えば、「縦長のパネルを水平に並べる程度」の段階で、「パネル絵画」の可能性をまだ本格的には展開していない時期の初期作品である(2022年以降の作品は3階フロアにまとめて展示されている)。
「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(3)
2025-07-17
「あかさかみつけ」 1981年作
岡﨑氏のいわば代名詞とも言える通称「あかさかみつけシリーズ」は、1981年3月村松画廊での「たてもののきもち」というタイトルの氏の初個展で発表された。その時の「あかさかみつけ」が、今回は「こづくえ」と同じ部屋の壁に展示されている。
不覚にも私は氏の初個展を見ていない。すでに述べたように、私が岡﨑氏の作品を初めて見たのは1981年11月の「第2回 ハラ・アニュアル」でだった。先輩画家の桜井英嘉氏が、今やってる「ハラ・アニュアル」に出してるから見ておいてよ、と言うので、品川の原美術館へ見に行った。その時に、廊下の壁に展示されていた名前も知らなかった岡﨑氏のいくつかの作品を見たのである。現在言われる「あかさかみつけ」シリーズだった。どの作品だったか、何点あったか、などはもう記憶していない。記憶はないが、とても面白い、と思って、氏の名前を覚えた記憶はある。その時、私はただちにタトリンを思い浮かべていたが、磯崎新氏は「『カタジナ・コブロだね』とニヤリと」言ったそうである(『群像』2025年4月号、田中純氏による岡﨑氏へのインタビュー「シン・イソザキがヨミがえる」での岡﨑氏の発言)。私は1987年にポーランドのウッジを訪れるまでカタジナ・コブロをまったく知らなかったが、岡崎氏は1981年にはすでにもう知っていて磯崎氏と話がはずんだというのだから驚きだ。
今回は、1981年の「たてもののきもち」での発表作のうち、「そとかんだ」「あかさかみつけ」「うぐいすだに」「かっぱばし」の4点が展示されている。「かっぱばし」は個人蔵、それ以外は高松市美術館の所蔵。「うぐいすだに」以外は、先に指摘した“先すぼまり”になっているのが興味深い。この当時の岡﨑氏は空間を包み込みたい、と思っていたということだろうか。その“包み込み”たかったらしき空間と、その外側の空間とが行き来すること。
1981年の「あかさかみつけ」などを見るのは三度目だったが、ジオットの壁画を参考にして着彩したというその色どうしの響きが、鈍く、重苦しく感じさせられて、あまりジオットらしくなく、想定外の印象を受けた。ポリスチレンのボードは建築模型によく使われるようだが、その切断面には空隙がない。そうしたところからの影響があるかもしれない。岡﨑氏は、その切断面にも着彩していて、面への着彩との関係を探っており、複雑な「見え」を実現しようとしている。
観客の視点が変化するたびに(もっと言えば、同一の視点でもそこから視線を動かすたびに)、岡﨑氏のレリーフは次々と表情を変えていく。というか、表情が変化していることに私たちが気付くことをレリーフが促してくる。柔らかな一分節の曲線と直線、面の形状と色の広がり、隙間のかたち、目の位置が動いて隙間が消えた時に手前と奥の面とが一体化する時のヴォリウム感、ネガポジの形状の反復・反転・交錯が生み出す豊かなリズム、、、。これらが豊かで心地よく、見飽きることがない。まさに「こづくえ」からの展開だといえよう。
岡﨑氏のいわば代名詞とも言える通称「あかさかみつけシリーズ」は、1981年3月村松画廊での「たてもののきもち」というタイトルの氏の初個展で発表された。その時の「あかさかみつけ」が、今回は「こづくえ」と同じ部屋の壁に展示されている。
不覚にも私は氏の初個展を見ていない。すでに述べたように、私が岡﨑氏の作品を初めて見たのは1981年11月の「第2回 ハラ・アニュアル」でだった。先輩画家の桜井英嘉氏が、今やってる「ハラ・アニュアル」に出してるから見ておいてよ、と言うので、品川の原美術館へ見に行った。その時に、廊下の壁に展示されていた名前も知らなかった岡﨑氏のいくつかの作品を見たのである。現在言われる「あかさかみつけ」シリーズだった。どの作品だったか、何点あったか、などはもう記憶していない。記憶はないが、とても面白い、と思って、氏の名前を覚えた記憶はある。その時、私はただちにタトリンを思い浮かべていたが、磯崎新氏は「『カタジナ・コブロだね』とニヤリと」言ったそうである(『群像』2025年4月号、田中純氏による岡﨑氏へのインタビュー「シン・イソザキがヨミがえる」での岡﨑氏の発言)。私は1987年にポーランドのウッジを訪れるまでカタジナ・コブロをまったく知らなかったが、岡崎氏は1981年にはすでにもう知っていて磯崎氏と話がはずんだというのだから驚きだ。
今回は、1981年の「たてもののきもち」での発表作のうち、「そとかんだ」「あかさかみつけ」「うぐいすだに」「かっぱばし」の4点が展示されている。「かっぱばし」は個人蔵、それ以外は高松市美術館の所蔵。「うぐいすだに」以外は、先に指摘した“先すぼまり”になっているのが興味深い。この当時の岡﨑氏は空間を包み込みたい、と思っていたということだろうか。その“包み込み”たかったらしき空間と、その外側の空間とが行き来すること。
1981年の「あかさかみつけ」などを見るのは三度目だったが、ジオットの壁画を参考にして着彩したというその色どうしの響きが、鈍く、重苦しく感じさせられて、あまりジオットらしくなく、想定外の印象を受けた。ポリスチレンのボードは建築模型によく使われるようだが、その切断面には空隙がない。そうしたところからの影響があるかもしれない。岡﨑氏は、その切断面にも着彩していて、面への着彩との関係を探っており、複雑な「見え」を実現しようとしている。
観客の視点が変化するたびに(もっと言えば、同一の視点でもそこから視線を動かすたびに)、岡﨑氏のレリーフは次々と表情を変えていく。というか、表情が変化していることに私たちが気付くことをレリーフが促してくる。柔らかな一分節の曲線と直線、面の形状と色の広がり、隙間のかたち、目の位置が動いて隙間が消えた時に手前と奥の面とが一体化する時のヴォリウム感、ネガポジの形状の反復・反転・交錯が生み出す豊かなリズム、、、。これらが豊かで心地よく、見飽きることがない。まさに「こづくえ」からの展開だといえよう。
「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(2)
2025-07-17
「こづくえ」1979年作、色紙、ボール紙、12.5×10.8×10.0(cm)。
1981年3月の初個展で「あかさかみつけ」シリーズを発表する以前、岡﨑氏はどんな作品を作っていたか、その一端を、1979年作というこの「こづくえ」の展示で明らかにしている。よくこれを手元に保管してあったものだ。同時に、今回、これをよく展示・公開してくれた。今回の“目玉”のひとつだろう。
「こづくえ」は、この展覧会の冒頭に展示されており、1階入り口からこのあたりだけ、“モギリ”のお姉さんと監視員が観客の順路を誘導していた。ここから見はじめてください、というわけで、岡﨑氏と美術館との強い意志を感じさせていた。であるから、おとなしく監視員の指示に従えば、入場直後にこの「こづくえ」と出会えることになったのだが、観客の動線から言えば、進行方向の右側に立てられた仮設壁の裏側の壁面に「こづくえ」が掛けられているので、私(たち)は、その気配を感じて振り向きざまに出会うという“演出”のゆえかまんまと、おお、これが出たか! と思わず叫びたくなるくらいにされるのであった。が、同時に、床置きの什器が気になって(ここにも習作的な貴重な作品群が置かれているが)、他の観客もいるし、「こづくえ」がいくら小さな作品だといっても、仮設壁の幅も十分にあるわけではないから、仮設壁の奥の方へと回り込んだりして「こづくえ」を観察することがやりにくいのだった(気にせず何度も回り込んじゃったけど)。
先に述べた『ART TODAY 2002 Kenjiro OKAZAKI 岡崎乾二郎展』図録(セゾン現代美術館、2002年)などに掲載された小さな白黒の写真図版で、この作品のことは知っていたが、こうして実物とまみえると、実物の情報量は実に豊かであった。色、形状、大きさ、ボール紙の材質感、切り口、折り曲げたところに加えられた力の入り具合、繋ぎ合わせ部を補強する紙やホッチキス、色紙の薄さ、セロテープや糊の跡らしきいくつかのシミ、、、など、たえまなく目に飛び込んでくる。
1981年3月の初個展で「あかさかみつけ」シリーズを発表する以前、岡﨑氏はどんな作品を作っていたか、その一端を、1979年作というこの「こづくえ」の展示で明らかにしている。よくこれを手元に保管してあったものだ。同時に、今回、これをよく展示・公開してくれた。今回の“目玉”のひとつだろう。
「こづくえ」は、この展覧会の冒頭に展示されており、1階入り口からこのあたりだけ、“モギリ”のお姉さんと監視員が観客の順路を誘導していた。ここから見はじめてください、というわけで、岡﨑氏と美術館との強い意志を感じさせていた。であるから、おとなしく監視員の指示に従えば、入場直後にこの「こづくえ」と出会えることになったのだが、観客の動線から言えば、進行方向の右側に立てられた仮設壁の裏側の壁面に「こづくえ」が掛けられているので、私(たち)は、その気配を感じて振り向きざまに出会うという“演出”のゆえかまんまと、おお、これが出たか! と思わず叫びたくなるくらいにされるのであった。が、同時に、床置きの什器が気になって(ここにも習作的な貴重な作品群が置かれているが)、他の観客もいるし、「こづくえ」がいくら小さな作品だといっても、仮設壁の幅も十分にあるわけではないから、仮設壁の奥の方へと回り込んだりして「こづくえ」を観察することがやりにくいのだった(気にせず何度も回り込んじゃったけど)。
先に述べた『ART TODAY 2002 Kenjiro OKAZAKI 岡崎乾二郎展』図録(セゾン現代美術館、2002年)などに掲載された小さな白黒の写真図版で、この作品のことは知っていたが、こうして実物とまみえると、実物の情報量は実に豊かであった。色、形状、大きさ、ボール紙の材質感、切り口、折り曲げたところに加えられた力の入り具合、繋ぎ合わせ部を補強する紙やホッチキス、色紙の薄さ、セロテープや糊の跡らしきいくつかのシミ、、、など、たえまなく目に飛び込んでくる。
「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(1)
2025-07-17
この文を書き(打ち込み)始めて、私は、氏の氏名の表記が、「岡崎乾二郎」ではなく、「岡﨑乾二郎」だ、ということに気がついた。「岡崎」だと思い込んで、「岡崎」と表記してきた。
じつに失礼なふるまいであった。岡﨑氏にお詫びしたい。
申し訳ありません! 今後気をつけることはもちろんのこと、この『雑記帳』で生じさせてしまっていた表記の誤りはすべて私に責任があります。「雑記帳」の管理運営者にお願いして、訂正を実現してもらうようにしていきます。
そんなわけで、しばらく落ち込んでいた。
が、念のため、手元にあったいくつかの資料を確認してみた。
たとえば、私には極めて衝撃的だったあの『批評空間1995〈臨時増刊号〉モダニズムのハード・コア』(1995年3月、太田出版)。この書物の表紙カバーには3箇所に「岡崎乾二郎」とある。その12年後=2007年、この年の5月発行の『芸術の設計 見る/作ることのアプリケーション』(フィルムアート社)。この本も、監修・著者として「岡崎乾二郎」と表記している。
じつに失礼なふるまいであった。岡﨑氏にお詫びしたい。
申し訳ありません! 今後気をつけることはもちろんのこと、この『雑記帳』で生じさせてしまっていた表記の誤りはすべて私に責任があります。「雑記帳」の管理運営者にお願いして、訂正を実現してもらうようにしていきます。
そんなわけで、しばらく落ち込んでいた。
が、念のため、手元にあったいくつかの資料を確認してみた。
たとえば、私には極めて衝撃的だったあの『批評空間1995〈臨時増刊号〉モダニズムのハード・コア』(1995年3月、太田出版)。この書物の表紙カバーには3箇所に「岡崎乾二郎」とある。その12年後=2007年、この年の5月発行の『芸術の設計 見る/作ることのアプリケーション』(フィルムアート社)。この本も、監修・著者として「岡崎乾二郎」と表記している。




















