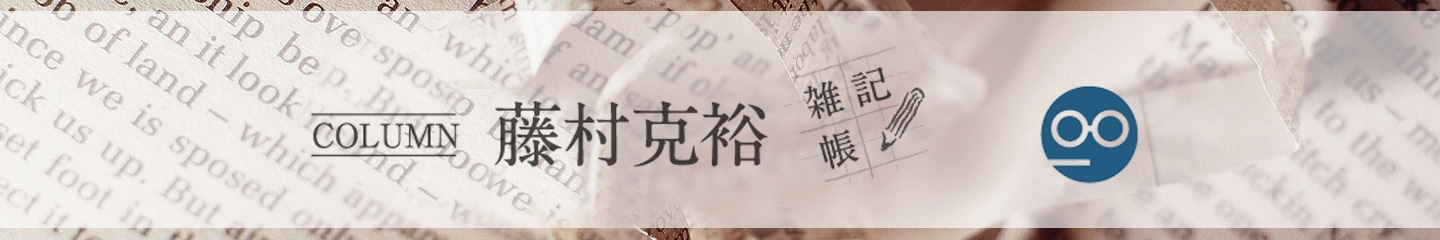

立体作家、元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員の藤村克裕先生のアートについてのコラムです。
藤村克裕 プロフィール
1977年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。
1979年 東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修了。
元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員。
迎賓館に行ってみた その2
2018-08-21
そして建物内を巡っていくと、いろんな部屋がある。玄関ホールと二階へ伸びる階段が観察できるところではしばし佇んだ。階段の上は吹き抜けになっているので、二階の天井までの高さが結構凄い。賓客は玄関から入って、この階段を登って、二階で待つ天皇皇后や政府首脳の出迎えを受けるのであろうか、などと想像してみるが、途中でやめた。
やがて、二階。大きな部屋を見物して、さっきの階段を登り切ったホールに出ると、小磯良平の大きな絵が二点あった。向かって左に『絵』、右に『音楽』。どうやら、小磯が勤務していた東京芸大を描いているらしい。『絵』に描かれている背景の窓は、絵画棟のアトリエの窓の形状である。ということは、描かれている複数の画学生らしきは、芸大油画科の学生であろうか。しかし、どれもスタイルが良すぎて現実感がない。当然のように造形上の破綻など一切ない絵である。これも、ふーん、と見た。
天井画は建物全体の修復時に寺田春弌画伯が描いた、との音声が繰り返し流れていた。この画伯も芸大の先生だった人。油画の材料と技法とを専門にしていた人で、著書『油彩画の科学』は書棚のどこかにいまもあったはず。この天井画を描いたのは、ちょうど私たちが学生の頃のことのようであった。当時、彼の授業も受けたけど、この天井画のことは全然知らなかったし、授業の中でも何も言っていなかった気がする。でも、当時の技法材料研究室の関係者は当然のように駆り出されて手伝ってたんだろうなあ、と妙なことを考えていた。
大きな部屋の一つに仮設の大きな黒い壁が作られて、そこに藤田の絵が三点、並んでかけられていた。どれも、特別な感興が起きるような絵ではなかったが、興味深かったのはその仮設の壁。
鏡のある壁面の前に大きく作られていた。その側面には黒い布がかかって観客の視線を塞いでいる。しかし、鏡との間にわずかな隙間があって、仮設壁の裏側の構造が鏡に映って見えている。どこにでもあるパネル仕立ての構造物である。上部は、観客からはどうせ見えないからか、作られていないのがわかる。だから光が入ってきて、余計に鏡の中にパネルの裏側がはっきりと見えている。おそらくは現場で組み立ててから、裏側がすっかり鏡に映ってしまうことに気づいたのだろう。で、布をかけた。壁やレリーフ、鏡に傷をつけては大変だし、時間がない。予算もない。わずかな隙間はできるけど、ま、これで勘弁してもらいましょうか、布にはアイロンも当てたし、ということではないか。
しかし、見えてしまうものは見えてしまうのである。木材とベニヤ板で作られた仮設壁は、その仮設性とニセモノ性とをわずかな隙間から、わずかであるからこそいっそう露わにしてしまっていたのである。隙間ができても、上部が塞いであったり、パネルを太鼓張にして裏側も黒くしてあったりすれば、見え方は違ったろうし、違う感じ方も生じたかもしれない。しかし、こうして、建物の中に入ってすぐ感じた“キッチュ”な印象が、鏡との間のわずかな隙間から見えてしまった光景によって、さらに決定的なものになったのだった。この仮設壁がない場合でも、外国からの賓客は、もっと“キッチュ”さを感じるのではないだろうか。こうして、日本の近代、というものの姿の一端を見せつけられた気がしたものである。「ゴージャスな気分」どころではなくなった。
この建物内には現首相・安倍晋三氏が写り込んだ写真がたくさん飾られていて、その教育力=宣伝力の凄まじさを感じさせてくれたが、こうしたせっかくの公開の機会であれば、現首相の“活躍ぶり”ばかりでなく、日本の近・現代史でこの建物がどういう経緯で作られ、どう使われてきたか、そして今どう使われているか、などを示す資料類をしっかり展示するなどの「本来の教育」をしっかりとやって欲しい、と思ったものである。
売店を訪れて、藤田の絵葉書とかはないの? と尋ねると‥‥、
あれは、「コロンバン」というお菓子屋さんのために藤田が描いた絵で、「コロンバン」が絵を寄贈したわけ、それをどこかにしまってあったんじゃないの? それを今回公開しただけで、迎賓館とはもともと関係ないのよ。だから、絵葉書なんかないのよ。よく訊かれるんだけどね。
え、迎賓館の壁とか天井に飾る絵だったんじゃないの?
違うわよ、お菓子屋さんに飾るために描いた絵。だから、っていうわけじゃないけど、ほら、なんだかねえ‥‥。
なるほど、そうだったんですね。知らなかった。どうも、ありがとうございました。
どういたしまして。
不勉強を恥じながら、国宝を後にする私と家人であった。
2018年8月14日、東京にて
やがて、二階。大きな部屋を見物して、さっきの階段を登り切ったホールに出ると、小磯良平の大きな絵が二点あった。向かって左に『絵』、右に『音楽』。どうやら、小磯が勤務していた東京芸大を描いているらしい。『絵』に描かれている背景の窓は、絵画棟のアトリエの窓の形状である。ということは、描かれている複数の画学生らしきは、芸大油画科の学生であろうか。しかし、どれもスタイルが良すぎて現実感がない。当然のように造形上の破綻など一切ない絵である。これも、ふーん、と見た。
天井画は建物全体の修復時に寺田春弌画伯が描いた、との音声が繰り返し流れていた。この画伯も芸大の先生だった人。油画の材料と技法とを専門にしていた人で、著書『油彩画の科学』は書棚のどこかにいまもあったはず。この天井画を描いたのは、ちょうど私たちが学生の頃のことのようであった。当時、彼の授業も受けたけど、この天井画のことは全然知らなかったし、授業の中でも何も言っていなかった気がする。でも、当時の技法材料研究室の関係者は当然のように駆り出されて手伝ってたんだろうなあ、と妙なことを考えていた。
大きな部屋の一つに仮設の大きな黒い壁が作られて、そこに藤田の絵が三点、並んでかけられていた。どれも、特別な感興が起きるような絵ではなかったが、興味深かったのはその仮設の壁。
鏡のある壁面の前に大きく作られていた。その側面には黒い布がかかって観客の視線を塞いでいる。しかし、鏡との間にわずかな隙間があって、仮設壁の裏側の構造が鏡に映って見えている。どこにでもあるパネル仕立ての構造物である。上部は、観客からはどうせ見えないからか、作られていないのがわかる。だから光が入ってきて、余計に鏡の中にパネルの裏側がはっきりと見えている。おそらくは現場で組み立ててから、裏側がすっかり鏡に映ってしまうことに気づいたのだろう。で、布をかけた。壁やレリーフ、鏡に傷をつけては大変だし、時間がない。予算もない。わずかな隙間はできるけど、ま、これで勘弁してもらいましょうか、布にはアイロンも当てたし、ということではないか。
しかし、見えてしまうものは見えてしまうのである。木材とベニヤ板で作られた仮設壁は、その仮設性とニセモノ性とをわずかな隙間から、わずかであるからこそいっそう露わにしてしまっていたのである。隙間ができても、上部が塞いであったり、パネルを太鼓張にして裏側も黒くしてあったりすれば、見え方は違ったろうし、違う感じ方も生じたかもしれない。しかし、こうして、建物の中に入ってすぐ感じた“キッチュ”な印象が、鏡との間のわずかな隙間から見えてしまった光景によって、さらに決定的なものになったのだった。この仮設壁がない場合でも、外国からの賓客は、もっと“キッチュ”さを感じるのではないだろうか。こうして、日本の近代、というものの姿の一端を見せつけられた気がしたものである。「ゴージャスな気分」どころではなくなった。
この建物内には現首相・安倍晋三氏が写り込んだ写真がたくさん飾られていて、その教育力=宣伝力の凄まじさを感じさせてくれたが、こうしたせっかくの公開の機会であれば、現首相の“活躍ぶり”ばかりでなく、日本の近・現代史でこの建物がどういう経緯で作られ、どう使われてきたか、そして今どう使われているか、などを示す資料類をしっかり展示するなどの「本来の教育」をしっかりとやって欲しい、と思ったものである。
売店を訪れて、藤田の絵葉書とかはないの? と尋ねると‥‥、
あれは、「コロンバン」というお菓子屋さんのために藤田が描いた絵で、「コロンバン」が絵を寄贈したわけ、それをどこかにしまってあったんじゃないの? それを今回公開しただけで、迎賓館とはもともと関係ないのよ。だから、絵葉書なんかないのよ。よく訊かれるんだけどね。
え、迎賓館の壁とか天井に飾る絵だったんじゃないの?
違うわよ、お菓子屋さんに飾るために描いた絵。だから、っていうわけじゃないけど、ほら、なんだかねえ‥‥。
なるほど、そうだったんですね。知らなかった。どうも、ありがとうございました。
どういたしまして。
不勉強を恥じながら、国宝を後にする私と家人であった。
2018年8月14日、東京にて
迎賓館に行ってみた その1
2018-08-21
毎日暑すぎるわけだが、そんな中、夏休み中の長男夫婦の提案で、私たち夫婦と四人、“昼食会”をした。とっても豪華でおいしかった。しかも、あろうことか、ゴチになってしまった。ありがたいことである。しばし、暑さを忘れることができた。
このあと、どうするのか? と家人が長男夫婦に尋ねると、水族館に行く、と言う。いかにも涼しげで、グッドアイディア、と思ったが、くっついて行ったりはしないのである(あたりまえか)。じゃあね、ごちそうさま、と別れて、私と家人は四谷・迎賓館に向かった。ちょうど、迎賓館では、藤田嗣治の絵が公開されているはず。ついゴージャスな気分になっていたのだった。
正面の門から入って、そのまま正面の玄関から建物の中に入っていくような気がしていたが、正面に向かおうとしているのをみてとったらしき路上の人から、あっち(学習院初等科の向かい側)の方に行くように誘導された。炎天下の路上で頑張っているのはすごい、と驚いていると、件の人だけでなく、次々に別の係員たちが誘導してくれるので、やがて、「西門」と呼ばれているらしい門から敷地内に入って、列に並び、荷物検査、チケット購入、チケット確認、入場、と滞りようのない流れに乗ることになったのである。
建物に入ったのは正面向かって右側の端っこのところ。そこから中をぐるぐる巡っていく。館内には冷房が効いているので、外の暑さからは逃れることができた。しかし、すぐに私と家人は気づかされるのである。
なんだか居心地が悪い。
高い天井、白い塗装、金色の金具、赤カーペット、床面のモザイク、歪みもクモリもない大きな鏡、各種の大理石、窓の形状、レースのカーテン、シャンデリア、壁画、レリーフ、椅子やテーブル、‥‥。なんだか、ひどく丁寧に作られた舞台装置のようである。「本物感」がほとんどない。“キッチュ”とでも言うのか、うーん、場違いなところに来てしまった。
藤田嗣治の絵は、入ってすぐのところに、まず一点展示されていた。描かれている男女ふたりの人物も、その場の景色も、明らかに西洋人であり西洋のどこかのようである。ヘロヘロ、ホイホイ描かれていて、ふーん、という以外の感想が生じない。
つづく→
このあと、どうするのか? と家人が長男夫婦に尋ねると、水族館に行く、と言う。いかにも涼しげで、グッドアイディア、と思ったが、くっついて行ったりはしないのである(あたりまえか)。じゃあね、ごちそうさま、と別れて、私と家人は四谷・迎賓館に向かった。ちょうど、迎賓館では、藤田嗣治の絵が公開されているはず。ついゴージャスな気分になっていたのだった。
正面の門から入って、そのまま正面の玄関から建物の中に入っていくような気がしていたが、正面に向かおうとしているのをみてとったらしき路上の人から、あっち(学習院初等科の向かい側)の方に行くように誘導された。炎天下の路上で頑張っているのはすごい、と驚いていると、件の人だけでなく、次々に別の係員たちが誘導してくれるので、やがて、「西門」と呼ばれているらしい門から敷地内に入って、列に並び、荷物検査、チケット購入、チケット確認、入場、と滞りようのない流れに乗ることになったのである。
建物に入ったのは正面向かって右側の端っこのところ。そこから中をぐるぐる巡っていく。館内には冷房が効いているので、外の暑さからは逃れることができた。しかし、すぐに私と家人は気づかされるのである。
なんだか居心地が悪い。
高い天井、白い塗装、金色の金具、赤カーペット、床面のモザイク、歪みもクモリもない大きな鏡、各種の大理石、窓の形状、レースのカーテン、シャンデリア、壁画、レリーフ、椅子やテーブル、‥‥。なんだか、ひどく丁寧に作られた舞台装置のようである。「本物感」がほとんどない。“キッチュ”とでも言うのか、うーん、場違いなところに来てしまった。
藤田嗣治の絵は、入ってすぐのところに、まず一点展示されていた。描かれている男女ふたりの人物も、その場の景色も、明らかに西洋人であり西洋のどこかのようである。ヘロヘロ、ホイホイ描かれていて、ふーん、という以外の感想が生じない。
つづく→




















