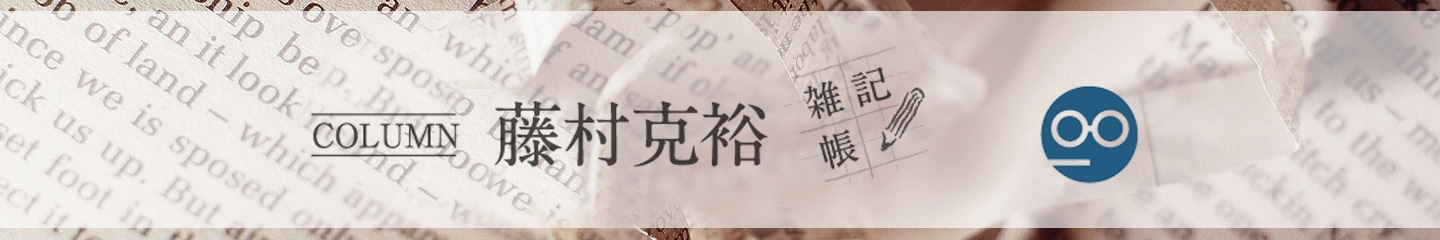

立体作家、元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員の藤村克裕先生のアートについてのコラムです。
藤村克裕 プロフィール
1977年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。
1979年 東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修了。
元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員。
世田谷美術館への行き方を忘れてしまっていた日
2023-06-12
近所にお住まいのOさんから、こんど世田谷美術館で「麻生三郎展」がありますよ、という内容のメモ書きとチラシが入った封書が届いたのは、まだまだ寒かった頃だった。
わざわざ知らせてくださったんだ、ありがたいなあ、楽しみだなあ、と思ったのだったが、その後ボヤボヤしていたらとっくに「麻生三郎展」は始まってしまって、明日は行くぞ、明日こそは行くぞ、と思っているうちに、会期の残りが一週間になってしまった。
で、雨の日曜日の午前中、家人と共に用賀駅に降り立つと、家人はこの先はバスで行く、と言う。美術館行きバスは一時間に一本だけで、しばらく来ないのが分かった。成城学園駅行きが来たので小田急線方向に行くのならこれでもいいはず、と当てずっぽうで乗り込むと、家人は運転手さんに、美術館に行くにはどこで降りるのかしら? とか何とか聞いている。運転手さんは、えと、砧、、、かな? と自信なさげに言っているのが聞こえた。
バスを降りたところは初めての道筋にあるバス停だった。やむを得ず、時々見える清掃工場の煙突を目印に歩き始めた。じきに案内板が見つかってその矢印に従って行く。つまり、どのバスに乗ればいいのかすら忘れてしまっていたのである。とは言え、初めての道筋をしばらく歩いて何とか公園に辿り着けた。緑が美しかった。
麻生三郎の大きな展覧会は東京国立近代美術館以来、十数年ぶりである。
その間にOさんと知り合った。ある日、Oさんがきちんと額装された麻生三郎のペンデッサンを貸してくださった。本物だ。貸してくださったいきさつは忘れてしまった。運河べりの風景が描かれていた。せっかくだから、と模写してみると、現場でいかにも素早く描かれたかのようなその風景のデッサンが、微細な点の一つ一つに至るまで、実に構成的な意志を伴って描かれていることに気がついて驚嘆した。す、すごい!
模写に「ASO」のサインを真似て「ASSO」と書き込んでおどけ、驚きをごまかした。その模写をしまい込み(行方がわからない)、Oさんにオリジナルをお返しした。その時以来、麻生三郎は特別な人になった。
会場に足を踏み入れると、1948年の「子供」という絵から始まる。その年の暮れに三軒茶屋にアトリエを構えたという。1972年に生田に移るまでの間の仕事が今回は紹介されている。世田谷、というところに着眼しての企画。
1948年、49年、50年と、しばらくの間は娘さんや奥さんがモデルになっていて、背景が黒い油絵が続く。キャンバスの表面が波打っていて、さらに照明で光って、よく見えない。見えないが、黒と言っても単純な黒さではない。厚くなってもなお重ねられた塗り込み、黒さの中に多様な色相が混入しているのが発見できる。一見、アクセントのように朱が与えられたりもするが、アクセントだけの役割にとどまることはない。ある種の象徴性を帯びて、麻生三郎の絵の中に繰り返し現れ出てくる。空襲の火の色か? また、画面の上下に帯状の枠のような領域が現れ出ることがある。これが興味深い。
1950年の「裸A」や1951年の「ひとり」では腕や手の表情が実に巧みである。手や足、目の表情が大きな役割を果たすのは麻生三郎の絵の一貫した特徴だろう。
1953年「母子」を見ていると、額縁にごく小さな虫がついていて、しかも少しずつ動いているのに気がついた。虫を見ていると、やがて額縁を越えて画面上方に”降り立ち”、少し動いては止まり、動いては止まる。監視のお姉さんを手招きして、虫のことを“告げ口”した。お姉さんに、ほら、この辺りに、と言うと、あれま、ほんのちょっとの間に虫の姿が消えていた。お姉さんと並んで虫を探していると、いた。上辺右隅の「ASO 53」のサインの「0」のところにじっとしている(ここも帯といえば帯になっている)。お姉さんも、あ、と言って、学芸員に知らせます、と言う。学芸員はこの虫をどうするのだろう、と思ったが、あとはお姉さんに任せて鉛筆を借りて一旦その場を離れた。
花を描いた絵が登場する。朱色の上と下の帯状の枠が花の絵では四辺に延びようとしている。
振り返るとデッサンがある。
ちょっと進むと土門拳が当時麻生家を撮影した写真パネルがある。
わざわざ知らせてくださったんだ、ありがたいなあ、楽しみだなあ、と思ったのだったが、その後ボヤボヤしていたらとっくに「麻生三郎展」は始まってしまって、明日は行くぞ、明日こそは行くぞ、と思っているうちに、会期の残りが一週間になってしまった。
で、雨の日曜日の午前中、家人と共に用賀駅に降り立つと、家人はこの先はバスで行く、と言う。美術館行きバスは一時間に一本だけで、しばらく来ないのが分かった。成城学園駅行きが来たので小田急線方向に行くのならこれでもいいはず、と当てずっぽうで乗り込むと、家人は運転手さんに、美術館に行くにはどこで降りるのかしら? とか何とか聞いている。運転手さんは、えと、砧、、、かな? と自信なさげに言っているのが聞こえた。
バスを降りたところは初めての道筋にあるバス停だった。やむを得ず、時々見える清掃工場の煙突を目印に歩き始めた。じきに案内板が見つかってその矢印に従って行く。つまり、どのバスに乗ればいいのかすら忘れてしまっていたのである。とは言え、初めての道筋をしばらく歩いて何とか公園に辿り着けた。緑が美しかった。
麻生三郎の大きな展覧会は東京国立近代美術館以来、十数年ぶりである。
その間にOさんと知り合った。ある日、Oさんがきちんと額装された麻生三郎のペンデッサンを貸してくださった。本物だ。貸してくださったいきさつは忘れてしまった。運河べりの風景が描かれていた。せっかくだから、と模写してみると、現場でいかにも素早く描かれたかのようなその風景のデッサンが、微細な点の一つ一つに至るまで、実に構成的な意志を伴って描かれていることに気がついて驚嘆した。す、すごい!
模写に「ASO」のサインを真似て「ASSO」と書き込んでおどけ、驚きをごまかした。その模写をしまい込み(行方がわからない)、Oさんにオリジナルをお返しした。その時以来、麻生三郎は特別な人になった。
会場に足を踏み入れると、1948年の「子供」という絵から始まる。その年の暮れに三軒茶屋にアトリエを構えたという。1972年に生田に移るまでの間の仕事が今回は紹介されている。世田谷、というところに着眼しての企画。
1948年、49年、50年と、しばらくの間は娘さんや奥さんがモデルになっていて、背景が黒い油絵が続く。キャンバスの表面が波打っていて、さらに照明で光って、よく見えない。見えないが、黒と言っても単純な黒さではない。厚くなってもなお重ねられた塗り込み、黒さの中に多様な色相が混入しているのが発見できる。一見、アクセントのように朱が与えられたりもするが、アクセントだけの役割にとどまることはない。ある種の象徴性を帯びて、麻生三郎の絵の中に繰り返し現れ出てくる。空襲の火の色か? また、画面の上下に帯状の枠のような領域が現れ出ることがある。これが興味深い。
1950年の「裸A」や1951年の「ひとり」では腕や手の表情が実に巧みである。手や足、目の表情が大きな役割を果たすのは麻生三郎の絵の一貫した特徴だろう。
1953年「母子」を見ていると、額縁にごく小さな虫がついていて、しかも少しずつ動いているのに気がついた。虫を見ていると、やがて額縁を越えて画面上方に”降り立ち”、少し動いては止まり、動いては止まる。監視のお姉さんを手招きして、虫のことを“告げ口”した。お姉さんに、ほら、この辺りに、と言うと、あれま、ほんのちょっとの間に虫の姿が消えていた。お姉さんと並んで虫を探していると、いた。上辺右隅の「ASO 53」のサインの「0」のところにじっとしている(ここも帯といえば帯になっている)。お姉さんも、あ、と言って、学芸員に知らせます、と言う。学芸員はこの虫をどうするのだろう、と思ったが、あとはお姉さんに任せて鉛筆を借りて一旦その場を離れた。
花を描いた絵が登場する。朱色の上と下の帯状の枠が花の絵では四辺に延びようとしている。
振り返るとデッサンがある。
ちょっと進むと土門拳が当時麻生家を撮影した写真パネルがある。




















