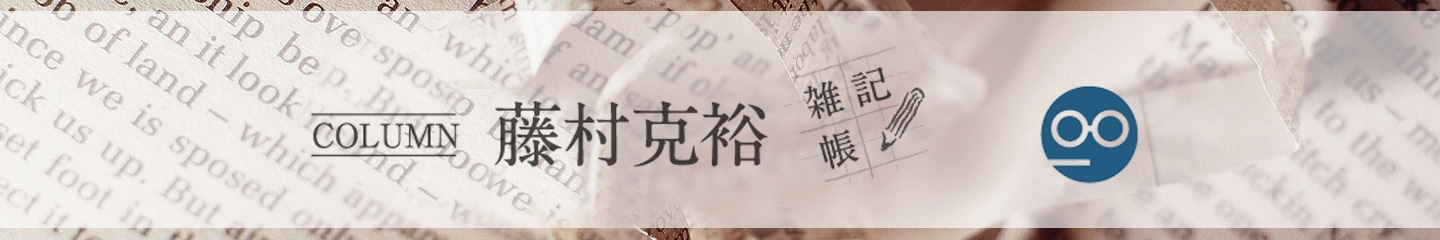

立体作家、元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員の藤村克裕先生のアートについてのコラムです。
藤村克裕 プロフィール
1977年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。
1979年 東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修了。
元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員。
加藤啓、ゾフィー・トイバー&ジャン・アルプ、ヒルマ・アフ・クリント、岡﨑乾二郎など
2025-05-22
またしばらく「雑記帳」が滞ってしまった。申し訳ない。
なんだか、文を書くのが困難になって、書けば、やたら長くなって時間がかかってしまう。読んでくださる方には迷惑な話、それはわかっている。わかっているが、どうすればいいのか自分ではわからない。そこで、文を書くことから意識的に離れてみたが、なにかが起きたわけではなかった。もとのもくあみ、である。
先日、地下鉄・丸ノ内線・四谷三丁目駅の近くの、「四谷ひろば」というところにある「四谷三丁目ランプ坂ギャラリーRAMP」で、加藤啓氏の展示と、それから別の日にパフォーマンスを見た。まったく知らなかった人だが、SNSへのある方の投稿に興味を覚えて、出かけて行った。
「四谷ひろば」は、かつて小学校だったところ。子供が減って、ここの小学校は閉じてしまった。そのあと、有志がここでさまざまな活動をしてきているようである。訪れた日には、体育館で居合の稽古が行われているのが見えた。稽古着に刀(模擬刀であろうが)姿の男女が十人ほど。居合は、人間を日本刀で斬ったり突き刺したりする技術の体系なので、ハタから見ているだけでこわい。なので、居合の見物はほどほどにして、ギャラリーに向かった。
ランプ坂ギャラリーには三つのスペースがある(廊下も含めれば四つ)。そのうちの最初の会場と廊下には、なにやら不思議な物品=人形やオブジェが、壁沿いや展示台の上にたくさん吊られたり置かれたりしていた。どうやら、海岸や川辺で拾い上げて持ち帰った流木や貝殻、プラスチックのゴミ、空き缶、‥‥などを相互に針金でつないでつくったもののようであった。会場を埋め尽くすほどの数の人形やオブジェ、片隅にはペンチや針金などが置かれた作業机もあって、どうやら会期中にも、そこで修繕や新作のための作業を行なっているようだ。会場に踏み込んだ時には、一見、雑然とした印象だったが、随所に工夫があるのがわかってくると、作者の細やかな視線や手ざわりがジワジワと伝わってくる。
ひとつひとつに見入ろうとしていると、奥の方からガラガラと音を立てて、大きな人形を持った背の高いやせた年かさの男性が現れて、横に渡して張ってあった針金にその人形からの針金を引っかけてふたたび奥に消えた。どうやらこれらをつくった加藤啓氏のようだ。修繕がすんだのだろうか。
ふたたび人形たちに見入ろうとしていると、ガッシャン! と大きな音がした。横に渡した針金が外れてさっきの人形が床に落ちてしまったのである。
慌てるでもなく、さっきの男性がもう一度現れて、外れた針金をあらため、床にうずくまって落ちた人形の具合を確かめ始めた。つい、お手伝いしましょうか? と声をかけると、いいえ、大丈夫です、と言った。背中が、放っておいて頂戴! と言っていたので、その場を離れ、人形のひとつひとつに見入っているうちに、男性のことを忘れてしまった。
言ってみれば「見立て」による仕事である。多く使われている流木にはできるだけ手を加えないように配慮されている。拾得物相互を針金で繋いで人間や動物や魚や鳥や虫などをつくる、と決めている。関節や節のところでつないであるから、動く。というか、動くように作っていく。操り人形としての仕掛けがこれも針金で加えられていく。とても面白い。強引すぎるような「見立て」さえたびたびなされ、そうなってくると俄然面白くなる。
二つ目の部屋にあったオブジェの方は、舟や船、楽器というか音具のようなもの、富士山、‥‥など。窓を巧みに使っている。展示に用いられているテーブルに、白い布がさりげなく掛けられているのが人形やオブジェへの愛情を感じさせている。ここにも多くの人形が吊り下げられている。
三つ目の部屋には、絵や紙で作ったレリーフが並んでいた。船や海をテーマとした作品群だった。
会場を二巡し、男性=加藤氏とお話しできた。人形やオブジェは鎌倉の海や三浦海岸で拾ったものでつくっている、と言った。昔、故大野一雄氏のところにいたことがある、とも言った。つまりダンスの心得がある人なのである。その後、新宿区の小学校の教員となって定年まで勤め上げたが、若い頃から緑内障で、いまは片方の目がほとんど見えない、とも言った。「ランプ坂ギャラリー」ではすでに何度も展示をしてきたという。展示のためのさりげない工夫がじつに合理的で感心させられたが、そのよってきたるところが理解できた。思わず、なにか買って帰りたくなって申し出ると、私がとりわけ気に入った作品は、パフォーマンスに使うので売れない、と言った。やむをえず、値段をつけて展示してある中から、ひとつ選んで買わせてもらった。いま、リビングの壁にぶら下げてある。とても気に入っている。
なんだか、文を書くのが困難になって、書けば、やたら長くなって時間がかかってしまう。読んでくださる方には迷惑な話、それはわかっている。わかっているが、どうすればいいのか自分ではわからない。そこで、文を書くことから意識的に離れてみたが、なにかが起きたわけではなかった。もとのもくあみ、である。
先日、地下鉄・丸ノ内線・四谷三丁目駅の近くの、「四谷ひろば」というところにある「四谷三丁目ランプ坂ギャラリーRAMP」で、加藤啓氏の展示と、それから別の日にパフォーマンスを見た。まったく知らなかった人だが、SNSへのある方の投稿に興味を覚えて、出かけて行った。
「四谷ひろば」は、かつて小学校だったところ。子供が減って、ここの小学校は閉じてしまった。そのあと、有志がここでさまざまな活動をしてきているようである。訪れた日には、体育館で居合の稽古が行われているのが見えた。稽古着に刀(模擬刀であろうが)姿の男女が十人ほど。居合は、人間を日本刀で斬ったり突き刺したりする技術の体系なので、ハタから見ているだけでこわい。なので、居合の見物はほどほどにして、ギャラリーに向かった。
ランプ坂ギャラリーには三つのスペースがある(廊下も含めれば四つ)。そのうちの最初の会場と廊下には、なにやら不思議な物品=人形やオブジェが、壁沿いや展示台の上にたくさん吊られたり置かれたりしていた。どうやら、海岸や川辺で拾い上げて持ち帰った流木や貝殻、プラスチックのゴミ、空き缶、‥‥などを相互に針金でつないでつくったもののようであった。会場を埋め尽くすほどの数の人形やオブジェ、片隅にはペンチや針金などが置かれた作業机もあって、どうやら会期中にも、そこで修繕や新作のための作業を行なっているようだ。会場に踏み込んだ時には、一見、雑然とした印象だったが、随所に工夫があるのがわかってくると、作者の細やかな視線や手ざわりがジワジワと伝わってくる。
ひとつひとつに見入ろうとしていると、奥の方からガラガラと音を立てて、大きな人形を持った背の高いやせた年かさの男性が現れて、横に渡して張ってあった針金にその人形からの針金を引っかけてふたたび奥に消えた。どうやらこれらをつくった加藤啓氏のようだ。修繕がすんだのだろうか。
ふたたび人形たちに見入ろうとしていると、ガッシャン! と大きな音がした。横に渡した針金が外れてさっきの人形が床に落ちてしまったのである。
慌てるでもなく、さっきの男性がもう一度現れて、外れた針金をあらため、床にうずくまって落ちた人形の具合を確かめ始めた。つい、お手伝いしましょうか? と声をかけると、いいえ、大丈夫です、と言った。背中が、放っておいて頂戴! と言っていたので、その場を離れ、人形のひとつひとつに見入っているうちに、男性のことを忘れてしまった。
言ってみれば「見立て」による仕事である。多く使われている流木にはできるだけ手を加えないように配慮されている。拾得物相互を針金で繋いで人間や動物や魚や鳥や虫などをつくる、と決めている。関節や節のところでつないであるから、動く。というか、動くように作っていく。操り人形としての仕掛けがこれも針金で加えられていく。とても面白い。強引すぎるような「見立て」さえたびたびなされ、そうなってくると俄然面白くなる。
二つ目の部屋にあったオブジェの方は、舟や船、楽器というか音具のようなもの、富士山、‥‥など。窓を巧みに使っている。展示に用いられているテーブルに、白い布がさりげなく掛けられているのが人形やオブジェへの愛情を感じさせている。ここにも多くの人形が吊り下げられている。
三つ目の部屋には、絵や紙で作ったレリーフが並んでいた。船や海をテーマとした作品群だった。
会場を二巡し、男性=加藤氏とお話しできた。人形やオブジェは鎌倉の海や三浦海岸で拾ったものでつくっている、と言った。昔、故大野一雄氏のところにいたことがある、とも言った。つまりダンスの心得がある人なのである。その後、新宿区の小学校の教員となって定年まで勤め上げたが、若い頃から緑内障で、いまは片方の目がほとんど見えない、とも言った。「ランプ坂ギャラリー」ではすでに何度も展示をしてきたという。展示のためのさりげない工夫がじつに合理的で感心させられたが、そのよってきたるところが理解できた。思わず、なにか買って帰りたくなって申し出ると、私がとりわけ気に入った作品は、パフォーマンスに使うので売れない、と言った。やむをえず、値段をつけて展示してある中から、ひとつ選んで買わせてもらった。いま、リビングの壁にぶら下げてある。とても気に入っている。




















