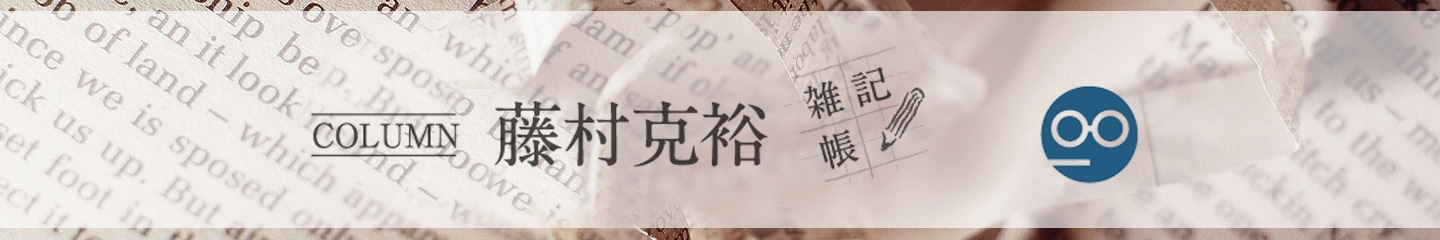

立体作家、元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員の藤村克裕先生のアートについてのコラムです。
藤村克裕 プロフィール
1977年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。
1979年 東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修了。
元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員。
武蔵美の市ヶ谷キャンパス
2020-02-19
駅近くのパン屋に寄ってから、都営新宿線・市ヶ谷駅まで移動した。伊藤誠氏の作品が展示されている、という情報を得ていたので、武蔵美の市ヶ谷キャンパスに立ち寄ったのである。ビル一階の無印良品の店舗に作品が紛れ込んでいる。
小林耕平氏のヴィデオ作品『瞬間レリーフ』に笑ってしまった。大真面目な顔で実にとぼけたやり取りを山形育弘氏と繰り広げる。その中に登場する「参考作品」や「試作品」の現物も展示されている。そのうちの一つをご紹介させていただく。グラスの口を押し付けてできたマルはハンドル。「八」の字型の線二本で道。穴はトンネル。六角形の箸を突き刺して作ってある。上部の塊は山。
手前にあるべきもの(ハンドル)が一番奥にあって、一番奥にあるはずのもの(山)が一番手前にあるレリーフだ、と言っている。
山の作り方がすごい。どうすごいかは、実際をヴィデオ映像でご覧いただきたい。笑う以外のことができない。
別の『瞬間レリーフ』作品について、山形氏が、地表を裏側から踏みつけたみたい、とか気の利いたコメントをしたりもする。そういうメリハリが身上だろう。
一息ついて、新宿方面に靖国通りを歩き出しながら、思わず“瞬間レリーフごっこ”をしてしまっていた。素直に路上に落ちていたものを拾い上げて持ち帰ってしまった。
防衛省前を渡ろうとしたら、赤信号です! と叱られた。
どんどん歩いて気がつくと12500歩を超えていた。えらい!
(2020年2月18日、東京にて)
小林耕平氏のヴィデオ作品『瞬間レリーフ』に笑ってしまった。大真面目な顔で実にとぼけたやり取りを山形育弘氏と繰り広げる。その中に登場する「参考作品」や「試作品」の現物も展示されている。そのうちの一つをご紹介させていただく。グラスの口を押し付けてできたマルはハンドル。「八」の字型の線二本で道。穴はトンネル。六角形の箸を突き刺して作ってある。上部の塊は山。
手前にあるべきもの(ハンドル)が一番奥にあって、一番奥にあるはずのもの(山)が一番手前にあるレリーフだ、と言っている。
山の作り方がすごい。どうすごいかは、実際をヴィデオ映像でご覧いただきたい。笑う以外のことができない。
別の『瞬間レリーフ』作品について、山形氏が、地表を裏側から踏みつけたみたい、とか気の利いたコメントをしたりもする。そういうメリハリが身上だろう。
一息ついて、新宿方面に靖国通りを歩き出しながら、思わず“瞬間レリーフごっこ”をしてしまっていた。素直に路上に落ちていたものを拾い上げて持ち帰ってしまった。
防衛省前を渡ろうとしたら、赤信号です! と叱られた。
どんどん歩いて気がつくと12500歩を超えていた。えらい!
(2020年2月18日、東京にて)
風間サチ子展
2020-02-19
天気の良い火曜日である。
朝9時半過ぎにテクテク最寄りの警察署の生活安全課に行った。
先週、その警察署から電話があって、法律が変わるのでちゃんと手続きしないと3月いっぱいを過ぎるとあなたの古物商の“免許”が失効してしまいますよ、と言われた。それで、慌てて“出頭”したのだ。なにせ私は、古本屋も営む多角個人営業主。古物商の“免許”がなくなっては困ってしまう。毎年、講習会があるのだが、去年はその当日に熱を出してダウンし、欠席してしまった。欠席の届けを電話でした時、書類は郵送すればいいか? と尋ねたら、あなたがちゃんと警察まで持って来なさい、と言われていたのだった。それを完全に忘れてしまっていた。おまけにもう、書類のありかがわからなくなっている。どこかにしまい込んだのだろうが、全く思い出せない。叱られるのを覚悟して、でも、やっぱり恐る恐る行った。
係の人は親切で、半ば呆れながらも色々教えてくれた。おかげで、書類も書けてそのまま提出できた。係の人は、これでもう大丈夫、と言ってくれた。
帰路、通り沿いに行列ができている。見れば薬屋。開店を待っているようだ。ちょうど前の方が動き始めたところなので、好奇心もあって最後尾に並んでみた。箱入りのマスクを一箱ずつ持った人たちが出てくる。しずしずと私がマスク売り場に着いた時には、もちろん箱などはなく、数枚入りの袋が一つだけ残っていた。ちょっと迷ったけど、それを買った。消毒用のアルコールも探したが無かった。何かあると、あっ!という間に物がなくなる。それがわかっているのに、ひょっとしたら、と探してみる自分が情けない。
一旦家に戻って、午後、都営新宿線・菊川駅から「無人島プロジェクト」をめざした。清澄白河から引っ越し後、初めて訪れる。「風間サチコ展」。
ムッチャかっこいい。建物も内部も作品も。
かつてはダンボール工場だったそうだが、長い間(三十年間だったか)使われていなかったという。置き去りにされていた機械類など7トン分を片付け、掃除し、さらに手を入れて現在のようにしたそうだ。専門家の力も借りた、と言うが、基本的に自分たちでやった、と「無人島プロジェクト」の人は教えてくれた。さぞ大変だっただろう。大変でもこんなにかっこいい。報われている。
建物の外観を写真で示す。が、中の様子は、どうか実際に訪れて体感していただきたい。
風間サチコ氏の作品は、いつもながらの力技だが、旧作も含めた展示でバラエティにとんでいる。明らかにインスタレーションの要素のある作品もあった。
聞けば、事前の調査は実に綿密に行われるという。今回は石灰岩、セメント、コンクリートという土木素材の変容、その素材のスイを尽くした黒部ダム、石灰岩の産地の武甲山、労働者などがテーマに取り上げられている。いつもながら、力強いノミ跡のキレが、重いテーマから観客の目がそれることを許さない。とはいえ、ユーモアをも感じさせてくれる。版そのものが作品に動員されているのも興味深い。版をフロッタージュすることも行われている。仕事を自在に揺さぶっている様子は、誠に頼もしい。今後も続くという発表が楽しみだ。
つづく→
朝9時半過ぎにテクテク最寄りの警察署の生活安全課に行った。
先週、その警察署から電話があって、法律が変わるのでちゃんと手続きしないと3月いっぱいを過ぎるとあなたの古物商の“免許”が失効してしまいますよ、と言われた。それで、慌てて“出頭”したのだ。なにせ私は、古本屋も営む多角個人営業主。古物商の“免許”がなくなっては困ってしまう。毎年、講習会があるのだが、去年はその当日に熱を出してダウンし、欠席してしまった。欠席の届けを電話でした時、書類は郵送すればいいか? と尋ねたら、あなたがちゃんと警察まで持って来なさい、と言われていたのだった。それを完全に忘れてしまっていた。おまけにもう、書類のありかがわからなくなっている。どこかにしまい込んだのだろうが、全く思い出せない。叱られるのを覚悟して、でも、やっぱり恐る恐る行った。
係の人は親切で、半ば呆れながらも色々教えてくれた。おかげで、書類も書けてそのまま提出できた。係の人は、これでもう大丈夫、と言ってくれた。
帰路、通り沿いに行列ができている。見れば薬屋。開店を待っているようだ。ちょうど前の方が動き始めたところなので、好奇心もあって最後尾に並んでみた。箱入りのマスクを一箱ずつ持った人たちが出てくる。しずしずと私がマスク売り場に着いた時には、もちろん箱などはなく、数枚入りの袋が一つだけ残っていた。ちょっと迷ったけど、それを買った。消毒用のアルコールも探したが無かった。何かあると、あっ!という間に物がなくなる。それがわかっているのに、ひょっとしたら、と探してみる自分が情けない。
一旦家に戻って、午後、都営新宿線・菊川駅から「無人島プロジェクト」をめざした。清澄白河から引っ越し後、初めて訪れる。「風間サチコ展」。
ムッチャかっこいい。建物も内部も作品も。
かつてはダンボール工場だったそうだが、長い間(三十年間だったか)使われていなかったという。置き去りにされていた機械類など7トン分を片付け、掃除し、さらに手を入れて現在のようにしたそうだ。専門家の力も借りた、と言うが、基本的に自分たちでやった、と「無人島プロジェクト」の人は教えてくれた。さぞ大変だっただろう。大変でもこんなにかっこいい。報われている。
建物の外観を写真で示す。が、中の様子は、どうか実際に訪れて体感していただきたい。
風間サチコ氏の作品は、いつもながらの力技だが、旧作も含めた展示でバラエティにとんでいる。明らかにインスタレーションの要素のある作品もあった。
聞けば、事前の調査は実に綿密に行われるという。今回は石灰岩、セメント、コンクリートという土木素材の変容、その素材のスイを尽くした黒部ダム、石灰岩の産地の武甲山、労働者などがテーマに取り上げられている。いつもながら、力強いノミ跡のキレが、重いテーマから観客の目がそれることを許さない。とはいえ、ユーモアをも感じさせてくれる。版そのものが作品に動員されているのも興味深い。版をフロッタージュすることも行われている。仕事を自在に揺さぶっている様子は、誠に頼もしい。今後も続くという発表が楽しみだ。
つづく→
森田恒友展
2020-02-10
テニスコートの横を通って行くと、つい笑ってしまいそうになる不思議な形の彫刻があった。ここにあの浦和高校があったことを記念して設置された“モニュメント”だった。作者は柳原義達。想定外のこんなことがあるので、いつもと違う道筋で歩くのは楽しい。遠足の醍醐味。
タマキンでは「森田恒友展」。予想以上に面白かった。
森田は、1881年現在の熊谷市の生まれ、というからピカソと同じ年齢だ。20歳の時、東京に出て、中村不折に師事するが、中村不折の留学により小山正太郎の塾へ移り、やがて東京美術学校入学。青木繁や熊谷守一とは二学年下。首席卒業。1914年渡仏。1915年帰国。1922年、春陽会結成。1933年、食道癌で死去。
最初期のデッサンから最晩年の風景画まで、デッサン、油彩、水墨、木版、挿絵、‥‥、そして文章、と驚くほど多彩な形式を自在に駆使している様子に驚かされた。その器用さだけでなく、この時代にはすでに様々な表現の「様式」を対象化してその都度選択できるようになっていたのだろうか。とはいえ、渡仏後のセザンヌへの傾倒ぶりと、次第に自分のものにしていく様子には、冷静でおられぬ迫力がある。とりわけ、“森田様式”ともいえそうな最晩年の風景画に至る様子は、静かながら大変な迫力を含んでいる。初期の1907年作の「湖畔」、この素晴らしい作品をものしたこの人にして、またこの凄まじいほどの制作量にして、ようやく到達し得たであろう1930年代の作品の持つ意味については、いずれきちんと考えてみたい。
そんなわけで、ヘトヘトになって京浜東北線・北浦和駅から電車に乗った。幸い座ることができてホッとした。バチが当たりそうなほどの満足感満載の遠足。一万歩軽く突破!
(2月8日、東京にて)
タマキンでは「森田恒友展」。予想以上に面白かった。
森田は、1881年現在の熊谷市の生まれ、というからピカソと同じ年齢だ。20歳の時、東京に出て、中村不折に師事するが、中村不折の留学により小山正太郎の塾へ移り、やがて東京美術学校入学。青木繁や熊谷守一とは二学年下。首席卒業。1914年渡仏。1915年帰国。1922年、春陽会結成。1933年、食道癌で死去。
最初期のデッサンから最晩年の風景画まで、デッサン、油彩、水墨、木版、挿絵、‥‥、そして文章、と驚くほど多彩な形式を自在に駆使している様子に驚かされた。その器用さだけでなく、この時代にはすでに様々な表現の「様式」を対象化してその都度選択できるようになっていたのだろうか。とはいえ、渡仏後のセザンヌへの傾倒ぶりと、次第に自分のものにしていく様子には、冷静でおられぬ迫力がある。とりわけ、“森田様式”ともいえそうな最晩年の風景画に至る様子は、静かながら大変な迫力を含んでいる。初期の1907年作の「湖畔」、この素晴らしい作品をものしたこの人にして、またこの凄まじいほどの制作量にして、ようやく到達し得たであろう1930年代の作品の持つ意味については、いずれきちんと考えてみたい。
そんなわけで、ヘトヘトになって京浜東北線・北浦和駅から電車に乗った。幸い座ることができてホッとした。バチが当たりそうなほどの満足感満載の遠足。一万歩軽く突破!
(2月8日、東京にて)
ヒヤシンス・ハウス
2020-02-10
天気予報が、冷え込むぞ! と驚かせていた土曜日は快晴。寒さはそれほどでもなかった。
電車に乗って川を越えると「遠出」した気がするものだ。よし、遠足だ。目指すは、中浦和・別所沼公園。立原道造設計の「ヒヤシンスハウス」がそこにある(はずだ)。数日前の新聞に、小さな記事が出ていた。「早世の建築家、夢見た小屋」。
この「小屋」のことは知っていた。ずっと興味もあったのに、どこにあるか知らなかった。調べようともしなかった。急に情報が“向こう”から飛び込んできたのである。逃す手はない。
埼京線・中浦和駅ホームは高いところにある。周囲を眺めると、並んだ屋根の向こうに梢が集まっているところがあった。あそこだな。見当をつけて歩き出した。
ものの数分で別所沼公園近くまで着いたが、入口がわからない。テキトーに行くと駐車場があった。突っ切れば公園の中に入れそうだ。ぐんぐん進むと、入れただけでなく、なんと、目の前にあっけなく目指す「ヒヤシンスハウス」があった。窓が開いていて人の気配がしていた。
周囲をゆっくり一周して、外観を確認したあと、中に入った。
明るくてじつにスッキリ心地いい。5坪ほどの「小屋」なのに、狭さを全く感じさせない。
ボランティアらしきご婦人がいた。手際よくまとめられた『ヒアシンスハウス・ガイド』を手渡してくれた。ご婦人は、あくまでも控えめ。何か問われればそれに答える、というようにしている。押し付けがましくない。とても感じがいい。見学者の関心を重んじてくれている。かなりの時間をゆっくり過ごしながら、ご婦人から少しずつ教わった。
小屋の構造を支える柱から離して外側に窓と雨戸とを作っている。それが広々とした印象を生んでいる。収納機能もあるベンチの前のテーブル、仕事机、出窓の下辺、これらの高さがほぼ同じで、しかし、ごくわずかに高さが異なって絶妙なリズムを感じさせているのも広さを感じさせている。一枚板の仕事机の一部がそのままベットの頭の上の方まで伸びている。これも実に効果的だ。窓の大きさ、配置がものすごくいい。太陽光を取り込む側の窓と仕事をする側との窓とがうまく役割分担されている。ベッドの脇の小さな出窓、惚れ惚れとする。暗がりの中にアクセントのように明るさを作り出している。トイレや“押入れ”の配置も絶妙、「小屋」内部の全体をスッキリさせている。
でも、台所がない。ご婦人は、立原道造がこの小屋を構想していた時には、すでに結核が進んでいて、料理をしない(してはならない)ことが前提だった、と教えてくれた。切なすぎる。立原道造は24歳で亡くなった(そうだ)。
また、ご婦人は、わざわざ雨戸を閉めてくれて、そこに小さく十字がくり抜かれていること、同じ十字が仕事机とセットになっている椅子の背にも切り抜かれていることを示してくれたりもした。
玄関の作り、その玄関への飛び石と玄関脇に添えられた大きな直方体の石、小屋に居る/居ないを示すノボリをあげるための竿、その土台、、、。
「ヒアシンスハウス」は、立原道造という人の構想力、細部まで納得いくまで分け入ろうとするデリカシーを十分すぎるほど感じさせてくれた。
「ヒアシンスハウス」をあとにして、北浦和のタマキン(埼玉県立近代美術館)を目指してみた。そう遠くもないだろう、と方角の見当だけつけて、前方に伸びる自分の影に従ってどんどん歩いた。二十分間くらいか、ぴったりタマキンの「搬入口」のある通りに着いた。ほら、おいら、やるじゃん。
つづく→
電車に乗って川を越えると「遠出」した気がするものだ。よし、遠足だ。目指すは、中浦和・別所沼公園。立原道造設計の「ヒヤシンスハウス」がそこにある(はずだ)。数日前の新聞に、小さな記事が出ていた。「早世の建築家、夢見た小屋」。
この「小屋」のことは知っていた。ずっと興味もあったのに、どこにあるか知らなかった。調べようともしなかった。急に情報が“向こう”から飛び込んできたのである。逃す手はない。
埼京線・中浦和駅ホームは高いところにある。周囲を眺めると、並んだ屋根の向こうに梢が集まっているところがあった。あそこだな。見当をつけて歩き出した。
ものの数分で別所沼公園近くまで着いたが、入口がわからない。テキトーに行くと駐車場があった。突っ切れば公園の中に入れそうだ。ぐんぐん進むと、入れただけでなく、なんと、目の前にあっけなく目指す「ヒヤシンスハウス」があった。窓が開いていて人の気配がしていた。
周囲をゆっくり一周して、外観を確認したあと、中に入った。
明るくてじつにスッキリ心地いい。5坪ほどの「小屋」なのに、狭さを全く感じさせない。
ボランティアらしきご婦人がいた。手際よくまとめられた『ヒアシンスハウス・ガイド』を手渡してくれた。ご婦人は、あくまでも控えめ。何か問われればそれに答える、というようにしている。押し付けがましくない。とても感じがいい。見学者の関心を重んじてくれている。かなりの時間をゆっくり過ごしながら、ご婦人から少しずつ教わった。
小屋の構造を支える柱から離して外側に窓と雨戸とを作っている。それが広々とした印象を生んでいる。収納機能もあるベンチの前のテーブル、仕事机、出窓の下辺、これらの高さがほぼ同じで、しかし、ごくわずかに高さが異なって絶妙なリズムを感じさせているのも広さを感じさせている。一枚板の仕事机の一部がそのままベットの頭の上の方まで伸びている。これも実に効果的だ。窓の大きさ、配置がものすごくいい。太陽光を取り込む側の窓と仕事をする側との窓とがうまく役割分担されている。ベッドの脇の小さな出窓、惚れ惚れとする。暗がりの中にアクセントのように明るさを作り出している。トイレや“押入れ”の配置も絶妙、「小屋」内部の全体をスッキリさせている。
でも、台所がない。ご婦人は、立原道造がこの小屋を構想していた時には、すでに結核が進んでいて、料理をしない(してはならない)ことが前提だった、と教えてくれた。切なすぎる。立原道造は24歳で亡くなった(そうだ)。
また、ご婦人は、わざわざ雨戸を閉めてくれて、そこに小さく十字がくり抜かれていること、同じ十字が仕事机とセットになっている椅子の背にも切り抜かれていることを示してくれたりもした。
玄関の作り、その玄関への飛び石と玄関脇に添えられた大きな直方体の石、小屋に居る/居ないを示すノボリをあげるための竿、その土台、、、。
「ヒアシンスハウス」は、立原道造という人の構想力、細部まで納得いくまで分け入ろうとするデリカシーを十分すぎるほど感じさせてくれた。
「ヒアシンスハウス」をあとにして、北浦和のタマキン(埼玉県立近代美術館)を目指してみた。そう遠くもないだろう、と方角の見当だけつけて、前方に伸びる自分の影に従ってどんどん歩いた。二十分間くらいか、ぴったりタマキンの「搬入口」のある通りに着いた。ほら、おいら、やるじゃん。
つづく→
府中市美術館「青木野枝 霧と鉄と山と」展をみた その2
2020-02-07
今回の展示では、場を作り出す、というより、8点ずつひとまとまりの作品、という見え方になっている。もちろん対になって一つの作品、という場合もあるし、石膏で作られた『原形質』(2012年)越しに1981年の『untitled』や1992年の『untitled』が一体に見えてくるような場合もある。あるが、やはり8点それぞれ一つずつの彫刻、と見える。
とは言え、2019年作の『霧と鉄と山—Ⅰ』。床に置かれた鉄とガラスによる巨大な作品。これと、ガラスで仕切られた“ぐるり”の壁に一定の間隔で何枚も下げられた縦長の同じ寸法の樹脂製の何枚もの波板、これらの関係についてはビミョーであった。
リストではこれらは一つの作品とされている。が、壁にずらーっと連なるガラス板の仕切りのせいか、床の作品と壁の波板群、これらを一体の作品として感じ取るのは、なかなか難しい。波板はごくわずかに手前方向に湾曲させられており、そのせいか波板の一枚一枚それぞれが「彫刻」を感じさせる。私は、一体に見えなくてもいいではないか、と楽しんだ。
2019年作の『霧と鉄と山-Ⅱ』も楽しんだ。鉄板を溶断して作ったたくさんの「丸」が相互に溶接されて、大きなお椀を伏せたような、ドームのような、イグルーのような、つまり応力に強い形状、青木氏の作品に度々登場する形状だが、その形状に二本の“ツノ”、いや“ラッパ”、“吹き出し”、どう呼んでもしっくりこないが、が生えている。とても強い形状だ。不思議だし。「丸」のところどころには手製らしき色ガラスがはめ込まれていてアクセントを成しているが、注目すべきは、丸と丸との間の隙間。え、ここ繋がなくて大丈夫? というような見え方を生じている。もちろん鉄なので「点」での溶接で形状を維持・安定させることは可能だ。可能だが、やはりびっくりさせられドキドキする。この作品のためのドローイングやドライポイントの展示もあって、これも実に魅力的である。堪能ということをした。
スケッチブックの展示も嬉しい。その中にこんな文もメモされていたので書き写してきた。
とは言え、2019年作の『霧と鉄と山—Ⅰ』。床に置かれた鉄とガラスによる巨大な作品。これと、ガラスで仕切られた“ぐるり”の壁に一定の間隔で何枚も下げられた縦長の同じ寸法の樹脂製の何枚もの波板、これらの関係についてはビミョーであった。
リストではこれらは一つの作品とされている。が、壁にずらーっと連なるガラス板の仕切りのせいか、床の作品と壁の波板群、これらを一体の作品として感じ取るのは、なかなか難しい。波板はごくわずかに手前方向に湾曲させられており、そのせいか波板の一枚一枚それぞれが「彫刻」を感じさせる。私は、一体に見えなくてもいいではないか、と楽しんだ。
2019年作の『霧と鉄と山-Ⅱ』も楽しんだ。鉄板を溶断して作ったたくさんの「丸」が相互に溶接されて、大きなお椀を伏せたような、ドームのような、イグルーのような、つまり応力に強い形状、青木氏の作品に度々登場する形状だが、その形状に二本の“ツノ”、いや“ラッパ”、“吹き出し”、どう呼んでもしっくりこないが、が生えている。とても強い形状だ。不思議だし。「丸」のところどころには手製らしき色ガラスがはめ込まれていてアクセントを成しているが、注目すべきは、丸と丸との間の隙間。え、ここ繋がなくて大丈夫? というような見え方を生じている。もちろん鉄なので「点」での溶接で形状を維持・安定させることは可能だ。可能だが、やはりびっくりさせられドキドキする。この作品のためのドローイングやドライポイントの展示もあって、これも実に魅力的である。堪能ということをした。
スケッチブックの展示も嬉しい。その中にこんな文もメモされていたので書き写してきた。
府中市美術館「青木野枝 霧と鉄と山と」展をみた その1
2020-02-07
EUからついに離脱したイギリスに、かつてサッチャーという首相がいて、「鉄の女」と言われていた。現代日本の彫刻家・青木野枝氏もまた「鉄の女」である。一貫して鉄で制作を続けている。
だいぶ前のことだけど(いつだったかわかんなくなってる)、分厚い大きな鉄板を溶断して繋いで紙工作の恐竜みたいな形状のムッチャ巨大な青木氏の作品と逆光で出くわしてびっくりしたことがあった。同じような作品は何度か発表されたと思うが、分厚くて大きな鉄板の重さや硬さの感じ、その先入観を、お手軽な工作感覚ではぐらかしている様子が実に面白かった。作るのはさぞ大変だったろうに。
また、これもいつのことだったか記憶が定かではないが、たしか長野でやったアート・フェスティバルの時、いろんな人たちの作品を八王子に一旦集める作業を手伝ったことがあった。運ばれてきて置かれていた青木氏の作品を移動するので軽トラに乗せようとした時、見かけの軽快さに反してとっても重く、私一人では持ち上げるのが無理だった。この時もびっくりした。鉄でできているんだから当然といえば当然だったんだけど。
ともかく、青木氏の作品にはよくびっくりさせられてきた。最近だけでも、何年か前のあいちトリエンナーレ、自由が丘の黒田悠子さんのギャラリー(gall-ery21yo−j)、どれも、迫力満点だった。場全体をやすやすと変容させてしまっていた。ほんとは「やすやす」なんてもんじゃなくて、ものすごく大変なんだろうが、その「大変さ」を微塵も感じさせないのが青木氏のすごいところだ。以前、黒田さんのギャラリーが銀座にあった頃、青木氏の作品を見て、思わず「絶好調だなあ!」とつぶやいてしまって、黒田さんに聞かれて恥ずかしかったこともある。地方に出かけた時など、思いがけないところで青木氏の作品に出くわすことも度々ある。
だいぶ前のことだけど(いつだったかわかんなくなってる)、分厚い大きな鉄板を溶断して繋いで紙工作の恐竜みたいな形状のムッチャ巨大な青木氏の作品と逆光で出くわしてびっくりしたことがあった。同じような作品は何度か発表されたと思うが、分厚くて大きな鉄板の重さや硬さの感じ、その先入観を、お手軽な工作感覚ではぐらかしている様子が実に面白かった。作るのはさぞ大変だったろうに。
また、これもいつのことだったか記憶が定かではないが、たしか長野でやったアート・フェスティバルの時、いろんな人たちの作品を八王子に一旦集める作業を手伝ったことがあった。運ばれてきて置かれていた青木氏の作品を移動するので軽トラに乗せようとした時、見かけの軽快さに反してとっても重く、私一人では持ち上げるのが無理だった。この時もびっくりした。鉄でできているんだから当然といえば当然だったんだけど。
ともかく、青木氏の作品にはよくびっくりさせられてきた。最近だけでも、何年か前のあいちトリエンナーレ、自由が丘の黒田悠子さんのギャラリー(gall-ery21yo−j)、どれも、迫力満点だった。場全体をやすやすと変容させてしまっていた。ほんとは「やすやす」なんてもんじゃなくて、ものすごく大変なんだろうが、その「大変さ」を微塵も感じさせないのが青木氏のすごいところだ。以前、黒田さんのギャラリーが銀座にあった頃、青木氏の作品を見て、思わず「絶好調だなあ!」とつぶやいてしまって、黒田さんに聞かれて恥ずかしかったこともある。地方に出かけた時など、思いがけないところで青木氏の作品に出くわすことも度々ある。




















